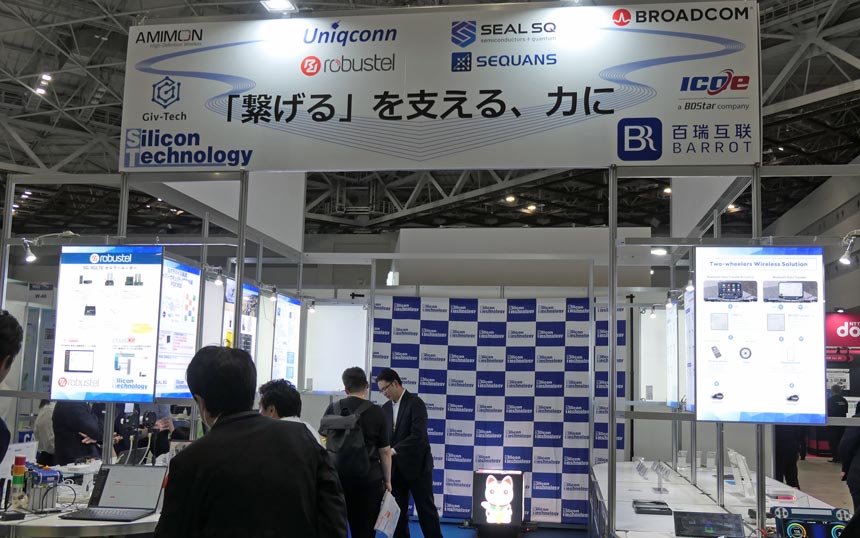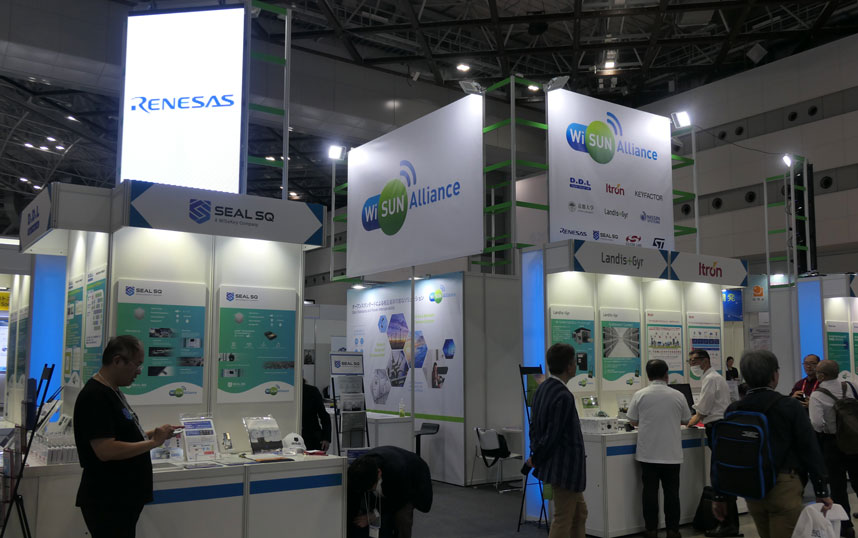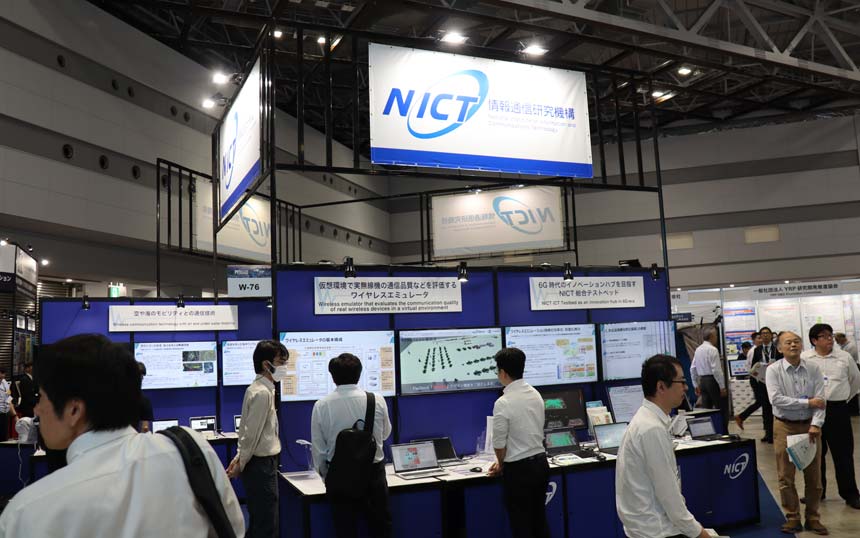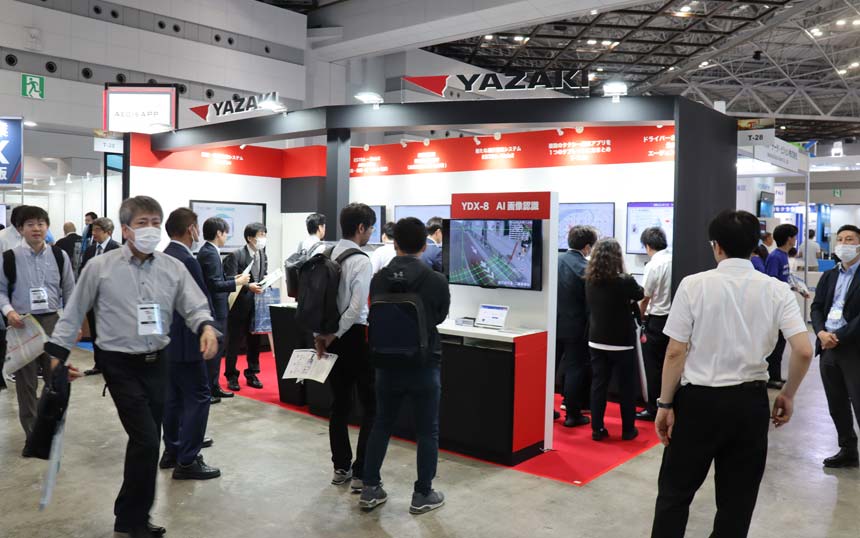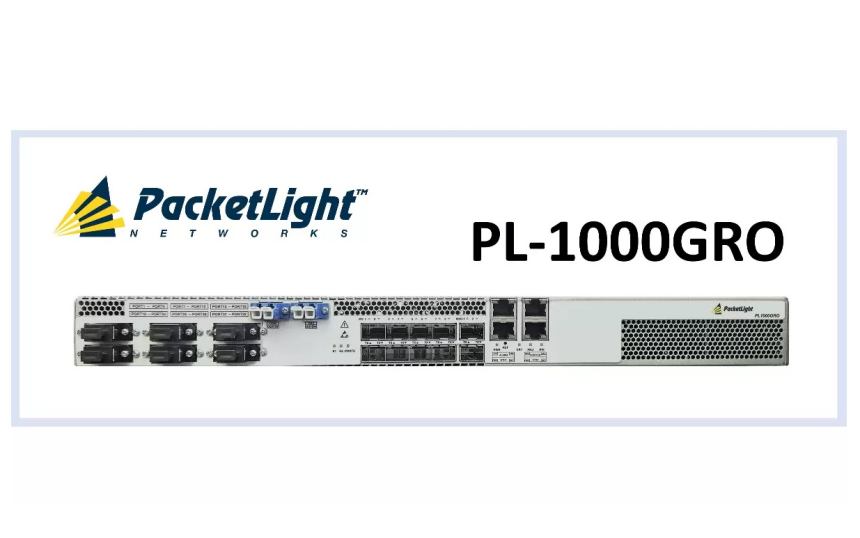エンジンやライト、カーナビなど自動車のあらゆる部品・機能は、ECU(Electronic Control Unit)と呼ばれる電子制御コンピューターによって制御される。加えて昨今は、周辺状況を検知するためのカメラやレーダーの搭載が進み、それらのデータをECUへ集め、被害軽減ブレーキやレーンキープアシストといった運転支援システム(ADAS)に活用している。これらは、自動運転の実現にも欠かせない技術だ。
クルマの高度化とともにECUやセンサーの数は増加。現在は1台当たり平均30、高級車では100超のECUが搭載されている。ソフトウェアによって性能・機能が決定付けられるSDV、そして自動運転の実現に向けて、その数はさらに増えていくだろう。
そこで存在感を増しているのが、センサー/アクチュエーター(モーターやシリンダー等)、ECUをつなぎ、制御信号やデータを伝送する車載ネットワークだ。その飛躍的な進歩をもたらすのがイーサネット、そして光ファイバー通信である。
車載ネットワークの現状 ドメイン型からゾーン型へ
車載ネットワークは、クルマという特殊環境の中で独自の進化を遂げてきた(図表1)。CAN(Control Area Network)、LIN(Local Interconnect Network)、MOST(Media Oriented Systems Transport)、FlexRayなど複数の通信方式を用途・機能に応じて使い分け、改良を続けてきた。CANはパワートレイン系、比較的広帯域なMOSTはカーナビ/AV系、FlexRayはカメラやLiDAR等の安全系、LINはウィンドウやミラー等のボディ系といった具合だ。
図表1 車載ネットワークの標準規格
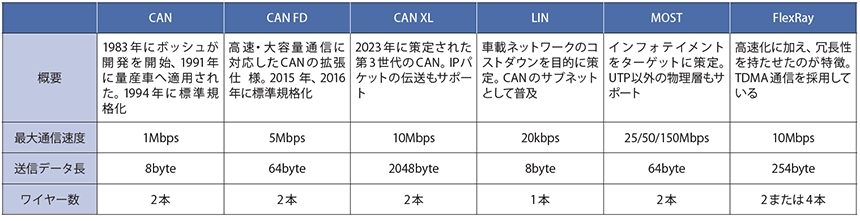
だが、機能ごとにネットワークが独立しているとADASは実現できない。機能間での協調動作が不可欠だからだ。そこで導入されたのが「ドメイン分割型」アーキテクチャである。
これは、機能(ドメイン)ごとに各系統を制御するドメインコントローラー(DC)を置き、このDCをゲートウェイ(GW)を介してつなぎ合わせたものだ(図表2の左)。現在の車載ネットワークの主流となっているが、ADASのために強引に統合したとも言える。そのため多くの課題がある。
図表2 車載ネットワーク・アーキテクチャの変遷
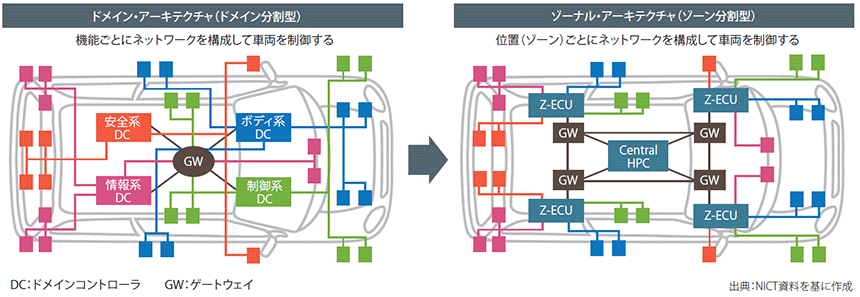
第1が、帯域不足だ。インフォテイメントのために作られたMOSTでも最大150Mbps。車載ネットワークの中核といえるCANについては、最新世代のCAN XLでも最大10Mbpsに過ぎない。車外の状況を認識するのに4Kカメラの画像・映像を使おうとする自動運転時代を見据えれば、甚だ心もとない。
車内の隅々まで配線が伸び、総延長は1台あたり数kmにも及ぶので、遅延の増大も課題となる。ケーブルの重さも車体重量や燃費・電費に悪影響を及ぼす。さらに、各系統がクモの巣状に張り巡らされるため電磁ノイズも増大。この干渉も大きな課題だ。
ゾーンに分けてイーサで連携
これらを解決し、SDV時代、そして自動運転時代を見据えた車載ネットワークをどのように実現するのか。キーポイントは2つ。アーキテクチャの刷新とイーサネットの活用である。
図表2の右は、ドメイン分割型に代わる「ゾーン分割型(ゾーナル・アーキテクチャ)」のイメージだ。クルマを「左前」「右後」などの複数ゾーンに分割してGWを配置。このZonal-GWと、ゾーン内の機器やCAN等の既存網を接続する。配線距離が短くなることで、重量やノイズ等を軽減する。
このゾーン分割と合わせて、ECUもZonal-GWと同数程度に集約する。そして、GWと中央制御コンピューター(Central HPC)間を大容量かつ低遅延なバックボーンで接続。このバックボーンには少なくとも1Gbps、将来的には10G、100Gといった広帯域ネットワークが必要だ。
このバックボーンの最有力候補が、民生用ですでに400/800Gbpsを実現しているイーサネットである。車載向け光通信技術を開発する情報通信研究機構(NICT) ネットワーク研究所 フォトニックICT研究センター 光アクセス研究室 総括研究員の髙橋亮氏は、「将来の自動運転では、データセンターとも交信しながら車載ネットワークで制御を行う。ゾーン分割型のアーキテクチャと、イーサネットをベースにしたネットワークはそれに非常に適している」と話す。
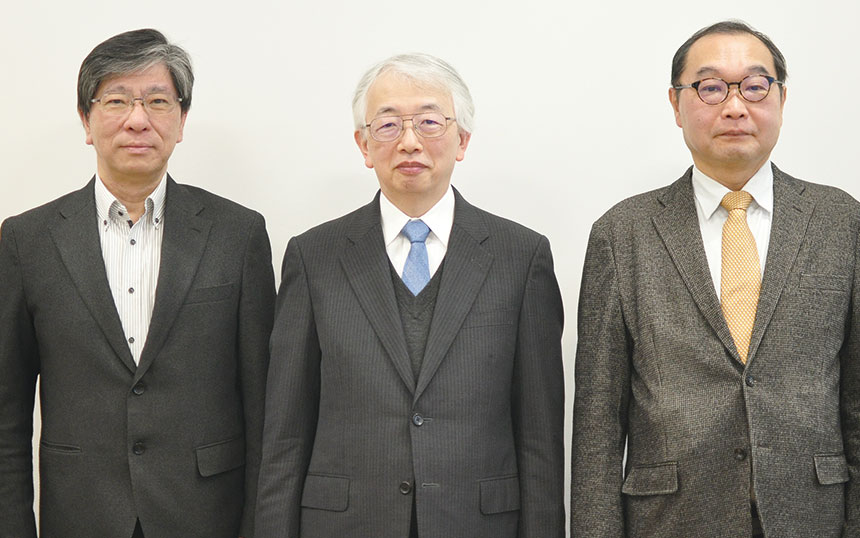
(左から)情報通信研究機構 ネットワーク研究所 フォトニックICT研究センター 光アクセス研究室 総括研究員 博士(工学) 髙橋亮氏、慶應義塾大学 理工学部 電気情報工学科 教授 光機能デバイス/光通信デバイス 博士(工学) 津田裕之氏、古河電気工業 研究開発本部 エレクトロニクス研究所 モビリティ技術開発1部 主席研究員 岩瀬正幸氏
このアーキテクチャの移行はすでに始まっている。車載ネットワーク関連ソリューションを手がけるアナログ・デバイセズのキャビンエクスペリエンスグループでシニアテクニカルリーダーを務める谷島潔氏によれば、「特に欧米のOEMでアーキテクチャの移行が進んでいる。その中でイーサネットが注目されてきている」。