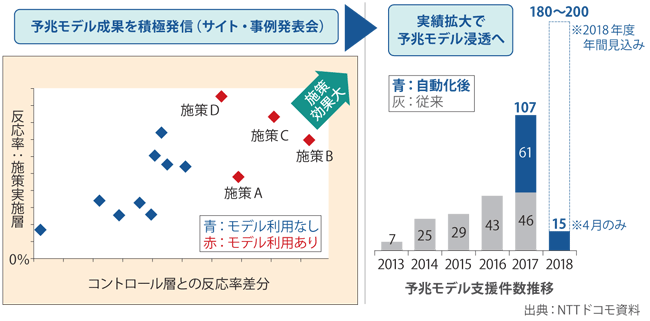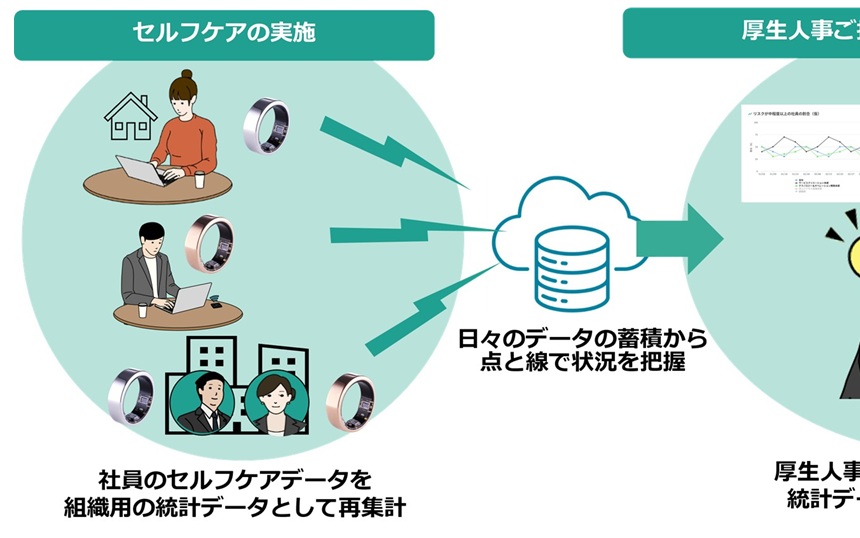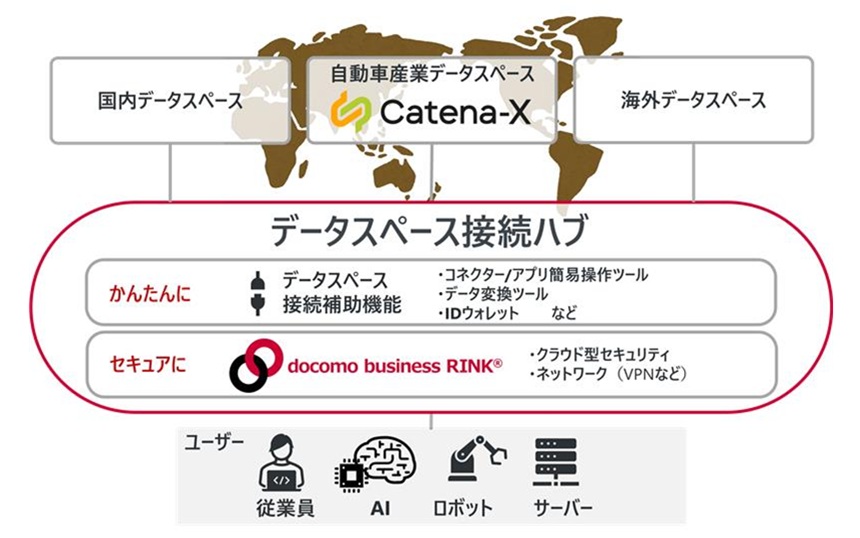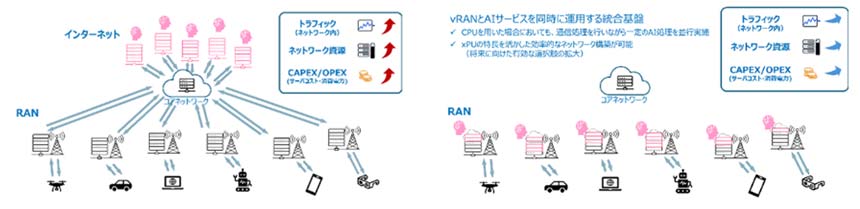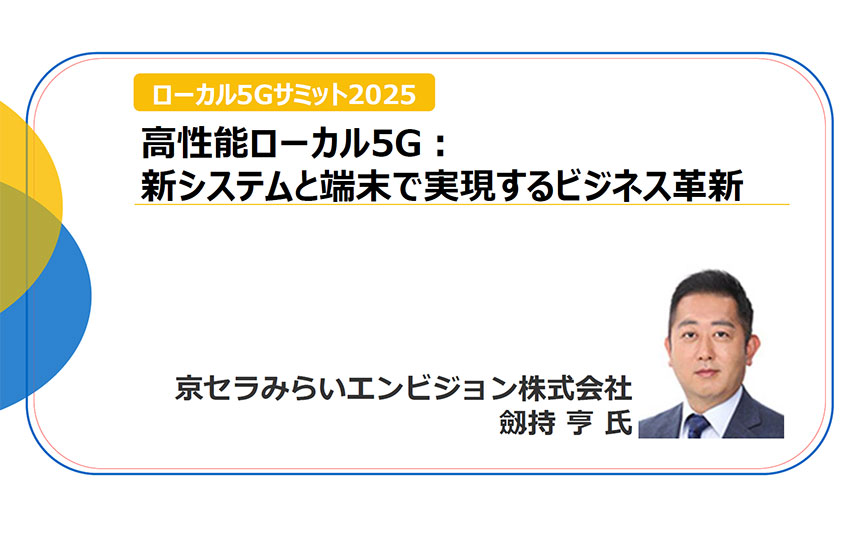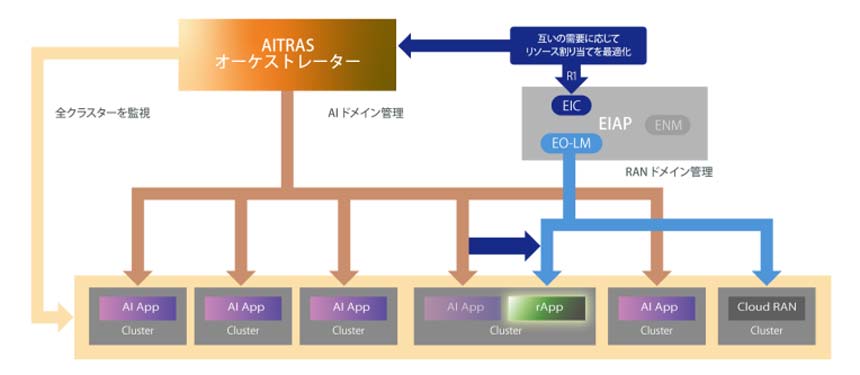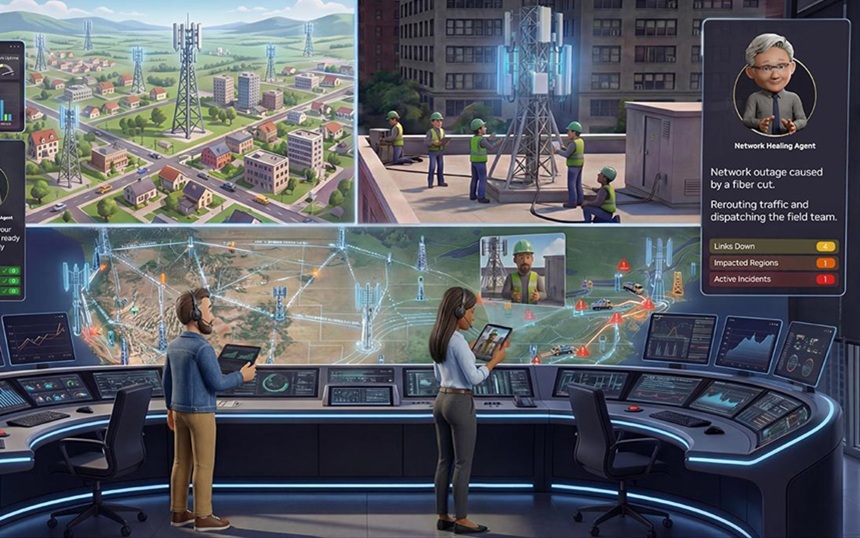携帯電話は年齢や居住地域などの顧客情報や各種コンテンツサービスの利用履歴など、まさに“データの宝庫”だ。しかも、通話料をはじめとする課金徴収が毎月発生する。登録後何年も経過した古い情報や虚偽の情報ではないため、通信事業者の元には、高鮮度かつ高精度なデータが大量に集まってくる。
意外と知られていないが、ドコモは携帯電話の黎明期から、これらのデータをマーケティングに活用してきた。
きっかけは解約予兆モデルドコモのデータ活用は、今から20年前の1998年に遡る。まだiモードサービスの開始前で、携帯電話が音声通話とメールしかできなかった時代だ。当時、ドコモ関西で「解約予兆モデル」による解約率の低減に取り組んだのが、執行役員で、この7月に新設されたデジタルマーケティング推進部の部長を務める白川貴久子氏だった。
予兆モデルとは、ロジスティック回帰分析を使い、過去の実績などを元に「~しそうな人」を抽出する手法だ。
解約予兆モデルであれば、解約につながるパラメーターを見つけ、スコアが高い(解約しそうな)人を見つけ出し、お得な提案を載せたダイレクトメール(DM)を送付する。解約予兆モデルを使わない場合と比べて、最大で解約率を3分の1に抑えるなどの成果が上がったという。
2009年に本社情報システム部情報戦略担当に着任した白川氏は、データ活用の効果をもっと社内に広めたいと考え、全国の支社に足を運び、データ分析の事例を披露する事例発表会を四半期に一度のペースで開催するなどの努力により、“データ分析仲間”を増やしてきた。
ただ、簡単に社内に受け入れられたわけではない。「解約予兆モデルに対しては、『ロジックがよくわからないから不安』『本当に有効なのか?』といった疑問の声も多かった」と白川氏は振り返る。
また、ドコモの施策を実施する各部門において、施策検証の方法が統一されていないといった課題もあった。
例えば、解約予兆モデルで「解約する可能性が高い」とされたグループが本当にそうであるかどうかを確かめるには、コントロールグループと呼ばれる集団を置き、解約可能性が高いグループの中でDMを送った場合と送らない場合の差を比較検証する必要がある。
しかし、営業担当者はより高い効果を期待するあまり、解約可能性の高いグループ全員にDMを送ってしまい、正しい効果検証が行えないなどの問題があった。
白川氏は「正しく効果検証を行える環境作りの必要性を痛感した」という。そこで適切な比較層を設定する検証サポート体制を構築するとともに、結果が自動的に反映される施策反応データベース(DB)を設置した。
施策反応DBには、DMに反応したかどうかといった施策結果がすべて蓄積される。これにより、契約者1人ひとりのプロファイルは「深化」する。施策登録の依頼者は、その結果を自席のPCから日々確認することが可能だ。また、DMの送付リストの抽出を担当する情報戦略部内の抽出チームが施策反応DBに登録するフローを組み込むことで、漏れなく登録が行われるよう工夫した。
この間、携帯電話がスマートフォンに移行し、ドコモが提供するサービスや料金プランが多様化したことで、ユーザーから上がってくるデータ量も初期の頃とは比較にならないほど膨大になった。
その一方、分析にはAIの機械学習をより積極的に用いるようになり、予測精度は格段に向上した。人間では処理しきれないような莫大なデータから、「動画サービスに関心が高く、dTVに加入しそうな人」「現在契約している固定回線をドコモ光に乗り換える可能性の高い人」など、様々な予兆をより高い精度で算出できるようになっている。
ただ、どんなに精度の高い予兆モデルを準備しても、そのターゲットに響く「施策内容」と「伝え方」がなければ、ユーザーには届かない。「精緻なターゲティングと響く見せ方の両輪が必要だ」と白川氏は強調する。
実績を重ねることで予兆モデルは社内で徐々に浸透し、依頼件数も2013年度の7件から、2017年度には107件と大幅に増加した。2018年度は4月時点ですでに15件の依頼があり、年間で200件を超えるのではないかと予想する。
図表1 予兆モデルの成果の発信が実績へ
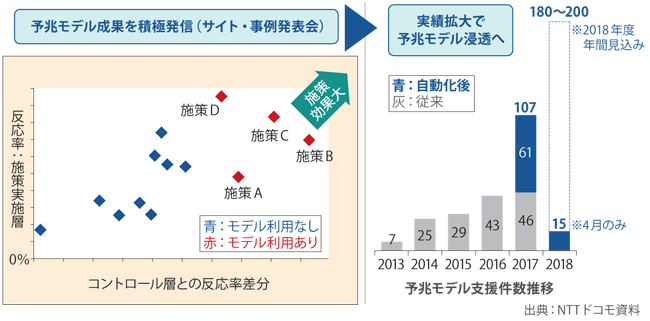
依頼件数の増加を受けて、2017年には予兆モデルを自動化した。これまで10年近くにわたる分析依頼で多くのビジネス課題が寄せられてきた。それらを基に、解約だけでなく販促やコンテンツ加入など様々なケースを想定し、約500の予兆モデルを用意することで、使いたいときにすぐ使えるようになった。
図表2 予兆モデル自動化で施策の高度化・高速化