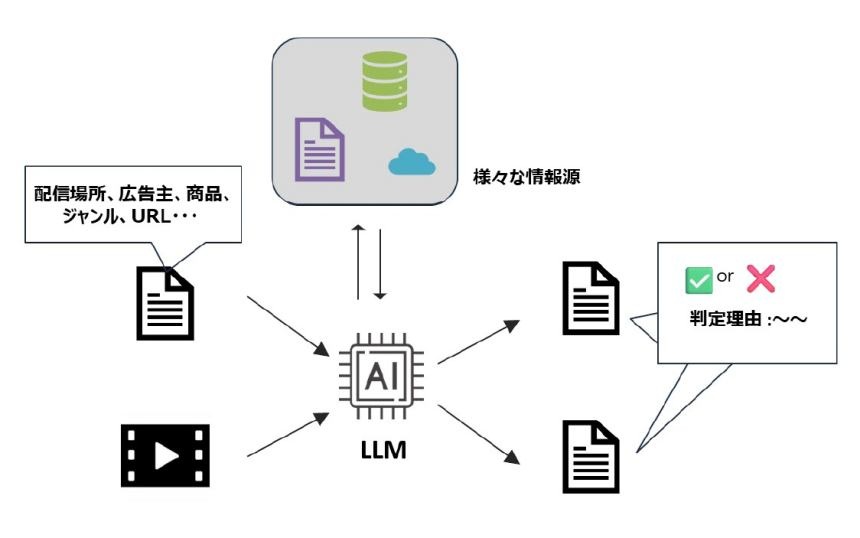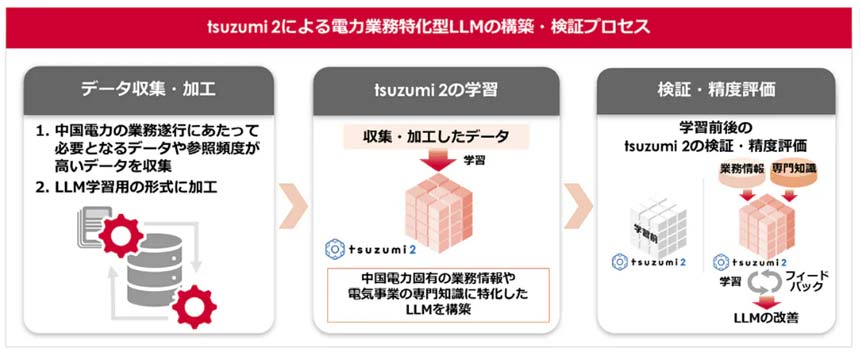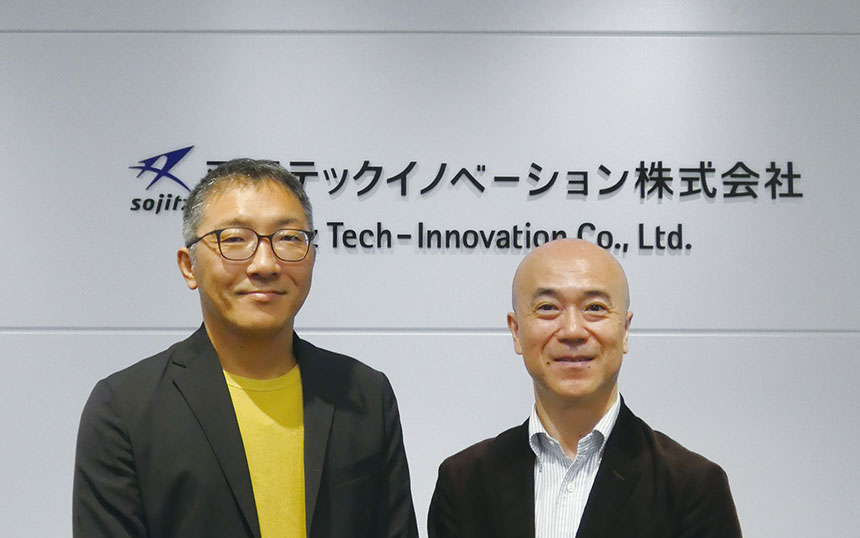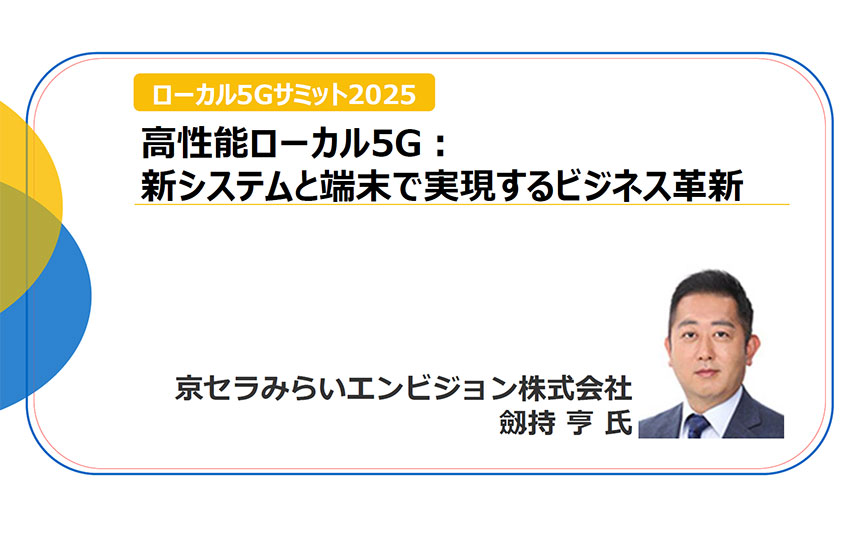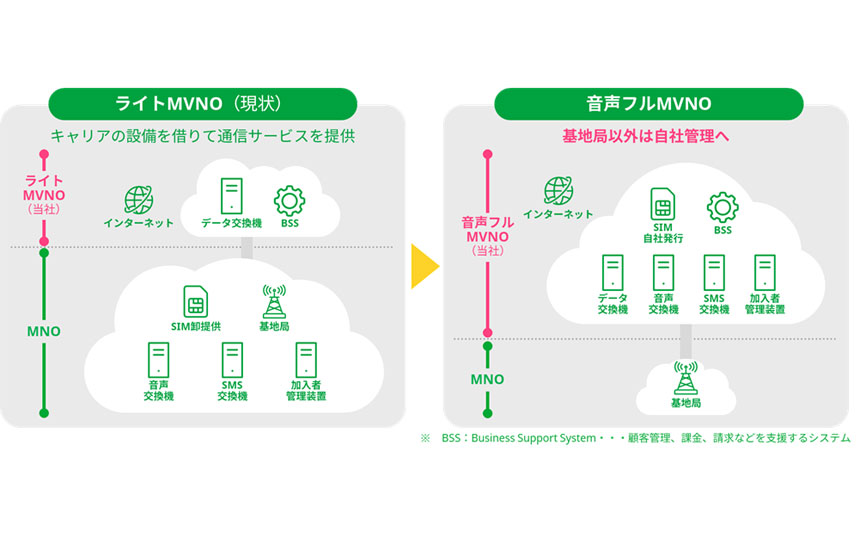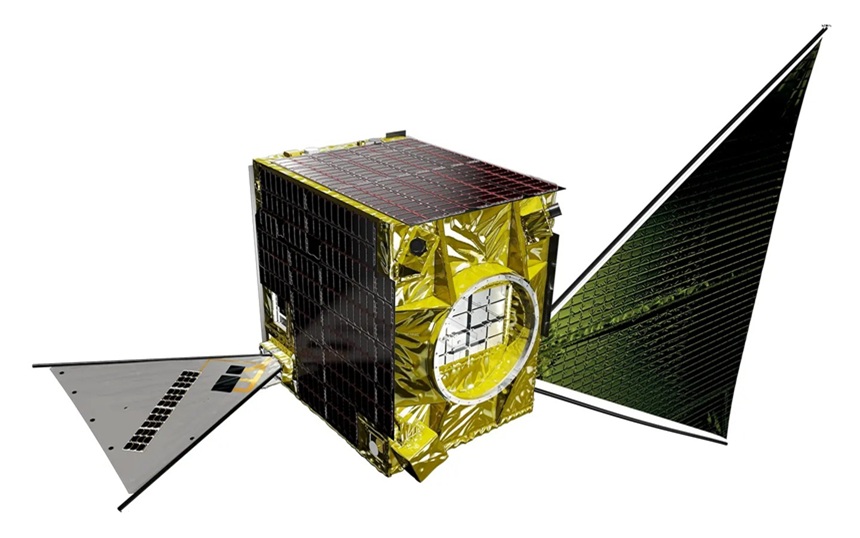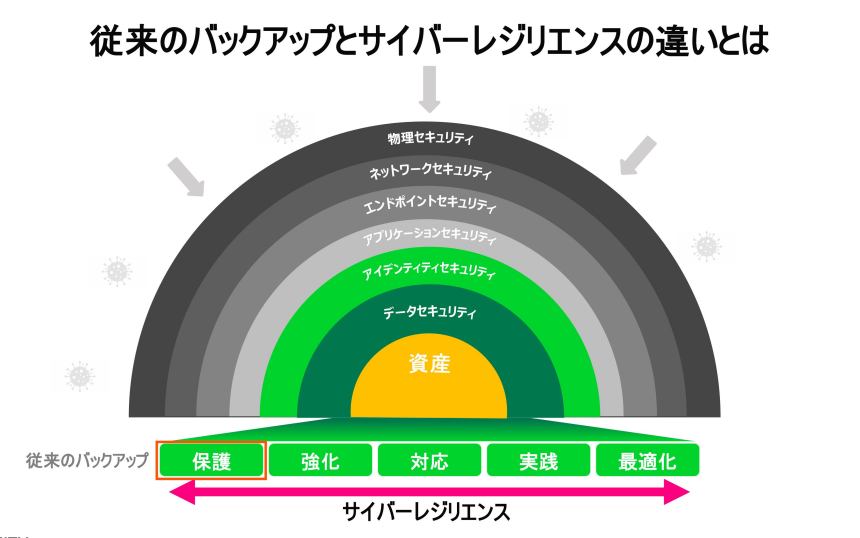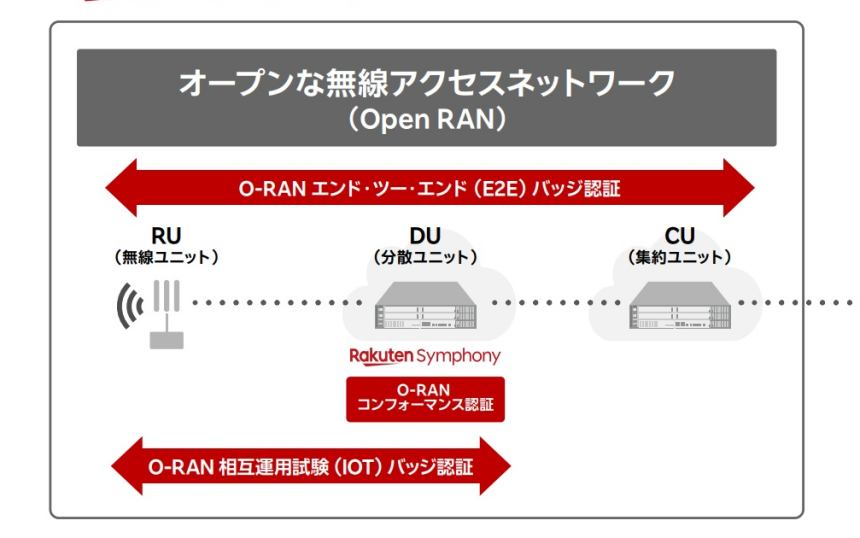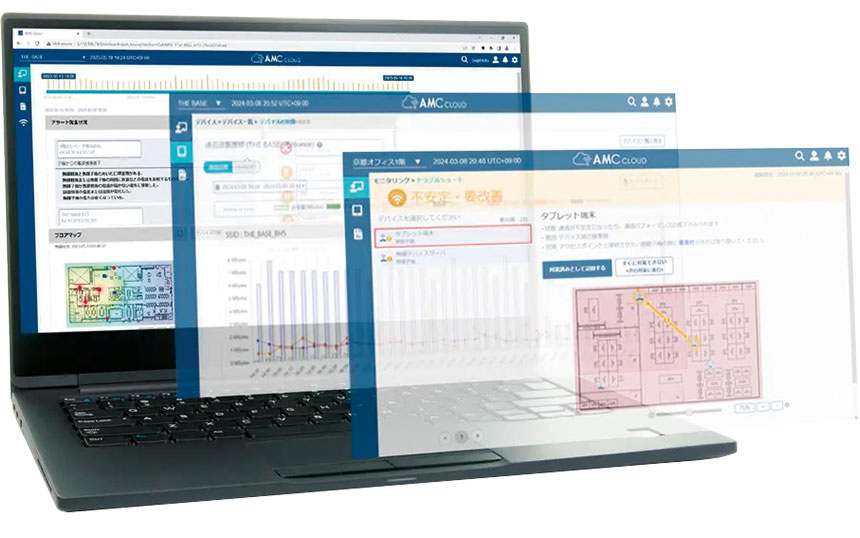世界中の企業・学術機関が開発にしのぎを削る量子技術。量子コンピューターや量子センサーなどの量子デバイスの開発が加速する一方で、それらをつなぐ新たなネットワーク基盤を実現しようとする取り組みも進んでいる。量子インターネットだ。
世界中のコンピューター/デバイスがインターネットに接続されているように、量子デバイス同士が情報交換を行うには、量子状態を保ったままやり取りできる通信基盤が必要だ。量子力学の原理に基づいて構築されるこのネットワークを、地球規模に広げたものが量子インターネットである。
量子インターネットは、量子デバイスと量子通信路で構成される。NTT物性科学基礎研究所(NTT物性研)理論量子情報研究センタ プロジェクトマネージャの東浩司氏によれば、「ノードもエッジもすべてが量子でできている純粋な量子通信ネットワークのこと」。量子性を運ぶ通信路には光ファイバーのほか、自由空間を無線接続する形態も検討されている。

NTT物性科学基礎研究所 理論量子情報研究センタ プロジェクトマネージャ 東浩司氏
量子インターネットの使い道
量子インターネットができると何が可能になるのか。活用範囲は広い。
1つが、無条件に安全な暗号通信だ。光子に鍵情報を載せて送信する量子鍵配送(QKD)として一部実用化されている。観測されると状態が変化する、原理的に複製ができないという光子の性質を利用して盗聴を検知する。盗聴・解読が絶対に不可能な暗号通信が可能になる。
電子的な通貨に量子情報を埋め込むと、原理的に複製できない「量子マネー」ができる。偽造が不可能な通過で、安全な商取引の基盤となる。
量子状態を転送する量子テレポーテーションは、量子デバイス間の情報交換を実現する。離れた場所にある原子時計を量子通信で結び量子情報を共有すれば、現在の仕組みよりはるかに高精度な超精密時刻同期も可能になる。
天文学の発展にも貢献する可能性がある。離れた望遠鏡で受信した光を1カ所に集約して像を得る超長基線望遠鏡において、量子インターネットによる超精密時刻同期を使えば、より離れた望遠鏡を使う長距離化が可能になる。
量子コンピューター実用化に向けては「クラウド量子計算」も重要なユースケースとなる。現在のPCのように量子計算機が持ち運べるサイズになるには長い年月がかかり、当面は「量子計算機をクラウド利用するのが自然だろう。その際、量子計算機の所有者に計算の中身を見られたくない。盗聴不可能な量子通信なら、そうしたクラウド利用が可能になる」(東氏)。
「分散量子計算」への期待も大きい。小規模の量子コンピューターを接続して、より大規模な量子計算機として活用する手法だ。現在の古典コンピューターでも計算タスクを複数の計算機に分散させる手法が採られるが、量子インターネットがあれば、量子計算の世界でもそれが可能になる。