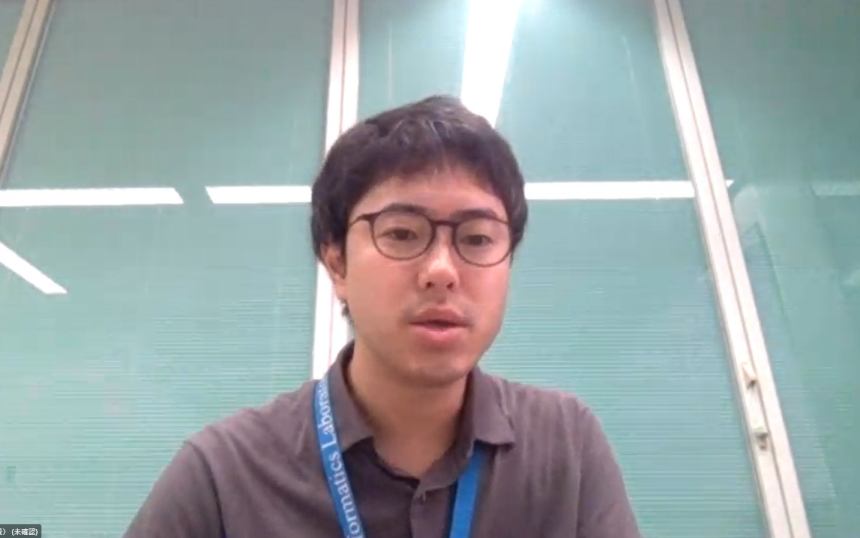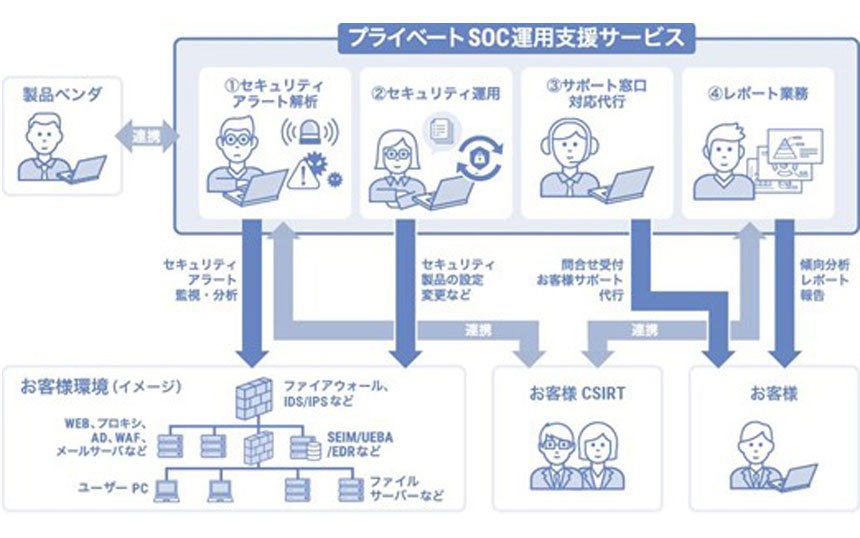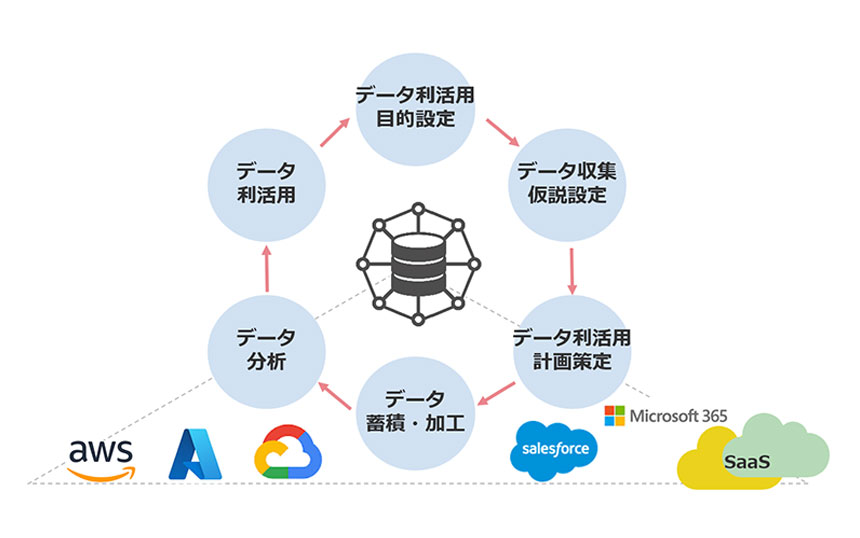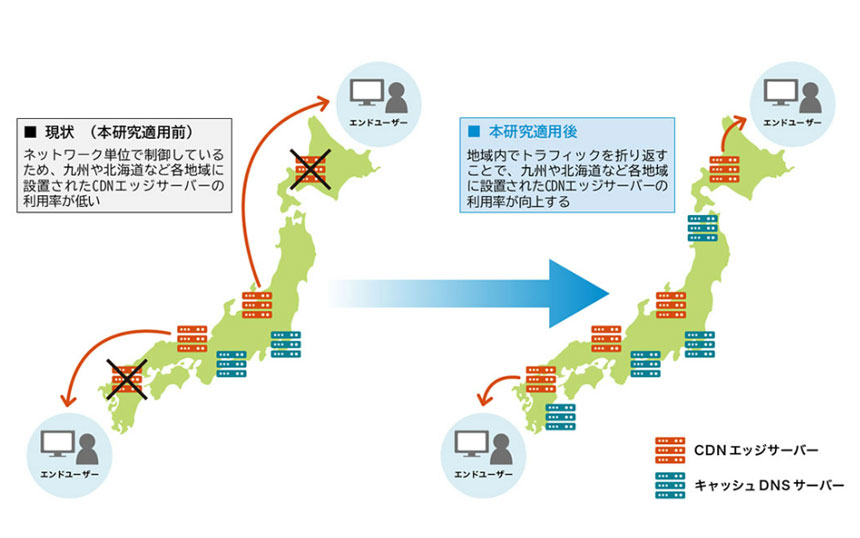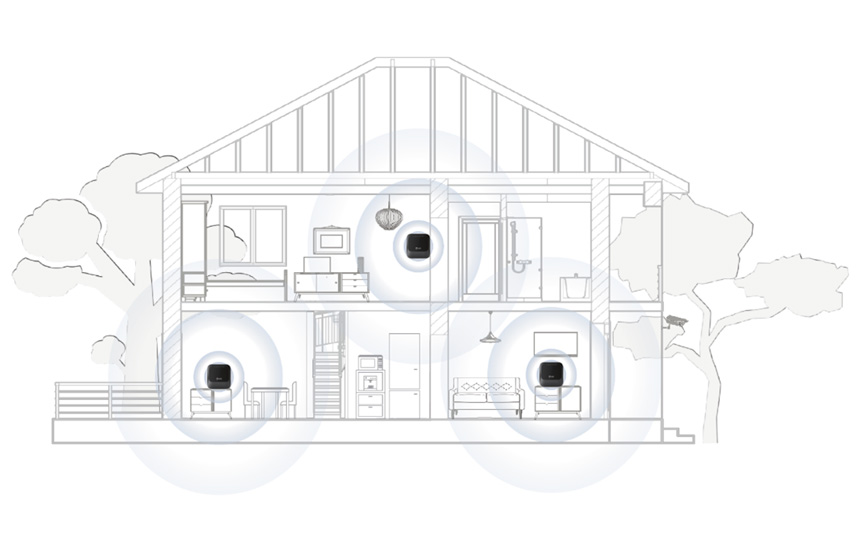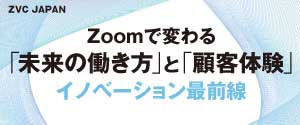6Gは当初からSA方式で
5Gから6Gへの移行も、パネルディスカッションの大事なテーマとなった。
中村氏は5Gの展開が世界的に遅れたことを踏まえて、「5G導入時に直面した社会的・技術的な課題から得た教訓は、6G展開にどう活かされると考えるか。5Gから6Gへの移行プロセスでは、どのような移行戦略が現実的か」と質問。
クアルコムの北添氏は4Gから5Gへの移行における戦略的な間違いとして、「ENDC(E-UTRAN NewRadio Dual Connectivity、いわゆるNSA方式の一形態)を最初にとったことがある。つまり、5Gがモバイルブロードバンドの延長であることを自ら認めてしまう結果となった」としたうえで、6Gのコアネットワークで実現される多くのサービスを提供できるアーキテクチャでスタートするマイグレーション方法のほうが望ましいとの見方を示した。
中華電信のリュウ氏は、「5Gから6Gへの移行は、新しい装置を購入する必要のないアップグレードになる可能性がある。ソフトウェア更新が可能になれば、TCOを最適化できる」とした。さらに現状のOpen RANについて「私の見解では“真のOpen RAN”とは言えない」としたうえで、6Gで真のOpen RANが実現できるかも「TCOの最適化の観点から重要だ」と話した。
キーサイトのラゴサマン氏は、6G標準化では必須機能を重視し、オプション機能は減らし、「初期導入段階(Day1)から機能する完全な標準規格を策定することが、6Gの成功のために大変重要だ」と述べた。
ノキアのレダーナ氏も6Gでは当初からSA型のアーキテクチャを採用すべきと主張。さらに、「6Gで朗報なのは、新しいコアネットワークが必ずしも必要ないことだ。5Gのコアはすでにクラウドネイティブなため、6Gの新機能は既存のクラウド基盤に組み込むことができる」と解説した。
XGMF 6G推進プロジェクト サブリーダーの城田雅一氏(クアルコム)もコメンテーターとして、「6Gでは5Gで取り組みが始まったバーティカル(特定の業界・分野向け)サービス・ソリューションの開拓が重要になる」と発言。XGMFは6Gに向けて、バーティカルにさらに力を入れていくとした。

XGMF 6G推進プロジェクト サブリーダー/クアルコムジャパン 標準化本部長 城田雅一氏
6Gは、システム・ユースケースともに5Gから連続的に進化することになりそうだ。