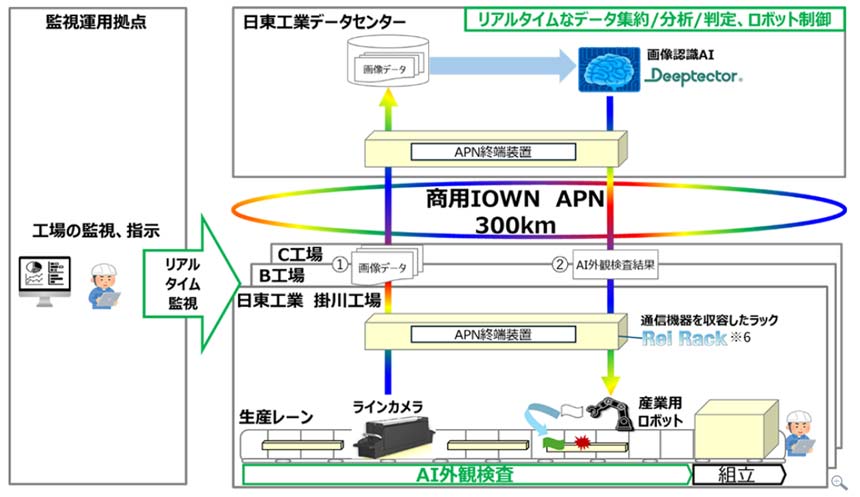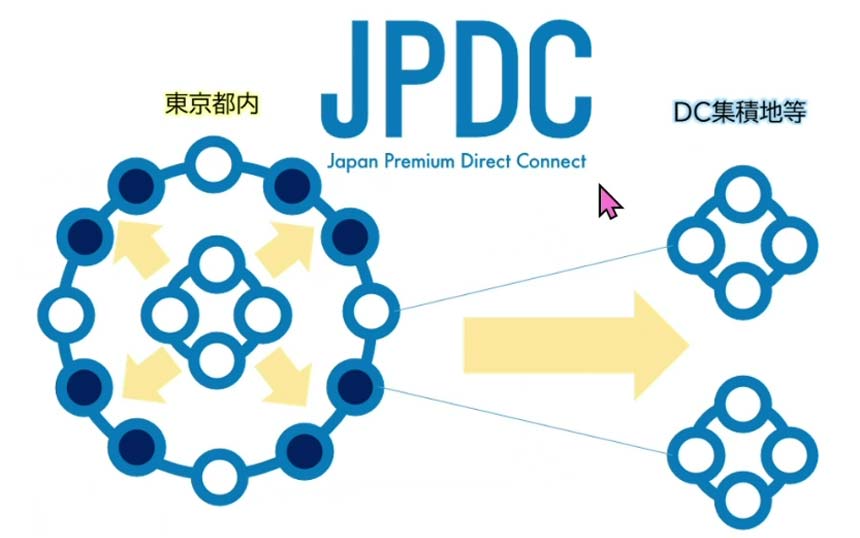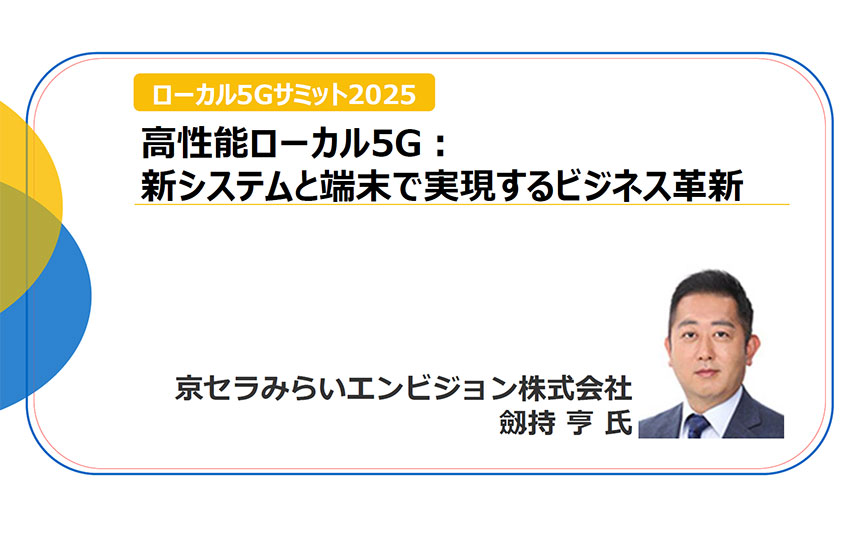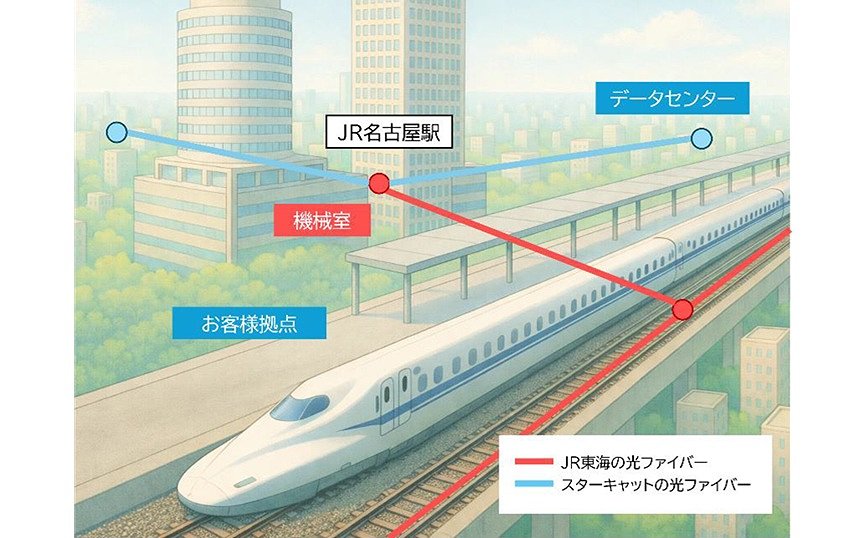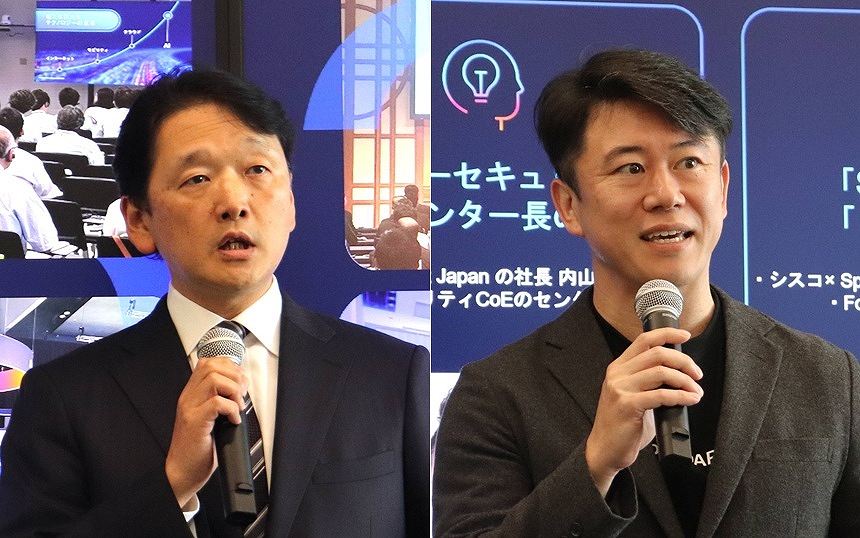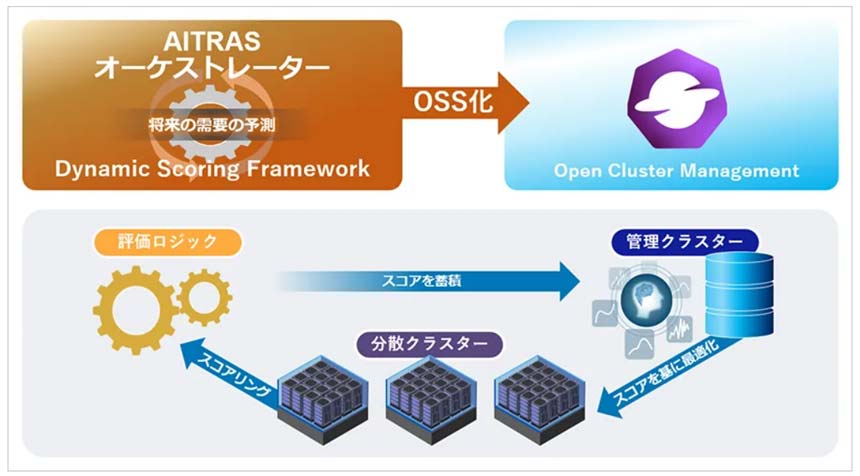情報通信システムはサーバー、ストレージ、スイッチ/ルーター等の装置をつなぎ合わせて構成されている。性能も機能も常に“箱”単位で評価され、技術が進化するたびに箱を入れ替え、つなぎ替えてICT基盤を発展させてきた。
この常識を変えたのが「ディスアグリゲーション」という新たな潮流だ。箱を形作るハードウェアとソフトウェアを分離し、組み換え可能な「ホワイトボックス」型ハードウェアが登場。仮想化技術の進展も手伝い、今ではネットワークの世界でホワイトボックススイッチの活用が進んでおり、サーバー内で仮想スイッチ/ルーターが稼働している。
NTTの次世代基盤構想「IOWN」は、この概念をさらに発展させた「ディスアグリゲーテッドコンピューティング」の実現を目指している。コンピューター内の物理・論理構成も分解。これを再構成し、新たな制御方式を確立する。これにより、サーバー内に閉じていたCPUやメモリ等のリソースを解放し、ラック単位やデータセンター単位で1つのコンピューターとして扱えるようにする──。このパラダイムシフトによって、処理性能や電力効率を圧倒的なレベルに引き上げるのが狙いだ。
IOWNのキー技術「光電融合」これを実現するためのコア技術が「光電融合」である。難しそうに思えるが、考え方は至ってシンプル。IOWN Global Forum(IOWN GF)のテクノロジーWGチェアを務める川島正久氏は「電気の配線区間を極力短くするためのもの」と説明する。
コンピューターとネットワークは電気と光でつながっている。ネットワークについては、電気信号への変換なしにエンドツーエンドに光で接続する「オールフォトニクス・ネットワーク」の実現を目指しているが、コンピューターの内部回路も、できるだけ電気を使わず光でつなぐことを目指す。理由は、電気は遅く、エネルギーを使いすぎるからだ。
“どうつなぐか”という観点で言えば、サーバーもネットワーク機器も構造は同じだ。「光のI/Oは箱の表面までで、内部はすべて電気回路。そこに数Gbpsのデータを通そうとすると、例えば“PCIeバスを16レーン”とか、パラレルに通信しないといけなくなる」(川島氏)。
ここに多大な無駄がある。箱内に入ってきたデータをパラレルに変換し、送り先で1つのデータに戻す。CPUやメモリ、GPUやSmart NIC等のアクセラレーターカードの性能は急速に向上しているが、現状はその間のデータ伝送が足枷になっている。
箱の中まで光でつながれば、この無駄は消え去る。
CPUやメモリ等に光のI/Oを直付けし、「光のインターコネクト」で高効率伝送ができれば性能向上、遅延削減、エネルギー効率の改善と、様々な効果が期待できる。光で各リソースをつなぐ大容量かつ低遅延なデータプレーンを備え、かつ、リソースの入れ替え、つなぎ替えも容易なこの新しい箱を川島氏は「スーパーホワイトボックス(SWB)」と呼んでいる。
SWBが実現できれば、隣の箱と光を介してリソースを共有することも可能になる。これまでのようにサーバー単位ではなく、ラック内やデータセンター内という大きなスケールで使われていないリソースをかき集め、超強力なコンピューティング処理をすることも夢ではない。
コンピューティングの形態も様変わりし、電力の制御やハードウェアの管理方法も大きく変わる可能性がある。
現在のような箱は最早不要で、CPUやメモリ、ストレージ、アクセラレーター等のリソースごとにモジュール化し、それを光のファブリックで接続して使う、圧倒的に拡張性の高いコンピューティング環境が実現できる。これまではサーバー単位で電力制御やハードウェアの追加を行っていたのに比べて、より細かなリソース単位で電力制御やハードウェアの追加が可能になるのだ。これが、ディスアグリゲーテッドコンピューティングの最終目標である。