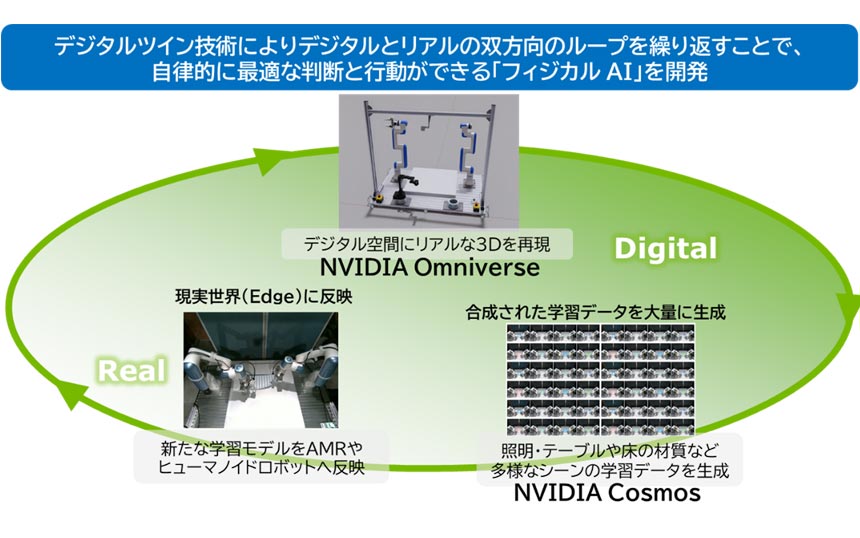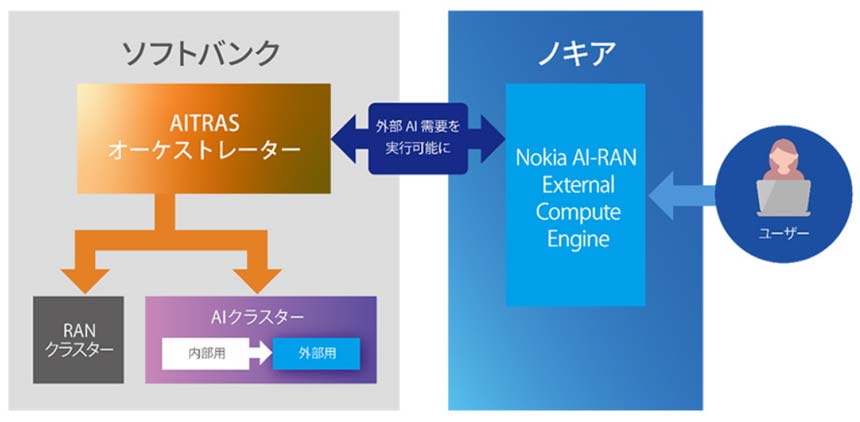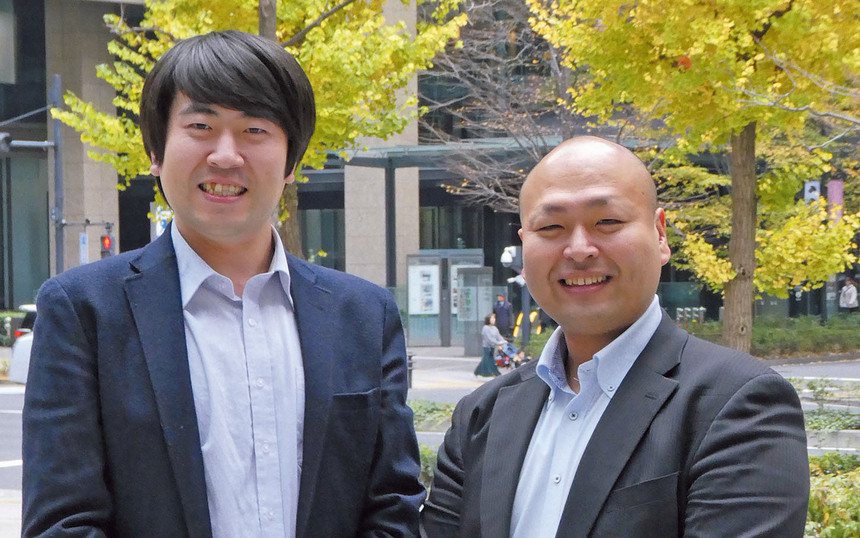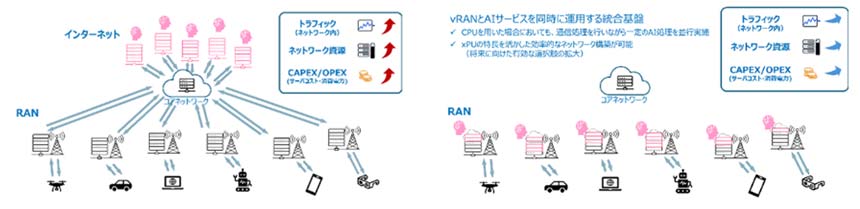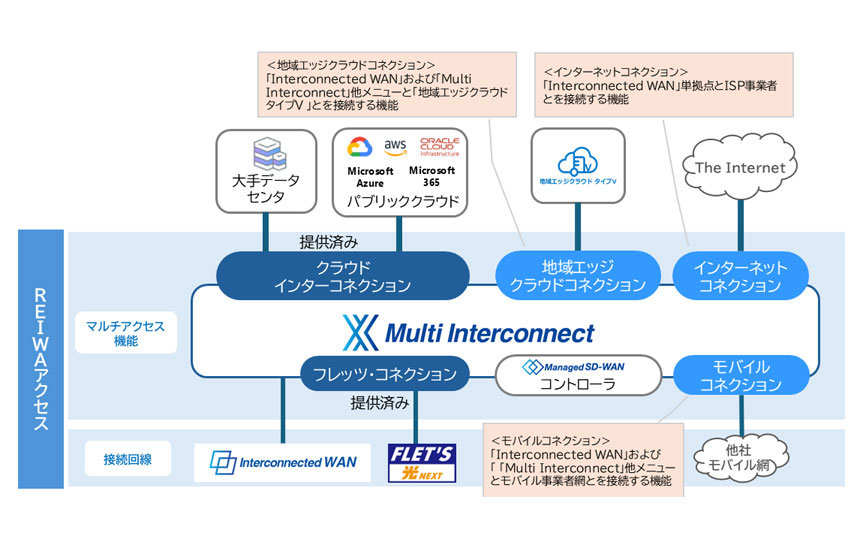6Gはどんな無線通信システムになるのか。
3GPP標準化が始まる前の現時点で確実に言えることは、6Gが“5Gの方向性を受け継ぎ、拡張する”ものになることだ。その方向性とは、異業種にモバイルネットワークをもっと深く浸透させること。モバイル業界が「バーティカル」というキーワードを掲げて5Gで始めたこの挑戦の実現を、20年越しで目指すのが6Gということになる。
とすれば、6Gの在り様を決める標準化で重要になるのが、ネガティブな評価も少なくない5Gの問題点を認識し、その教訓を活かすことだ。
図表1 3GPPにおける6G標準化のタイムライン
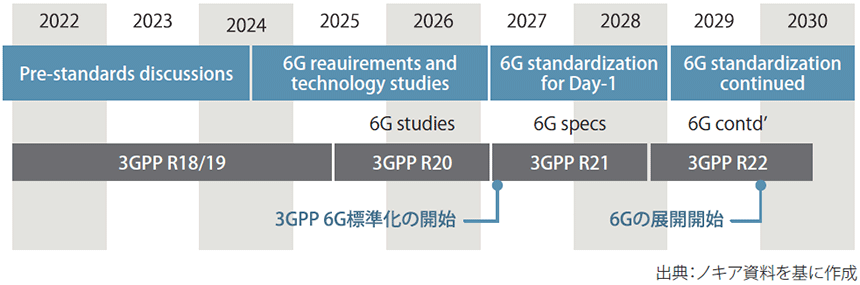
NSAは失敗、6GはSAで始める
中でも問題視されているのが、5Gのマネタイズだ。
インフラ投資が嵩む一方で、新たな収益源と目されていた産業分野の開拓が進まず、通信事業の収益性は年々悪化している。特に苦境に陥っているのが、欧州の通信事業者だ。日本では通信事業者の“脱・通信”が概ね成功しているため目立たないが、それでも、このギャップは改善しなければならない。
6Gで同じ轍を踏まないために鍵となるのが、TCOの削減だ。5Gから6Gへの移行コストを抑え、かつ6Gをシンプルに構築・運用するための方策が検討されている。AIの活用によるOPEX低減への期待も高い。
最優先事項は、5Gから6Gへの移行をスムーズかつコスト効率のよい形で実現することだ。ベンダー各社は、4Gから5Gへの移行時とは異なるシンプルな形態を提案している。
クアルコムジャパン 標準化本部長の城田雅一氏は、5G導入に当たって大多数の通信事業者が採用した「NSA(Non standalone)は失敗だった」と話す。同社は6Gへの移行についてSA(Standalone)、最初から6Gコアと6G RAN(無線アクセス網)を展開する方式を提言している。
エリクソンも同意見だ。「NSAは避けたい」と技術部門 アジア太平洋地域 先端技術担当ディレクターのクリストファー・プライス氏。「4Gと5Gではコアが大きく異なっていたが、6Gはそうではなく、5Gの進化版であるべき」とし、5Gコアから6Gコアへスムーズに移行できるアーキテクチャを実現したいと話す。
大きかった「早期展開」の代償
5Gの標準仕様では、既存の4Gネットワークを使ってカバレッジを確保しながら5G RANを展開する5G NSAと、5Gコアと5G RANのみで構成する5G SAが規定された。
多くの事業者がNSAを採用したことで5Gの展開が早まったものの、5G本来の機能を実装するSAの展開が遅れたり、国・事業者ごとでばらつきや混乱が起きたりした。プライス氏は、「単純な指標では5Gは成功している。(4G以前と比べて)急速に採用されたが、欠如している要素がある。企業や産業向けの収益化だ」と指摘する。5Gコアの導入前には、5Gならではの技術を用いて、ユーザーの要求にあった性能を持つネットワークスライスを提供したり、アプリケーションごとに特化した通信サービスを提供することはできない。
シンガポールや米国など5G SA先進国においては、ようやくこの動きが具体化してきているが、日本をはじめ多くの国・地域では5Gの用途開拓と、ソリューションパートナーらとのエコシステム確立が遅れた。5Gへの幻滅も招いたという意味で、これは痛恨だったと言えよう。