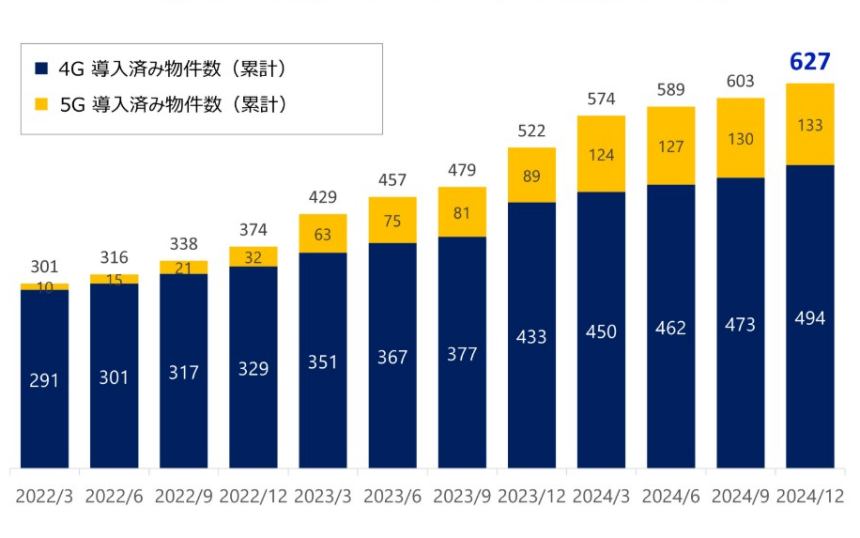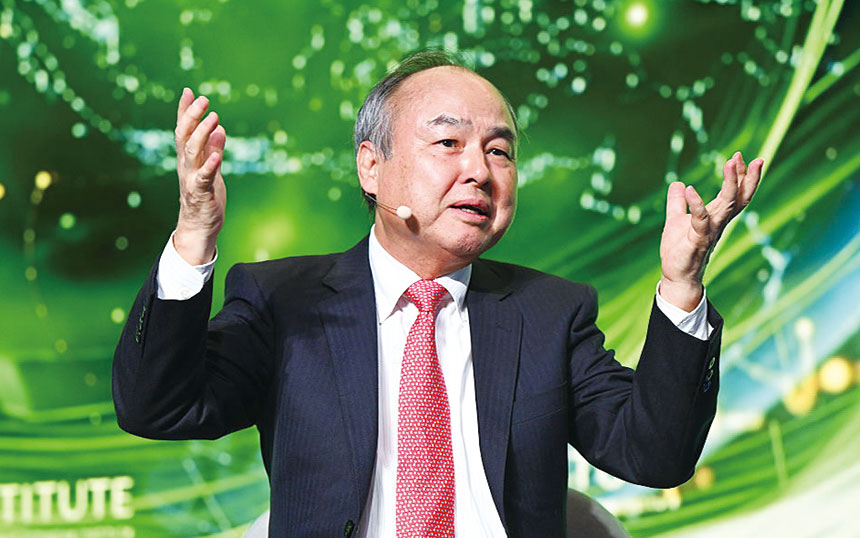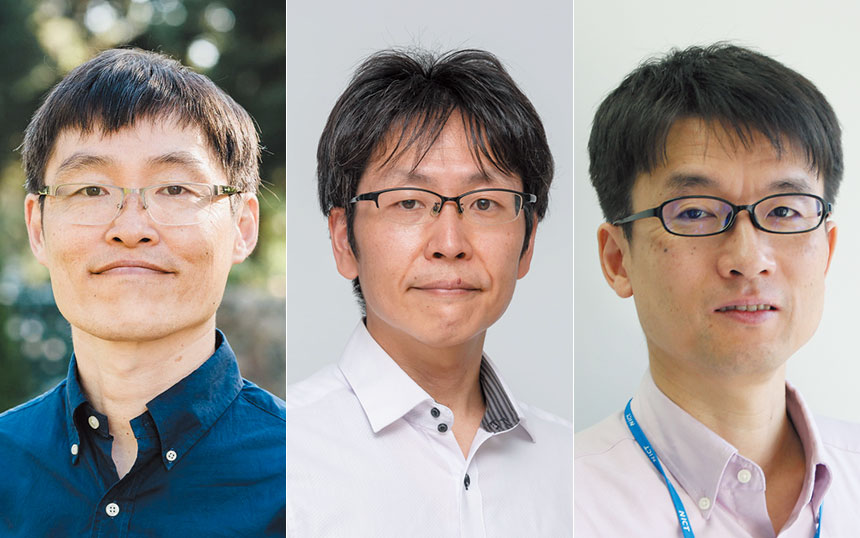JTOWER 代表取締役社長 田中敦史氏
――米国の投資会社であるDigitalBridgeによるTOBが2024年10月に成立しました。傘下入りの目的は何ですか。
田中 一番は、設備、技術開発、人材など今後も多額の投資を行っていきたいからです。上場維持と比較検討し、非公開化した方がタイムリーな資金調達が可能と判断して今回決めました。
株価の水準が非常に高ければ、上場を維持したままでも多くの資金調達ができます。しかし2024年2月に公募増資で170億円を調達して以降、市場から今後も増資が行われて株主価値が希薄化するのではないかと懸念されたこともあり、株価はずるずると下がっていました。また、日本の金利は上昇局面に入りましたが、東証グロース市場に上場するJTOWERのような成長株にとっては、金利上昇はどちらかというと株価の重しとなります。
業績は伸びており、成長の機会も見えています。必要なのは機動的に資金調達できる体制でした。1~2年後の株式市場の環境は分からず、非公開化は相手がいないとできないことから、今回のタイミングで非公開化するのが望ましいと考えました。
――DigitalBridgeの側からアプローチがあったのですか。
田中 先方からです。
実はDigitalBridge以外にも複数社から資本参加の提案が寄せられていました。そこで、そもそも提案を受け入れるかどうか、受ける場合はどこと組むのが最も望ましいのか、取締役会だけではなく、社外役員等で構成される特別委員会も設置して慎重に検討してきました。
――DigitalBridgeはどういう会社で、なぜパートナーとして選ばれたのでしょうか。
田中 DigitalBridgeはデジタルインフラに特化したファンドであり、業界を問わず投資する一般的なプライベートエクイティファンドとは異なります。北米、南米、欧州、東南アジアでタワー事業やデータセンター事業などに長期的な視点に立って投資しており、1991年の設立以来、20年以上の経験を持つエキスパートです。その運用資産は880億米ドルに上ります。
大きな決め手の1つとなったのは、DigitalBridgeがTOB後も経営陣を基本的に維持し、引き続き経営にあたる方針を示していたことでした。さらに、彼らは日本市場について徹底的に研究しており、その見方が当社と一致していたことも重要でした。
DigitalBridge傘下のタワー会社である米Vertical Bridge社はベライゾンからタワーを取得していたり、ドイツとオーストリアではGD Towersというタワー会社をドイツテレコムと共同運営したりしているのですが、インフラシェアリングにおいて通信事業者との協調を大切にするという哲学も当社と共通しています。
経済安保も“問題なし”
――JTOWERが外資企業の傘下に入ったことに対して、経済安全保障上のリスクを懸念する声もあります。
田中 心配はまったくありません。もちろん、通信の分野に限らず経済安全保障が各国で重要なテーマになっていることは認識していますが、DigitalBridgeには世界各国でタワー事業を長年行い、それぞれの国の規制や市場環境に適切に対応してきた実績があります。また、ニューヨーク証券取引所に上場している公開企業であり、経営の透明性も確保されています。
経営体制に問題のある企業と提携することはありませんし、仮にリスクがある場合、そもそも外為法に基づく厳格な審査をクリアすることはできません。こうした点を踏まえても、経済安全保障上の懸念は杞憂であり、問題はないと考えています。
――資本業務提携を結んでいたNTTグループ、KDDI、楽天モバイルは、JTOWERの顧客であると同時に株主でした。これらのMNOからは、TOBについてどんな反応がありましたか。
田中 TOB発表当日、NTTとは業務提携の維持を両社で発表しましたし、KDDIとの業務提携も継続しています。他の通信事業者や総務省にも事情を説明して、「引き続きしっかり頼むよ」という声をいただいていますので、その期待に応えていきます。
通信事業者のなかには、外資の傘下に入ることにより一方的に契約条件を変更されるのではと不安を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、通信事業者とはタワー事業でも屋内インフラシェアリング(IBS)事業でも長期の契約を結んでおり、当社で一方的に変更できるような建て付けにはなっていません。通信事業者にメリットを感じてもらうことが第一ですし、よりよい条件で利用してもらいたいと思っています。