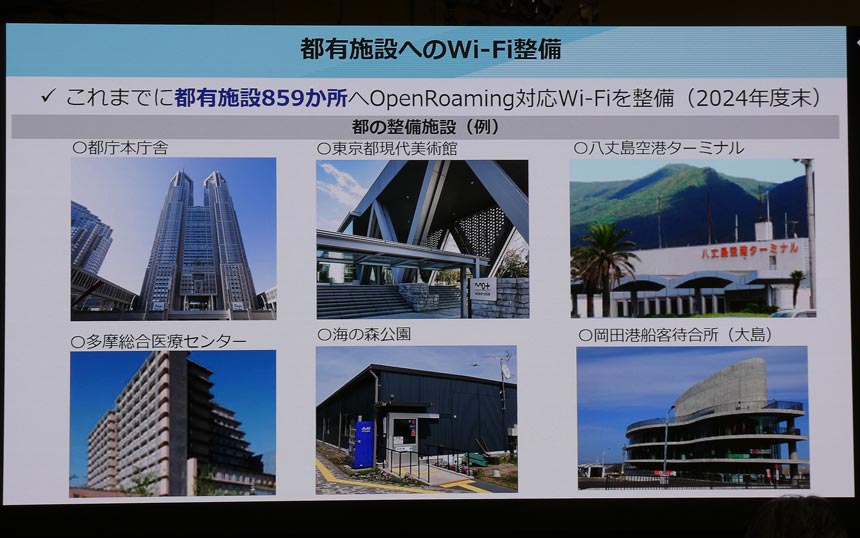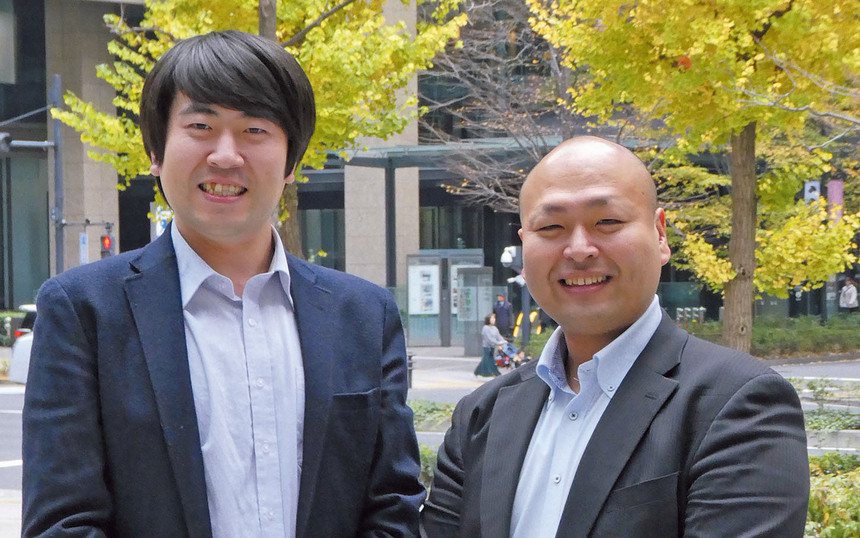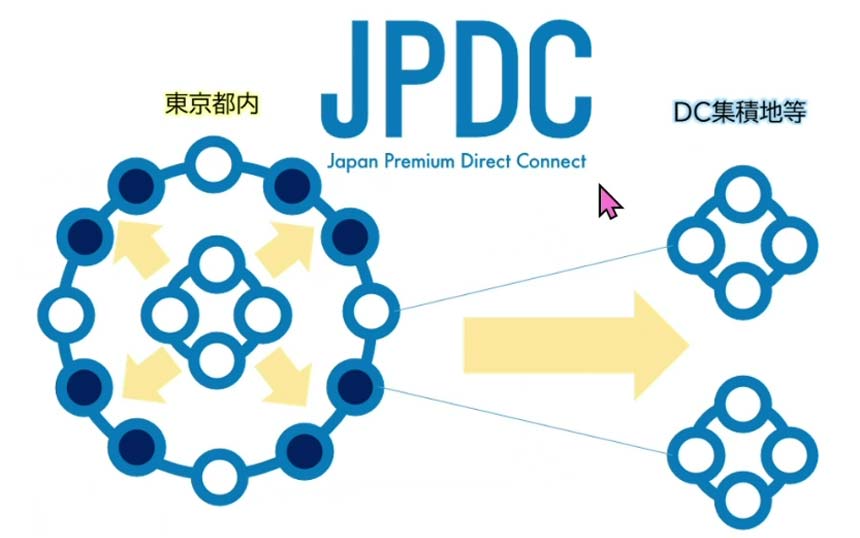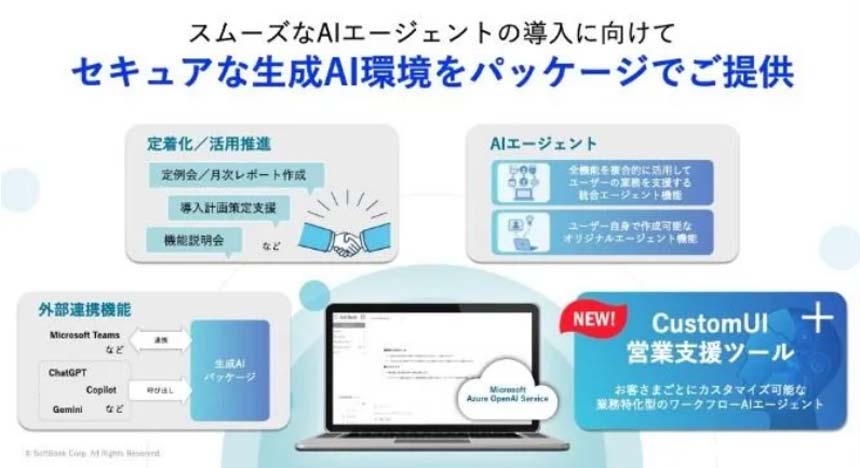2022年の9月にWi-Fi利用が解禁されたばかりの6GHz帯は現状、非常に良好な電波状態で使える。APもエンド端末もありふれていて、Wi-Fi以外でも使われている2.4GHz帯や5GHz帯とは異なり、期待通りの性能を引き出しやすい“計算の立つ”周波数だ。
無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz) 代表理事(会長)の北條博史氏は、「変な電波が入ってくる余地は、今のところない。6GHzを使う端末をきちんとコントロールできるエリアなら、一定の遅延で送信することができる」と話す。加えて、ベンダーが独自に実装するセキュリティ機能等によって接続の安全性も担保できるとなれば「ローカル5Gの代わりとして使うこともできる」と見通しを述べる。
こうした期待は、ベンダー側にも共通している。「5Gやローカル5Gで無線化できるとされていたユースケースのかなりの部分は、正直、Wi-Fi 7でも可能になってきている」と語るのは、シスコの高橋氏だ。事実、産業IoTやXR、高精細映像伝送など、ローカル5GとWi-Fi 7の想定ユースケースには大きな違いはない。
ただし、他の無線通信システムもそうであるように、Wi-Fi 7があればローカル5Gは無用といった排他的な関係ではない。Wi-Fiがここまで進化し、両者の差が縮まった今こそ、適材適所な使い分けが求められる。

(左から)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz) 代表理事(会長)の北條博史氏、シスコシステムズ 執行役員 ネットワーキング事業担当の高橋敦氏、日本ヒューレット・パッカード Aruba事業統括本部 技術統括本部 テクノロジーコンサルティング部 部長の下野慶太氏
最大の違いは「カバレッジ」
伝送容量や遅延、信頼性といった性能の差が縮まったなかでも、両者には決定的な違いがある。ローカル5Gが免許周波数帯で、Wi-Fiがアンライセンスバンドであることだ。他のユーザーが決して入り込まない「クリーンな電波を使いたいというニーズはなくならない」(高橋氏)。
HPE Arubaの下野氏は「カバレッジの広さが最大の違いだ」と指摘する。周波数帯と送信出力、基地局性能の違いなどから、ローカル5Gは少ない基地局数で圧倒的に広いエリアをカバーできる。同じ広さをWi- Fiで無線エリア化しようとすれば、多数のAPを設置するために電源とLANケーブルの敷設が必要だ。「工場や石油コンビナートのような広い施設、屋外の農場等をカバーするには、ローカル5Gのほうが向いている」
対して、Wi-Fi APが敷設しやすい場所ならWi-Fi 6E/7は低コストでパフォーマンスが出しやすいうえ、端末の調達も容易だ。
このように、設置環境や用途によってどちらが最適かを見極める必要があるが、ローカル5Gを導入・利用する場合でも、その企業・組織がWi-Fiをまったく使わないという選択は難しいだろう。あらゆるPC/スマホに普及したWi-Fiを使わないのは非効率だし、ローカル5Gの性能を担保するためにもWi-Fiへのオフロードは不可欠だ。
そこで欠かせないのが、運用・認証基盤の共通化である。シスコもHPE Arubaも、Wi-Fiとローカル5Gの両方のソリューションを提供しているが、「お客様がいつも悩むのが、ローカル5GとWi- Fiのポリシーが異なると、コントロールできなくなること」(高橋氏)だという。無線品質や端末の監視、アクセス制御などの仕組みを統合しておくことは欠かせない。
今後、こうしたニーズが拡大することを見据え、シスコはCisco Private 5GとWi-Fiの認証基盤や管理システムを統合。HPE Arubaも、LANスイッチやWi-Fi APなどを一元管理できるクラウド型管理ツールのAruba Centralにローカル5Gの運用管理・認証基盤を統合していく計画だ。