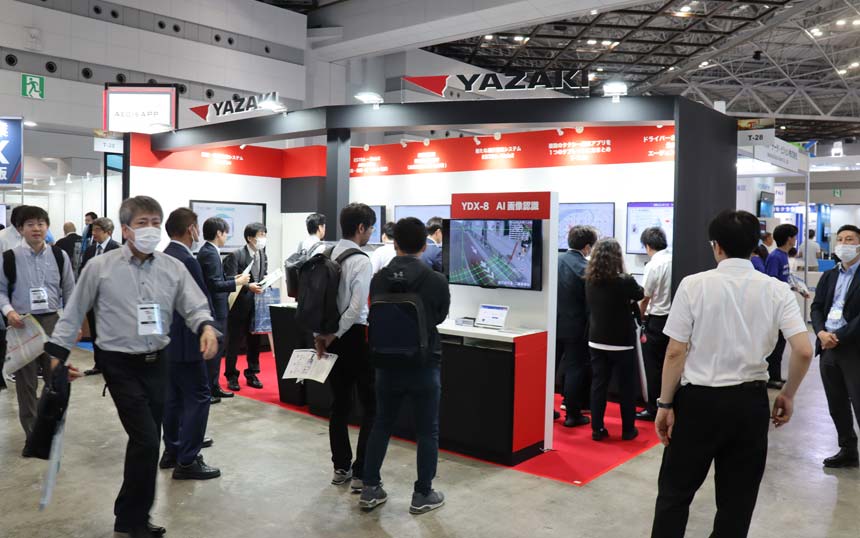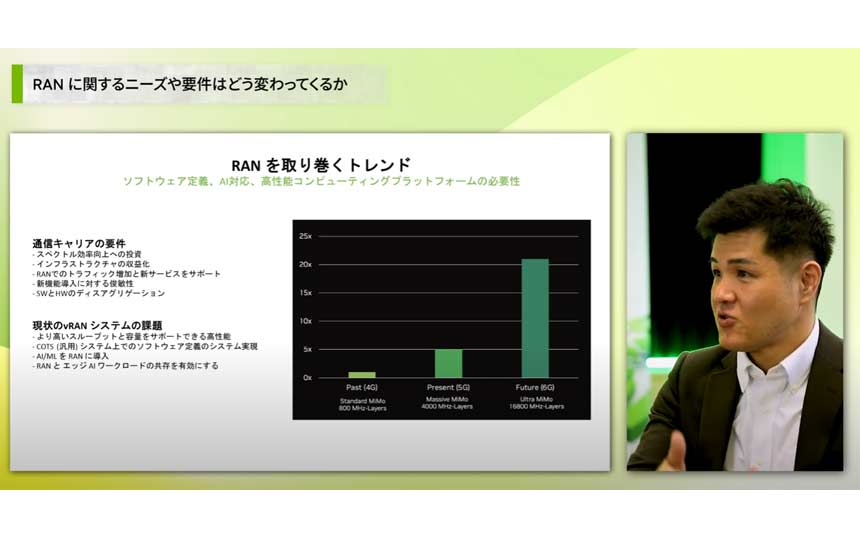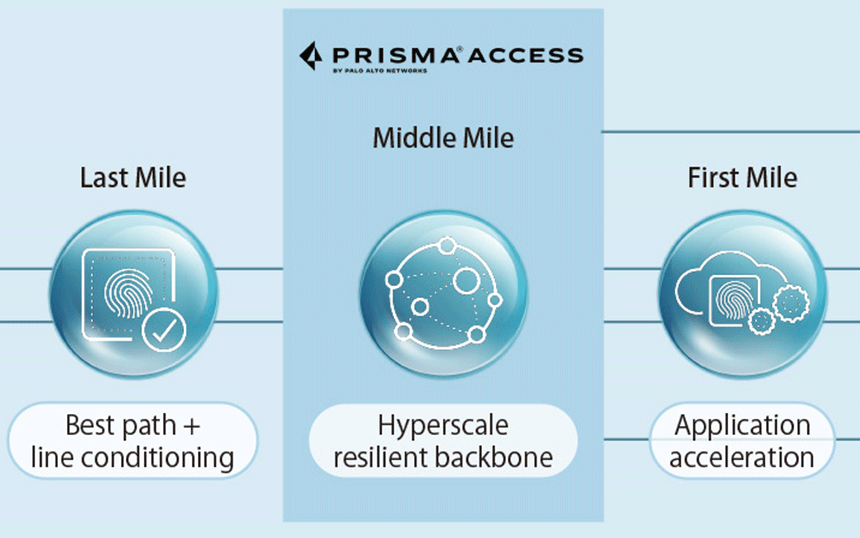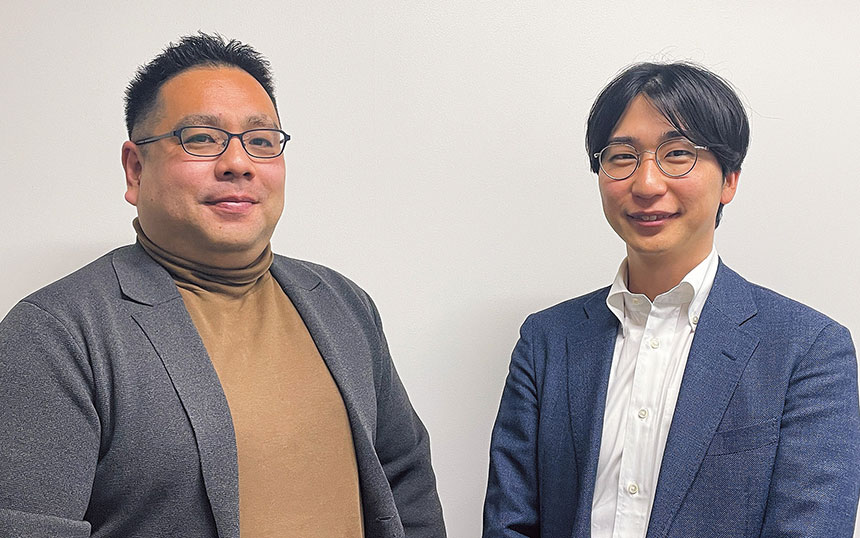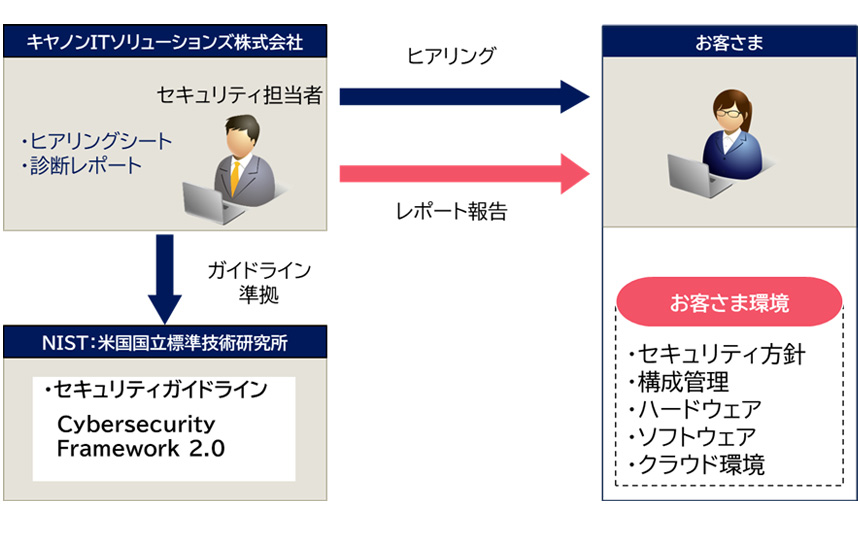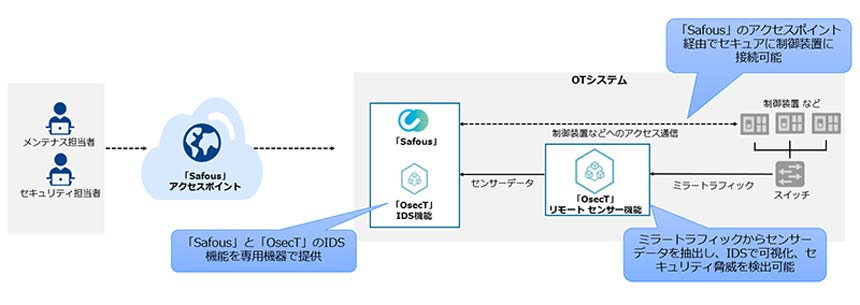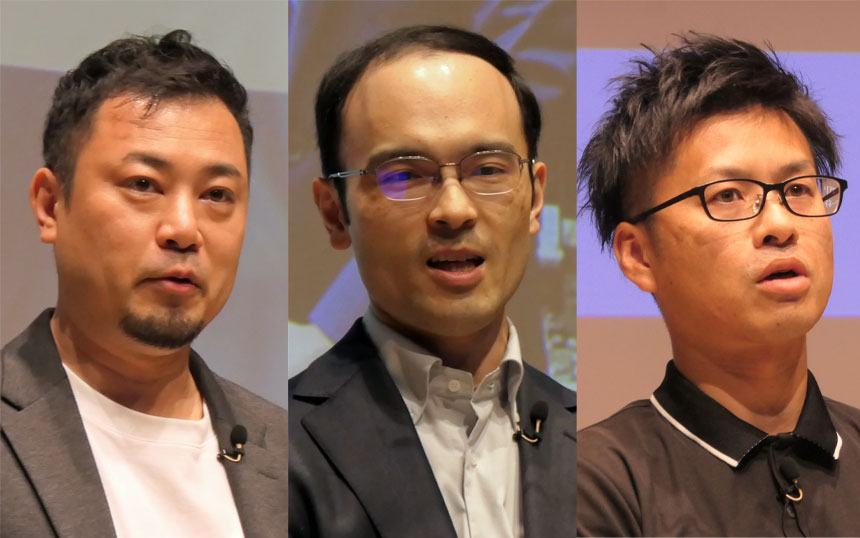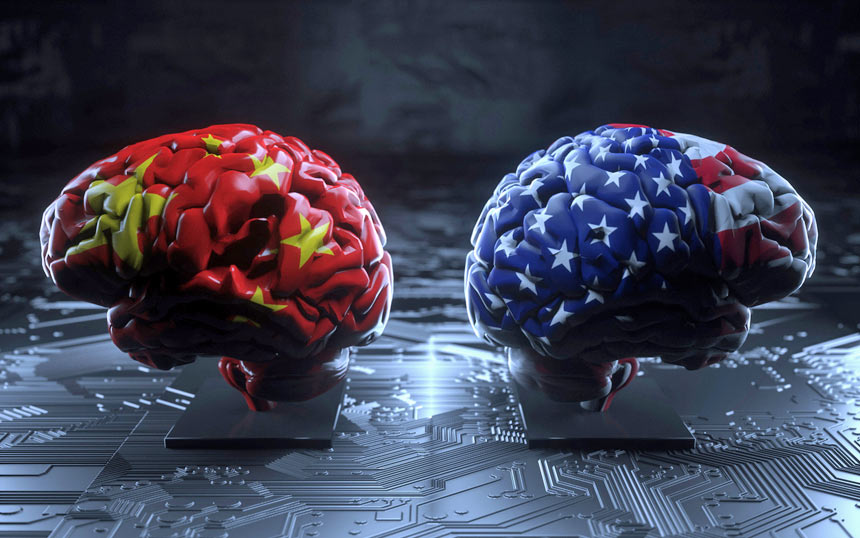
写真◎iStock / Just_Super
2025年1月に公開された中国DeepSeek社の大規模言語モデル「DeepSeek-R1」は、これまで米国企業の先端的なハードウェア資源に大きく依存してきたAI研究開発が、根本的に変化する可能性を示した。
米国が中国を警戒して行ったNvidia社の最先端GPUの輸出規制が、DeepSeek社の独自の学習方法による最先端GPUへの依存性軽減という、米国の立場からはある意味で逆効果とも言える事態に繋がっているのは非常に皮肉である。Nvidia製GPUの入手が難しくなったことで、中国国内の研究者や企業は、より効率的なモデル設計や分散学習手法、省メモリ化技術の開発に注力せざるを得なくなり、その結果として、DeepSeek社のようにハードウェア資源に依存しない革新的な学習戦略が生まれつつある。
こうした技術的独立の流れは、中国のAI開発における自立を促進し、米国の技術的優位性を基盤とした制裁戦略の限界を示唆するものでもある。今後、同様のアプローチが他国にも広がれば、AI開発の重心が再び大きく動く可能性がある。
短期間に連続して脚光浴びた中国のAIモデル
DeepSeekが世界に与えた衝撃の余韻がまだ残る今年3月、中国のスタートアップMonica社から汎用AIエージェント「Manus」が公開され、注目を集めた。従来の大規模言語モデルが会話の生成に留まっていたのに対し、Manusは自律的に行動してユーザが必要とする作業を直接行うところまで至っているエージェントである。
数えきれないほどのAIモデルが毎日のように公開され、それぞれ注目を集めようとしている中で、今回の成果が一時期的なスポットライトにすぎないか、それとも本質的に有意義なのかを把握するのは容易ではなく、時間の経過を要するところもある。しかし、数ヶ月という非常に短い時間の間に、中国のAIモデルが連続的に注目を集めた事実が示唆する意義を看過してはならない。
一般に知られている中国の最近の成果としてはDeepSeekやManusが代表的であるが、実は中国で注目を集めているスタートアップ企業や研究開発の成果は他にも数多くある。「XLNet」などの大規模トランスフォーマで知られている杨植麟(ヤン・ジーリン)氏が立ち上げたMoonShot AI社、ロボット犬の「go1」や「go2」で知られているUnitree社や、ヒューマノイドロボットを開発するAgiBot社なども、欧米の有望なスタートアップに比べても負けない程度の存在感を出しており、AlibabaやBaiduなど、一部の大企業に限られていた中国産AIの領域を広げている。
また、CVPR・ICML・NeurIPS・ICLRなどの最も高い水準のAI国際学会でも、中国から発表される論文数が米国の論文数を超えつつある。米国で発表されている最先端研究の多くには中国人の研究者が関わっていることを考えると、実際の中国の影響力は数値に現れる以上に及ぶと容易に想定できる。
3月には中国科学技術大学がGoogle社の昨年度の量子コンピュータより100倍程度演算速度が早い105量子ビット(Qbit)量子コンピュータ「Zuchongzhi-3」を公開するなど、中国の技術力はAIを筆頭に先端技術全般にわたって急速に進歩している。単なる量的な成長に留まらず、ある種の高いダイナミズムやエネルギーのようなものを、研究者である筆者としても感じるところが多い。