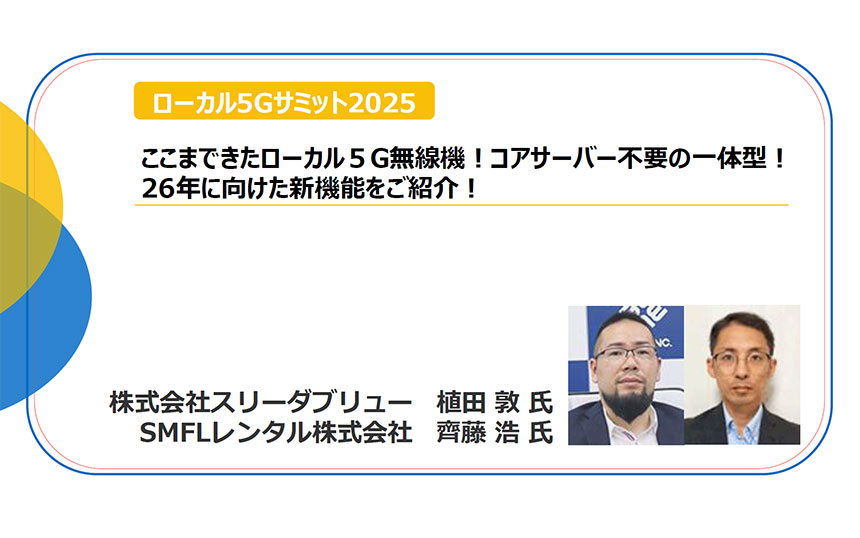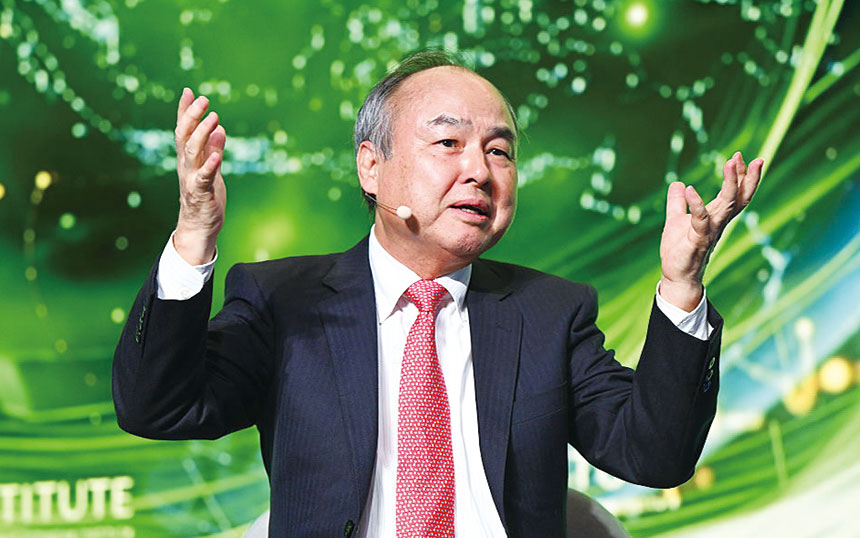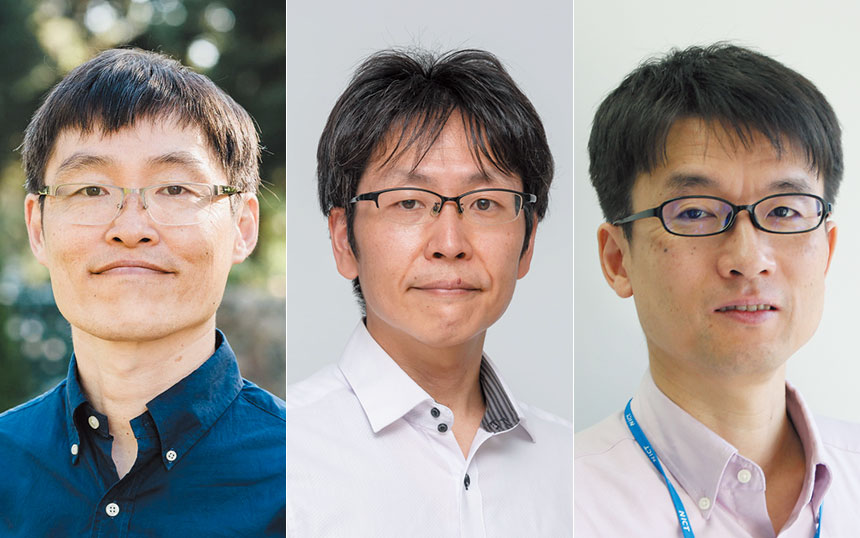ネオテニー
WUが電話をおもちゃと呼んだように、ある経営者がPCをおもちゃと呼んだように、全く新しい製品やサービスは、その黎明期には「おもちゃ」に見える。会社の上層部やオピニオンリーダーなどが、ある新しいサービスや商品などについて「価値がない」とか「おもちゃ」と口にしたときには要注意だ。そのサービスや商品は「ネオテニー」であり、大成功する可能性を秘めているかもしれないからだ。ネオテニーの代表的な生物は、一時期、日本でも人気のあったウーパールーパーである。
 |
 |
| ネオテニーの代表的生物であるウーパールーパー (イラスト:的場史子) | |
ウーパールーパーは、両生類つまりカエルと同じ種族であるが、オタマジャクシすなわち幼生の状態のまま成熟し、繁殖する。
1920年にL・ボルクは「人類ネオテニー説」を提唱した。ボルクによれば、ネオテニーは進化の過程に重要な役割を果たすという。ネオテニーは幼児または退化した状態であり、器官の特殊化が低く未分化であるために、新しい環境に適応する可能性が高いというのだ。真の進化の前には、一度、幼児化する必要があるということは、いったん体を縮めて再び成長し、いったん進化の枝を逆行して再進化するようなものだ。あたかもバネを縮めて指を離したとき、エネルギーが解放されるような状態を想像するとよいだろう。
そういえば、あるコミック誌に、ベンチャーはビジネスの経験者が参加するよりは、未経験者ばかりの方が成長するというシーンがあった。
かつてソニーに在籍していたあるエンジニアは、歯車の絵を数点描きながら、「ソニーは、歯車を小型化する必要に迫られたとき、経験も知識も少ない私たちに開発を任せた。仲間の1人はデッサンの天才的な才能があった。彼は、機械工学の知識がなかったため、金属の強度を知らずに、薄い形状の超小型の歯車の絵をフリーハンドで実寸大に見事に描いてみせた。経験者や専門家は、こんなに小さく薄い歯車は強度の関係で開発は不可能だと断じた。しかし私たちは、知識や経験がないために常識に縛られることなく、天才デザイナーが描いた歯車の開発に成功した。この歯車はソニーの製品のイノベーションに生かされた」と語った。このように知識や経験がない方が、イノベーションを生み出すこともある。
既存のバリューチェーンの関係性とホメオタシス(恒常性)の中で支配されてしか生存できない筆者のような平凡な経験者は、その自己保存本能から決して変わろうとはしない。その均衡の中での関係性こそが絶望という「死に至る病」なのである。組織の存続を保つホメオタシスは、環境への過剰反応を引き起こす。堺屋太一は、これを「巨大組織を死に至らしめる業病」と語った。我が国の大本営が、空力を軽んじ、対艦巨砲主義に陥ったのも日露戦争での海軍での成功体験にあった。「環境に過剰適応」した企業や制度は、その環境変化に追従できない。
それは恐竜の絶滅にも似ている。恐竜は進化の袋小路に入っていた。環境に過剰適応した恐竜は、地球に衝突した隕石による地球環境の激変において死滅した。一方、原始的で小型の哺乳類や鳥類は、環境の激変においても生き残った。WUの崩壊もガラパゴス携帯も、バリューチェーンを堅持する企業のホメオタシスが原因だ。