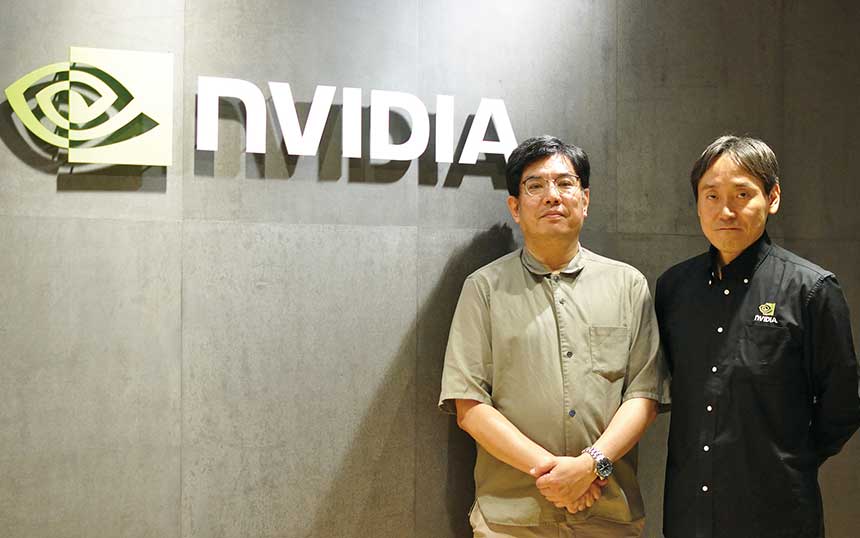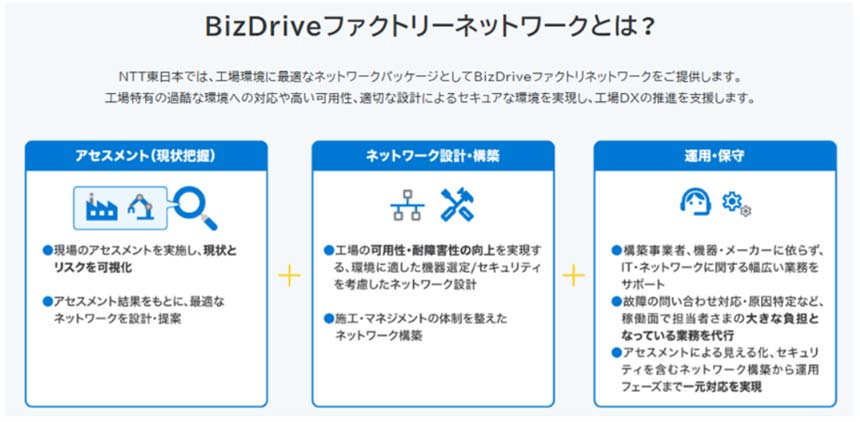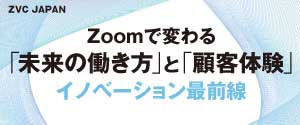Amazon Kuiperがついに始動
Starlink以外のLEOコンステレーションは、OneWebが648機、Iridium-NEXTが66機と規模が小さくなる。また、ルクセンブルクのSESが運営するO3b mPOWERは、GEOとLEOの中間に当たる中軌道(MEO)コンステレーションで、高度8000kmを周回する12機のMEO衛星で高スループットな通信サービスを提供している。
そして、Starlinkの対抗馬として注目が集まっているのが、Amazonが2025年以降のサービス開始を計画しているProject Kuiperだ。約3200機の衛星を使って第1次衛星通信システムを構築する計画で、2025年4月に第1回の、6月に2回めの衛星打ち上げに成功し、27機ずつの衛星を軌道上に届けている。1回ごとに数十機ずつを送り出す打ち上げを合計80回以上確保しているという。

2025年4月、AmazonのLEOコンステレーション「Project Kuiper」が第1回衛星打ち上げに成功した。6月には第2回も成功。今後80回で3000機以上を宇宙へ送り出す(画像:ULA発表資料)
Amazonは「下り最大1Gbps、上り最大400Mbps」の衛星通信サービスを提供することを目標に掲げている。アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)常務執行役員 情報通信・メディア・エンターテイメントゲーム・スポーツ・戦略事業統括本部 統括本部長の恒松幹彦氏によれば、「通信速度が異なる3種類のカスタマーターミナルを用意し、高速から低速まで幅広いニーズに応えられるように準備している」という。また、「光衛星間通信も搭載しており、メッシュ型のコンステレーションを組む。地上ネットワークとNTNを連携させてサービスを提供する」。
AmazonはNTTやスカパーJSATと2023年に、Project Kuiperの国内展開に関する戦略的協業に合意。NTTグループ内で活用するほか、日本企業や政府機関・自治体へ提供する計画だ。NTTの宇宙ビジネス「NTT C89」においても、Kuiperは重要な役割を果たすことが期待される。
実用化へ動く5G NTN
このように進化するNTNを地上の5Gネットワークと連携させてより便利に使おうという取り組みが、5G NTNだ。 3GPPでは、2022年に完了したRelease 17で5G NTNの最初の仕様を策定。地上設備と異なり高速移動する通信衛星やHAPS等を5Gネットワークの一部として活用するための技術仕様を決めた。同時に、NB-IoTやeMTC(enhanced Machine Type Communication)対応端末をサポートする「5G IoT-NTN」も仕様化されている。これら5G NTN仕様はその後、5G-Advancedの最初の仕様であるRel 18以降でも拡張され、6Gへとつながっていくことになる。
これを受けて、5G NTNの社会実装への取り組みも加速している。スマートフォンと衛星の直接通信が注目されがちだが、IoT分野での期待も大きい。最後に、日本が関連する動きを紹介しよう。
自動車メーカーや通信事業者の国際業界団体で、5Gを活用した自動運転やコネクテッドカーのユースケースを開発する5G Automotive Association(5G AA)は今年、3GPP Rel 17に準拠したNTNに関する複数のプロジェクトを行った。
BMWグループ、ドイツテレコム、Viasat、GEO衛星を使ったNTNサービスを提供するSkyloらの共同プロジェクトでは、ドライバーへの危険警告や自動車からの緊急メッセージ送信等の有効性を実証。CubicTelecom、Viasat、Skyloは、NTNを経由した通話やNTNと地上系ネットワークとのシームレスな接続切り替えの検証も行っている。これらの検証には、日本のアンリツがテストソリューションの提供で参加している。
シャープは今年2月、OneWeb、MediaTek、Airbus Defense and Space、ITRIと共同で、LEO衛星を経由した5G NTN通信に世界で初めて成功した。シャープはLEO衛星向けの地上局用フラットパネルアンテナを開発しており、その試作機(下写真)を用いて、LEO衛星経由の双方向通信を行った。5G技術のネットワークスライシングを衛星通信にも適用することで、自動運転や機器の遠隔制御など幅広いユースケースをサポートすることを想定しており、早期の実用化を目指す。

シャープが開発した地上局用フラットパネルアンテナの試作機
また、先述のEST-9では衛星通信と5G技術を活用したユースケース実証等も行われる予定で、5G NTNによるアプリケーション創出が期待される。
今後は、マルチオービットに加えて地上網とも連携する「NTNの三次元化」が大きなテーマとなる。衛星間や衛星−地上間をつなぐ光衛星通信技術だけでなく、各衛星通信インフラの制御を共通化、統合するための枠組みづくりや技術開発が鍵になることは間違いない。衛星通信インフラそのものでは遅れを取る日本は、この「つなぎ役」として存在感を発揮したいところだ。