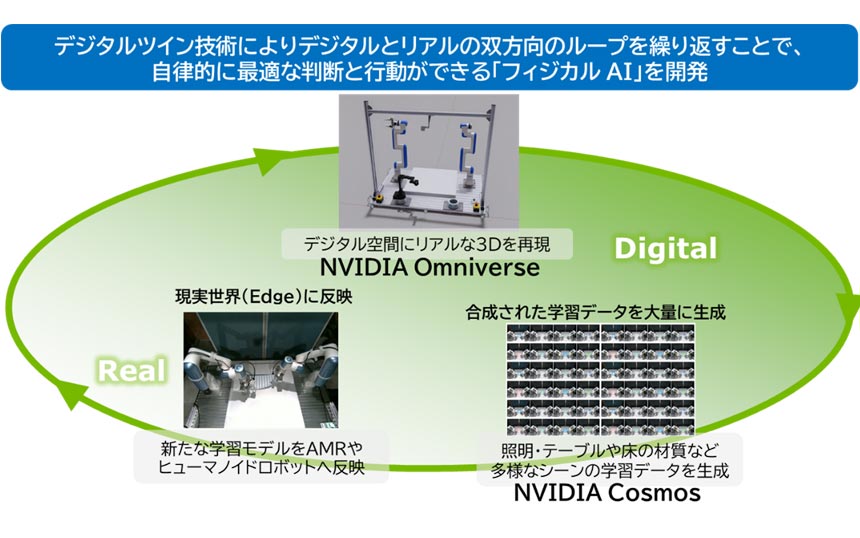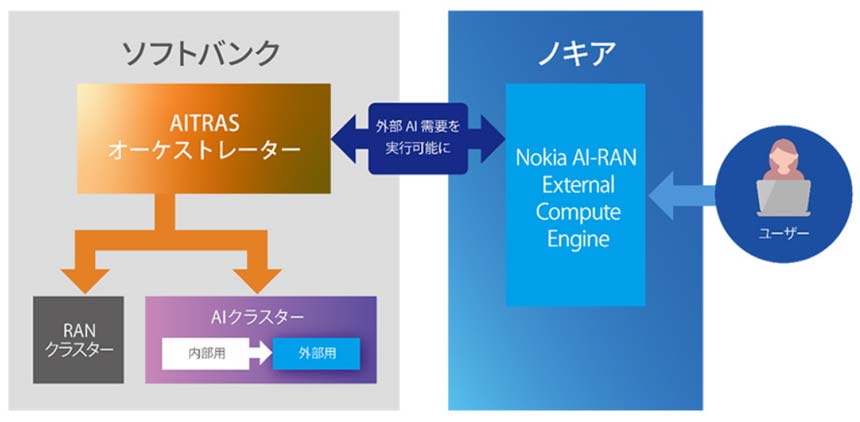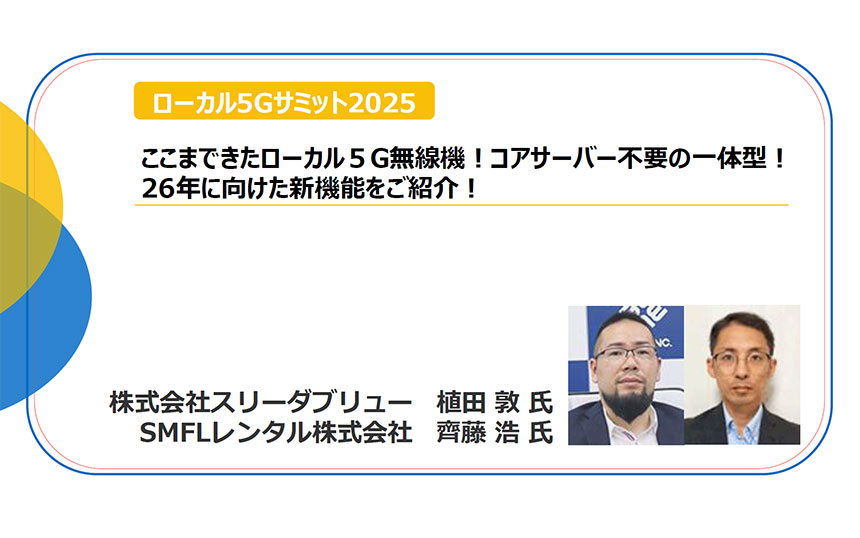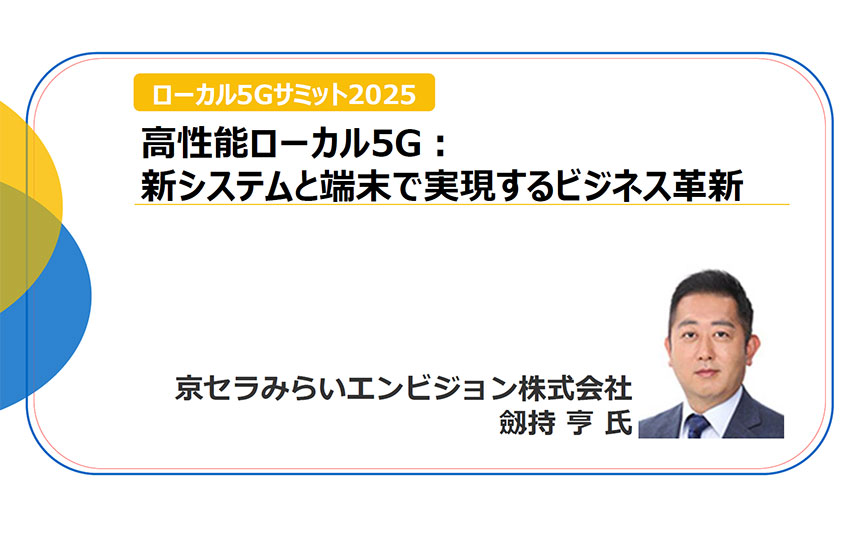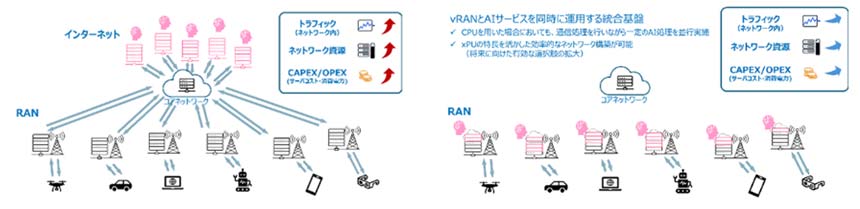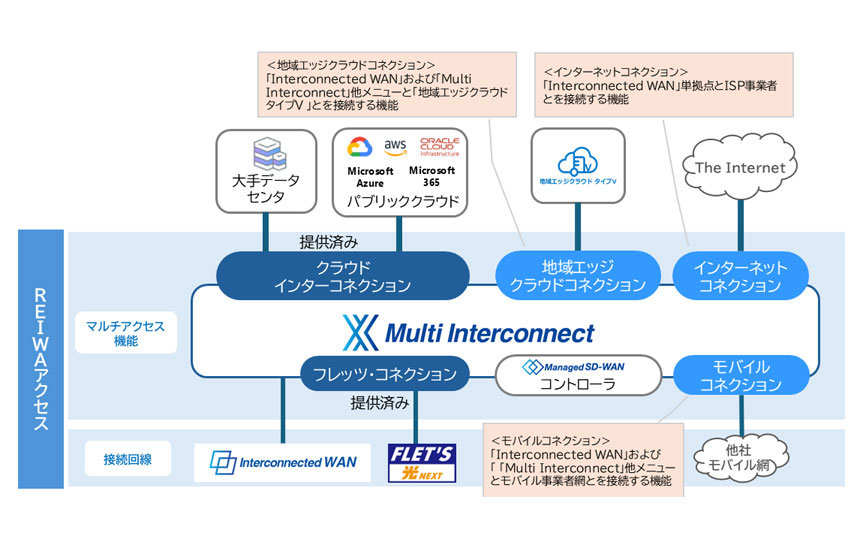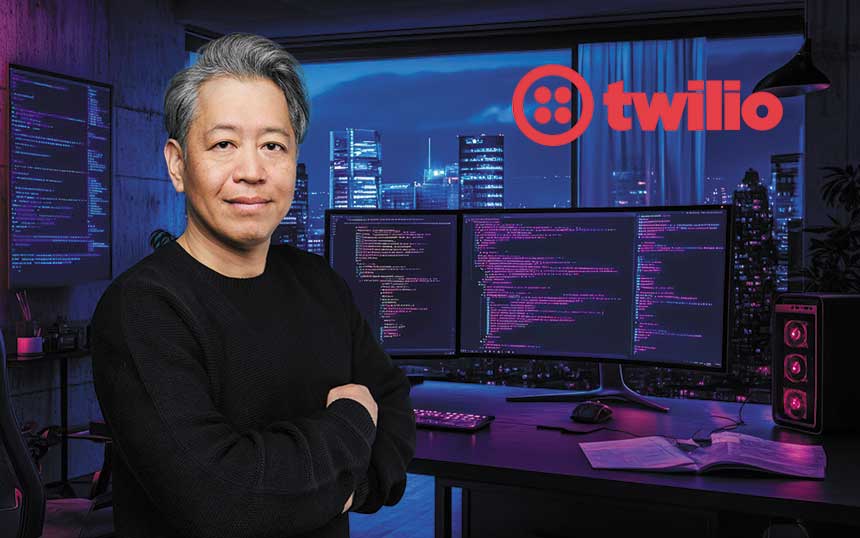
Twilio Japan 代表執行役員 社長の久保敦氏。NTT、インテル、リンクトイン、グーグル・クラウド・ジャパンを経て現職。IT業界での30年以上の経験をもとに、Twilio Japanで日本市場における展開を統括する
――Twilioは、音声・ビデオ通話やSMS、チャットなどのコミュニケーション機能をAPI経由で提供するCPaaS(Communication Platform as a Service)市場をリードしていますが、最新のビジネス状況を教えてください。
久保 現在、Twilioは世界で30万社以上にサービスを提供しています。最近は、音声通話機能の「Programmable Voice」やSMS送信用のAPIの導入から開始し、AIチャットやパーソナライズ対応へと発展するケースが増えています。APIトランザクションは年間13兆回を超えますが、国や地域ごとの通信規制・ネットワーク環境の違いを超え、グローバルに安定して利用できるのが長所です。
――幅広くサービスを提供するなかで、企業にはどんな課題があると考えていますか。
久保 顧客体験が一貫していないことです。
特に日本では、組織が縦割りであることに加え、メールやSMS、電話などチャネルごとのやり取りがバラバラに設計されており、どのチャネルでいつ、どう届けるのが最も効果的かが把握されていないことも多くあります。北米の航空会社では、乗り継ぎをする搭乗客に対し、着陸後に乗り継ぎ便のゲートや移動時間などの詳細な案内をSMSで送る例がありますが、日本では実現していません。
当社がグローバルで行った調査では、パーソナライズされた体験の提供に自信を持つ企業が46%ある一方で、実際にそう感じている顧客はわずか15%に過ぎません。このギャップは、単に技術が未熟だからというよりも、組織的な断絶やデータの分断が背景にあります。
収集した顧客データを十分に活用できていないことも問題です。CDP(カスタマーデータプラットフォーム)やCRMを導入しても、データ同士が連携されていなければ意味のあるコンテキストが生まれません。これはAIを活用するうえでも大きな障壁です。
「BYO-LLM」で柔軟なAI活用
――企業が保有するデータを連携させ、コミュニケーションチャネルを統合して一貫した顧客体験を提供するのがTwilioの「顧客エンゲージメントプラットフォーム」ですね。どのように実現しているのですか。
久保 3つの柱があります。
まず1つめは、「コンテクスチュアルデータ(文脈情報)」の収集と統合です。CDP「Twilio Segment」は、ユーザーのWeb・アプリでの行動や購買履歴、過去の問い合わせ内容などをリアルタイムに収集し、プロファイルとして一元化します。これによって「誰に・何を・いつ届けるか」の判断が可能になります。
2つめがAIの活用です。Twilioは、お客様が選んだ生成AIモデルを適材適所で活用する「Bring Your Own LLM(BYO-LLM)」の考え方を採っています。これにより、各社のセキュリティポリシーや業務要件に応じて、AIチャットボットやバーチャルエージェントを通じた柔軟でパーソナライズされた顧客体験を実現できます。
そして3つめは、マルチチャネルでのコミュニケーションです。Twilioは各チャネルをAPI経由で統合提供しており、例えば、「予約リマインドはSMS」「緊急通知は電話」「キャンペーンはメール」といった使い分けを、ユーザーごとに動的に行える設計になっています。
現在、パートナー企業と連携しながら、AIエージェントが顧客とのやりとりを「話す・聞く・見る」というインターフェースレベルまで支援することを目指しています。将来的には、AIが顧客の状況に応じて最適なチャネルを自動で選択することも視野に入れています。