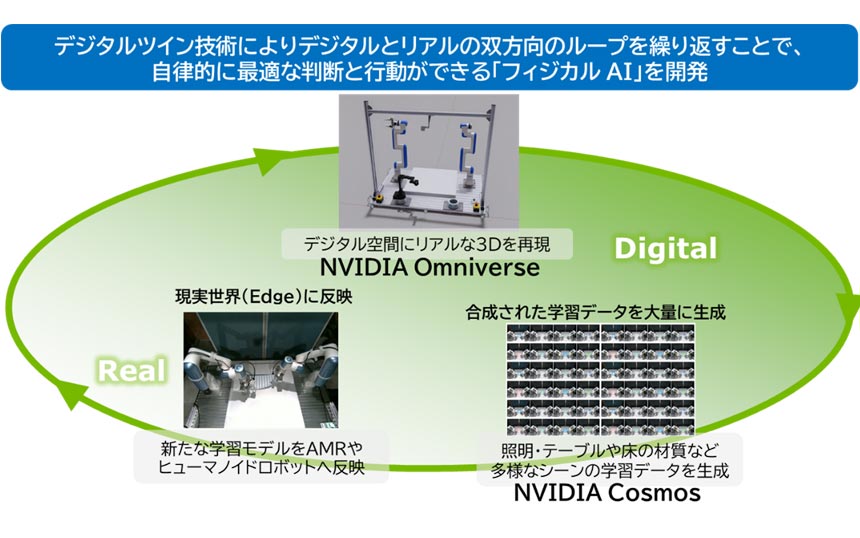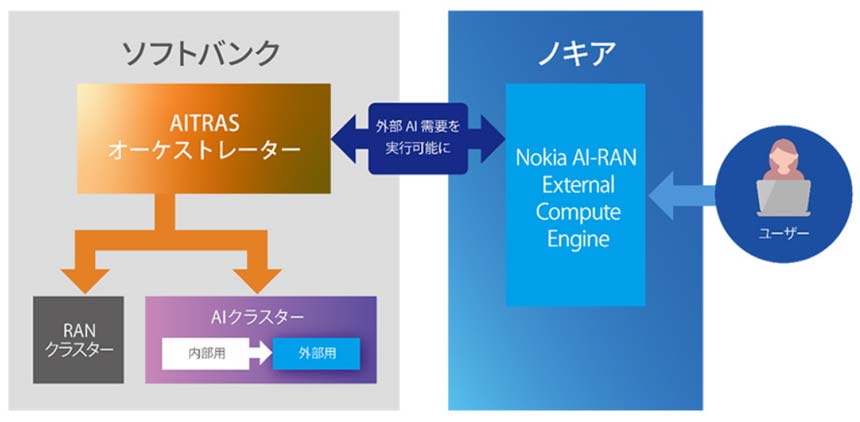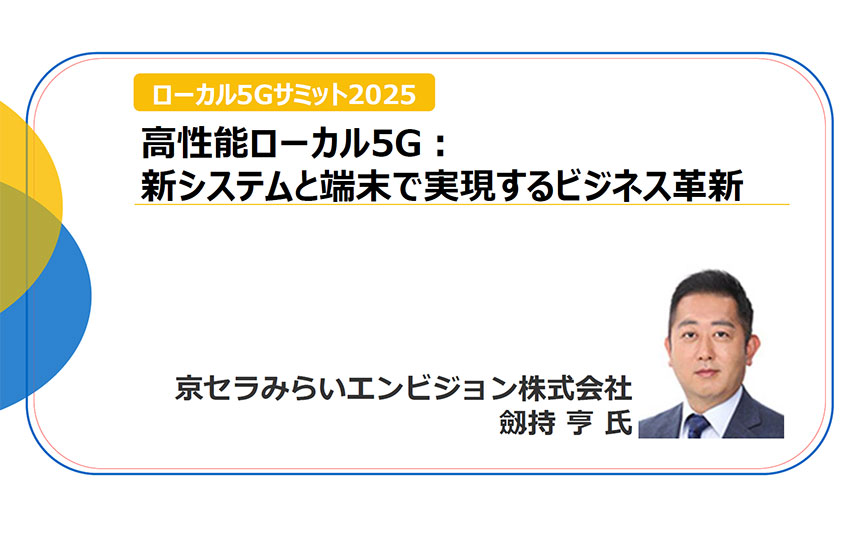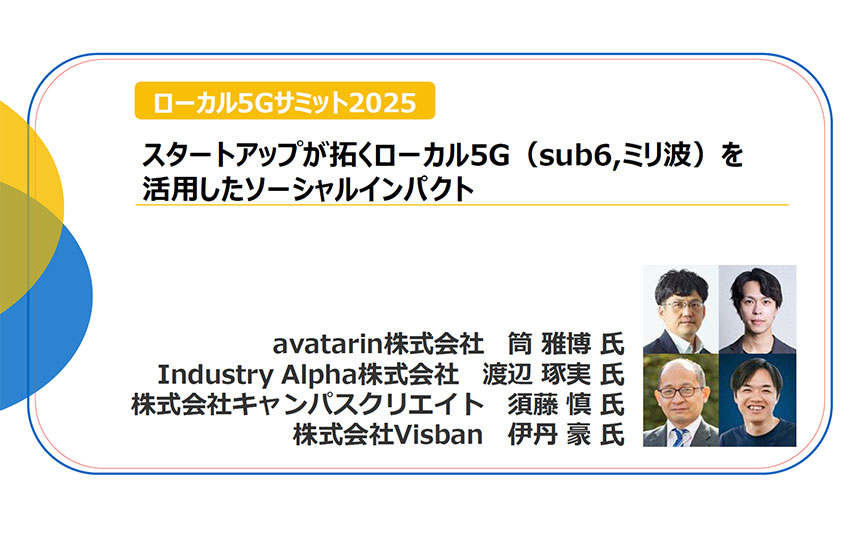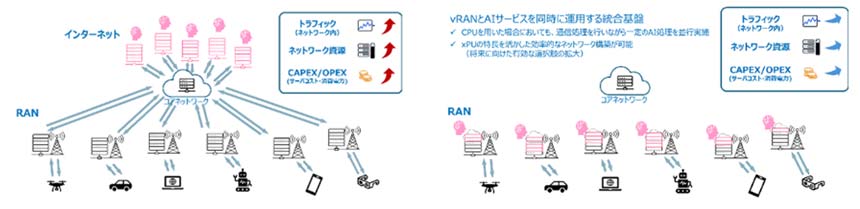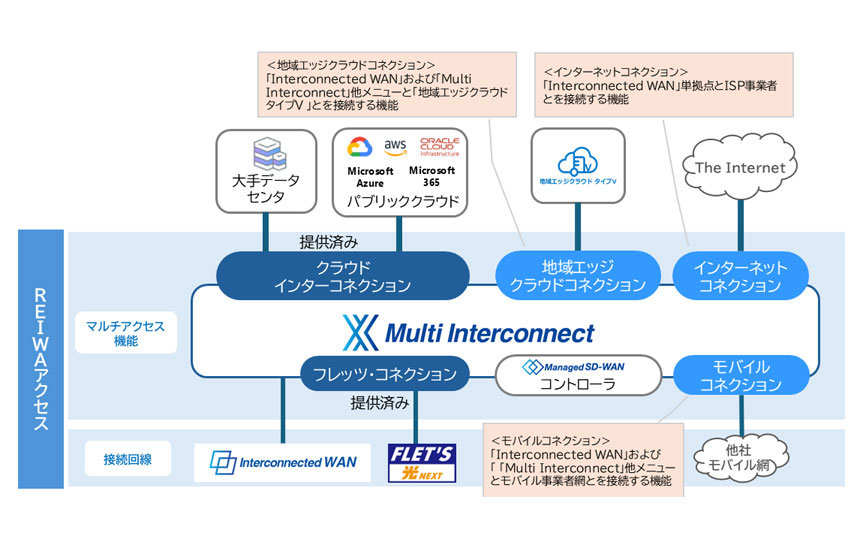2030年頃の商用化が見込まれている6G。その標準化作業(Work Item)に先立って行われる調査・検討フェーズ(Study Item)は、2025年夏頃に開始される3GPP Release 20(以下、Rel.20)から本格化する。このフェーズでの検討結果を踏まえ、2027年に始まるRel.21において6Gの初期仕様が策定され、2028年にはその策定が完了する見通しだ。
6Gの登場により、2030年以降にはどんなユースケースが実現するのだろうか。2023年11月に開催されたITU(国際電気通信連合)の無線通信総会(RA-23)では、6Gに相当するIMT-2030のフレームワーク勧告が承認された。その中では、没入型コミュニケーション、AIとコミュニケーションの統合、ユビキタス・コネクティビティといった利用シナリオが挙げられている。
「没入型体験」は6Gが不可欠
6G時代の没入型コミュニケーションについては、VR/ARやメタバースの活用に加え、手触りや味、匂いなどの「感覚共有」が行えるようになると期待されている。メタバースをより多くの人が快適に利用したり、人の感じ方や五感の情報を重畳して送るには、5Gを凌ぐ高速大容量・低遅延性能が求められる。また、わずかな遅延やデータの欠落が、受け手に“違和感”を与える可能性もある。
身体・感覚・感情などをあらゆる場所へ相手に合わせて共有する「人間拡張基盤」の実用化を目指すNTTドコモでは、6Gをその中核技術として位置づけている。人間拡張基盤は、例えば洋服の手触りや食品の味を自宅で体験可能なインターネット通販、トップアスリートの動作や感覚を追体験できるコンテンツなど、これまでにない新たなユーザー体験を可能にする技術である。
ホログラムも、没入型コミュニケーションを支える重要技術の1つだ。国内でも、すでにホログラムを用いた映像広告の配信などが始まっているが、「6Gがよりリアルなユーザー体験を可能にし、マーケティング手法の幅も広げる」。こう話すのは、未来トレンド研究機構が今年3月に刊行した調査レポート「2025年国内における『6G×想定ユースケース(事例)』に関する網羅的な調査」の執筆を担当したDream’s Commerce ゼネラルマネージャーのボリンジャー実穂子氏だ。

Dream’s Commerce ゼネラルマネージャー ボリンジャー実穂子氏
(未来トレンド研究機構の調査レポート
「2025年国内における『6G×想定ユースケース(事例)』に関する網羅的な調査」の執筆を担当)
具体的には、通勤中の車内などで、あたかも誰かが隣に座って会話をしているかのような自然なコミュニケーション体験や、空港で搭乗を待つ乗客に対して、ホログラムを用いてファーストクラスの疑似体験を提供し、チケットのアップグレードへの意欲を高めるといった手法なども構想されているという。