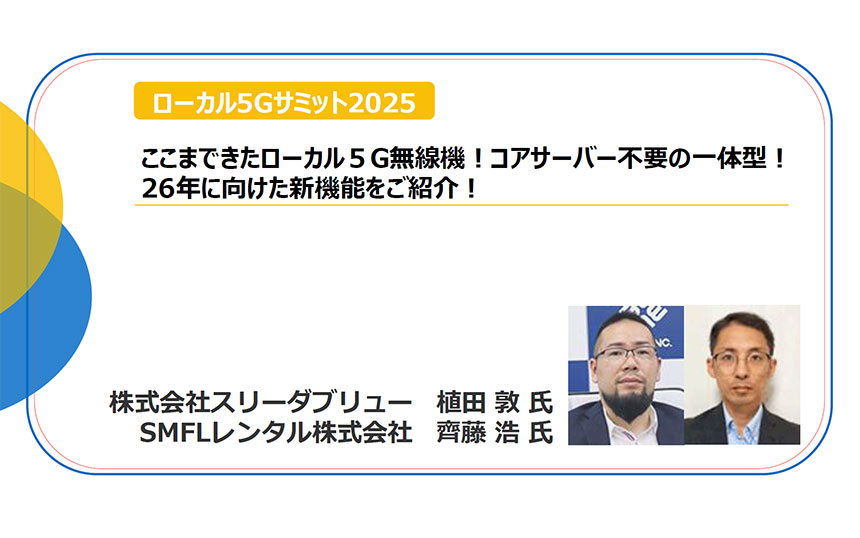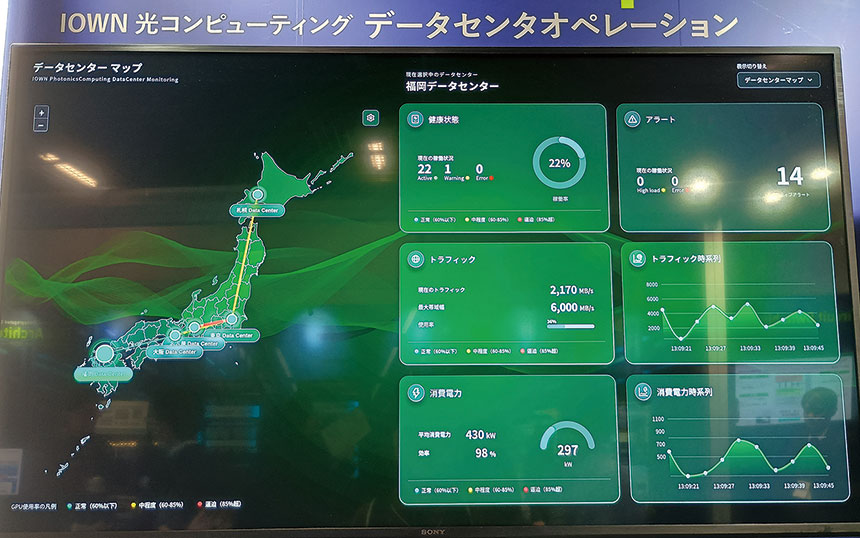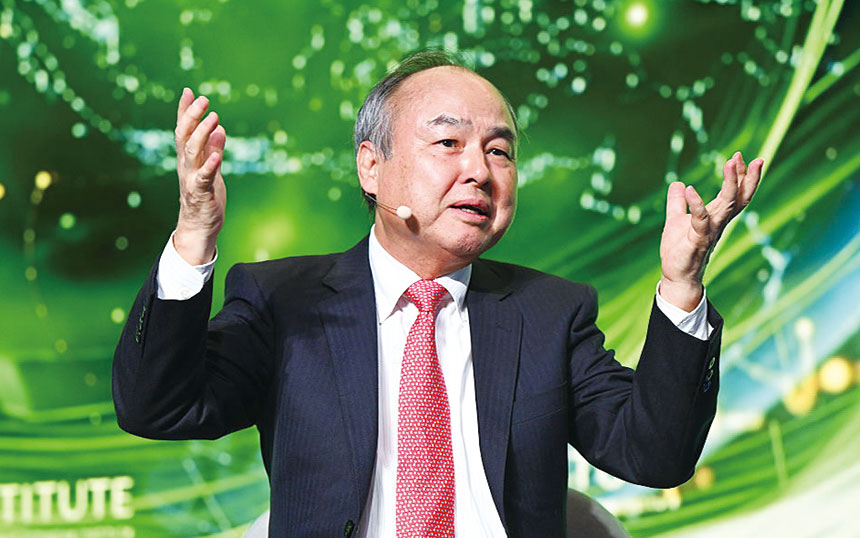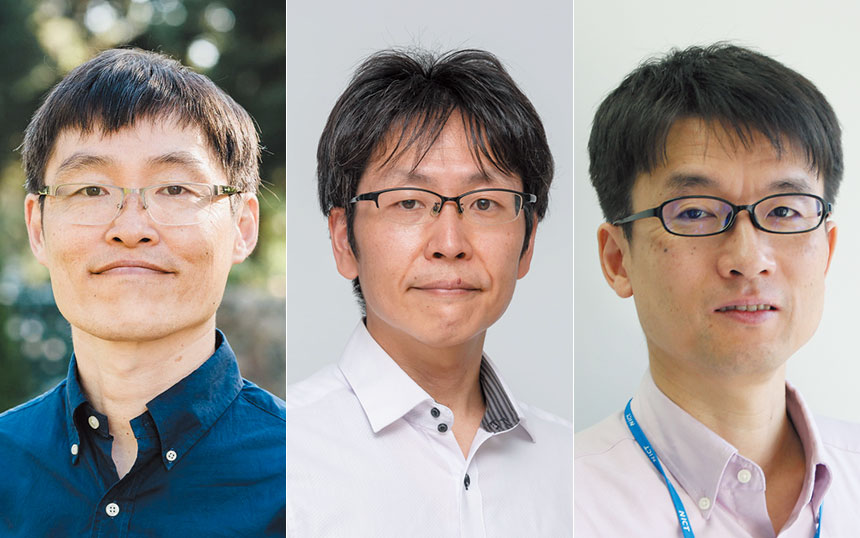「BYOD=安い」は本当か?
こうして見ていくと、BYODだからといって、特別にセキュリティリスクが高まるわけではないことが分かるのではないか。適切に運用管理していかなければならないのは、会社支給でも個人所有でも同じ。「運用管理面でいくつかの留意点があるだけの違い」ともいえなくはない。
とはいえ、IT部門にとってBYODで最も気がかかりな点の1つが、この運用管理面なのも事実だ。
そこで次に、運用管理も含めたコストの観点からBYODを見ていくことにしよう。BYODは、まさにこのコストから注目が集まったという側面もある。BYODなら端末コストを会社側で負担する必要なく、スマートフォン/タブレットの業務利用を推進できるからだが、「BYOD=安い」というのは本当なのだろうか。
JSSEC 技術部会の八津川直伸氏がまず注意を促すのは、端末が多種多様になることによる運用管理コストの増大だ。
「BYODといっても業務で使っているのだから、何かトラブルが起こったときには、ヘルプデスクが対応しなければならない。加えて、一定のセキュリティレベルを維持するため、技術的なセットアップを行う必要もある。ところが、従業員1人ひとりの端末の種類が違うと、ヘルプデスクやセットアップの工数がものすごく増える。企業側からすれば、端末は統一されていたほうが絶対に運用管理しやすい」(八津川氏)
この課題に対する手軽かつ有効な対処策としては、コニカミノルタのケースのように業務利用できる個人所有端末の種類を限定するという方法が挙げられるが、いずれにせよ無分別にBYODを解禁すると、運用管理負荷が想像以上に高まる怖れがあるというのは確かだ。一定の制限の下、段階的にBYODを進めていくのが現実的といえる。
また、端末の購入代金や通信料金の一部を会社側で負担する場合には、次のことも考慮に入れる必要がある。
「企業で一括契約すると個人契約と比べて通信料金はぐんと下がるし、端末もバルクで買ったほうが安い。そう考えると、BYODより会社支給のほうがトータルでは安くなる可能性もある」(八津川氏)
ちなみに、同じく技術部会の関德男氏によると、「日本が『バルクでまとめ買い』という文化なのに対し、米国は従業員に『この予算内で自分の好きな端末を買っておいで』という文化」だという。こうした“購買”文化の違いも、日本より米国のほうがBYODによる仕組みが発展した背景として考えられる。
「BYOD=安い」というイメージを鵜呑みにするのではなく、「我が社の場合はどうなるのか」をしっかり考えたうえで判断していくことが重要といえよう。
| >>この記事の読者におすすめのコンテンツ | ||
|