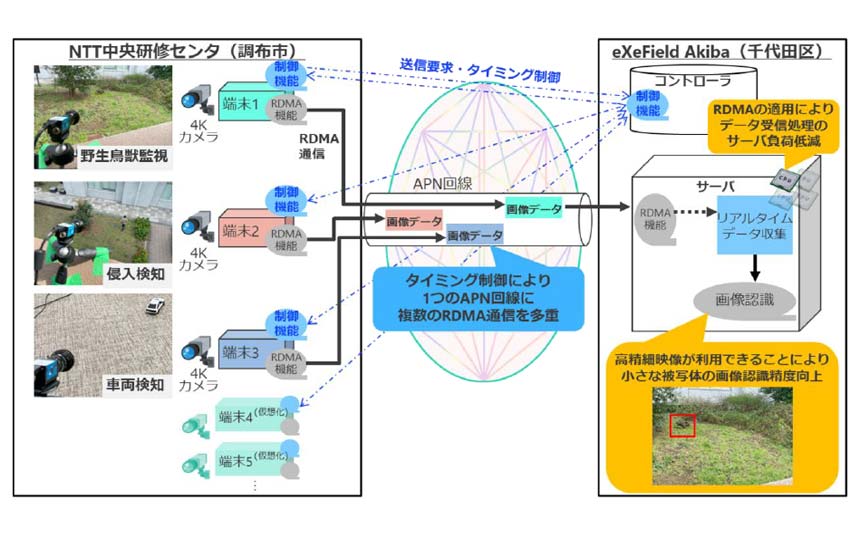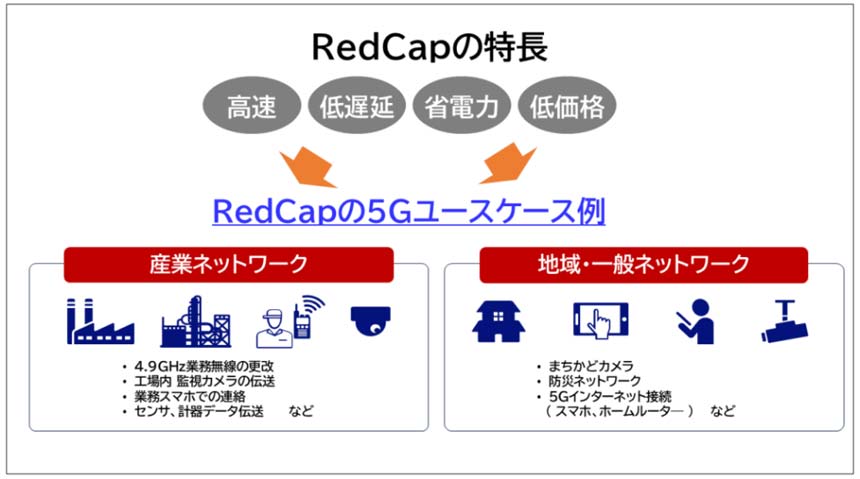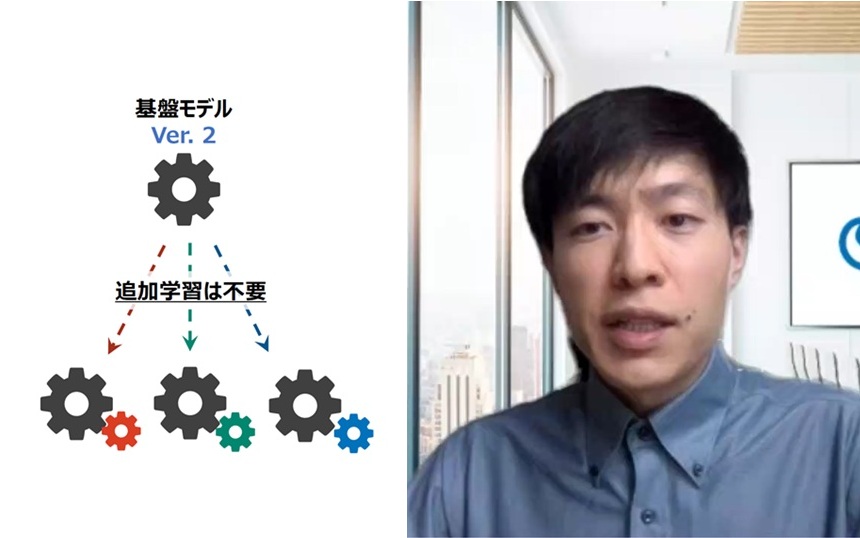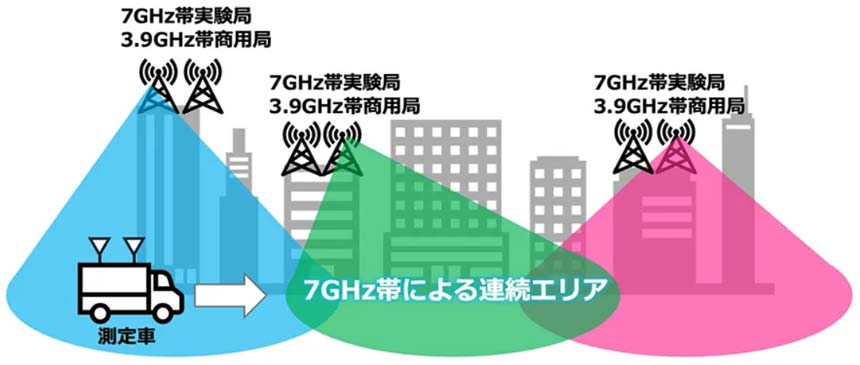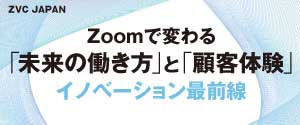中小規模の事業所では、電話のIP化が進まない。理由は、そのメリットがユーザーに理解されないからだ――。
PBX/ビジネスホン市場では未だにそうした声が多く聞かれるが、まったく逆のケースも存在する。2008年末から電話システムのIP化に着手した西川口病院は、その好例だ。
内線かけても捕まらず
同院ではかねてから、スタッフのコミュニケーション不足が課題だった。病院の環境が、一般的なオフィスのそれと大きく異なることは想像に難くない。医師や看護師、事務員らが頻繁に施設内を移動し、受付窓口やナースステーションなどの滞在時間が比較的長い場所であっても机に就いている人数は非常に少ない。
また、シフト制の勤務形態も情報伝達・共有の阻害要因となる。西川口病院の場合は、常時20人程度で業務を行うのに対しスタッフの頭数は60人強。勤務状況とその所在・状況を把握するのは容易ではない。例えるならば、レガシーPBXでフリーアドレス制のオフィスを運営しているようなもの。必然、内線通話の頻度は極端に少なかった。
状況の改善にはまず、電話を有効に活用できる仕組み作りが必要だ。経営管理室の柿沼宏幸室長は、移設やシステム変更の自由度の高さ、さらに情報系・基幹系システムとの連携も見越して、IP化を前提にシステム選定を開始。だが、同氏は滑り出しから躓くことになった。
 |
| 経営管理室室長の柿沼宏幸氏。使用端末はiPhone |