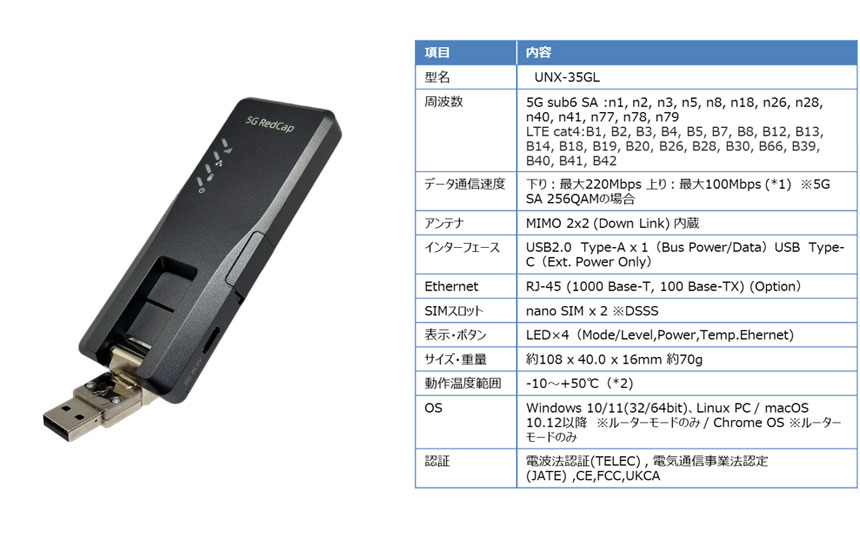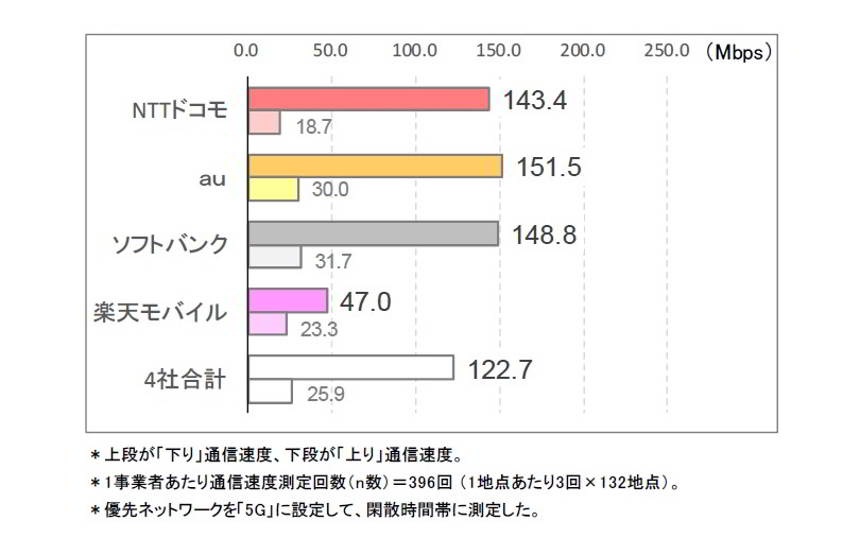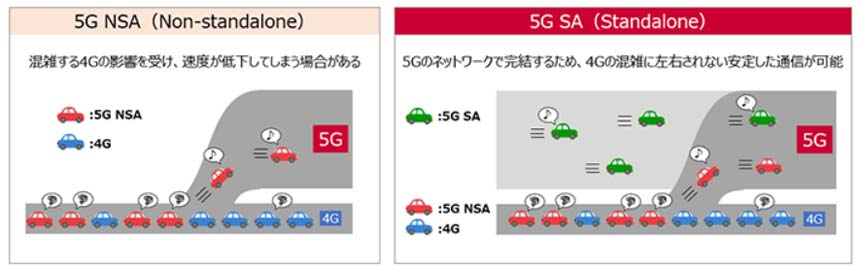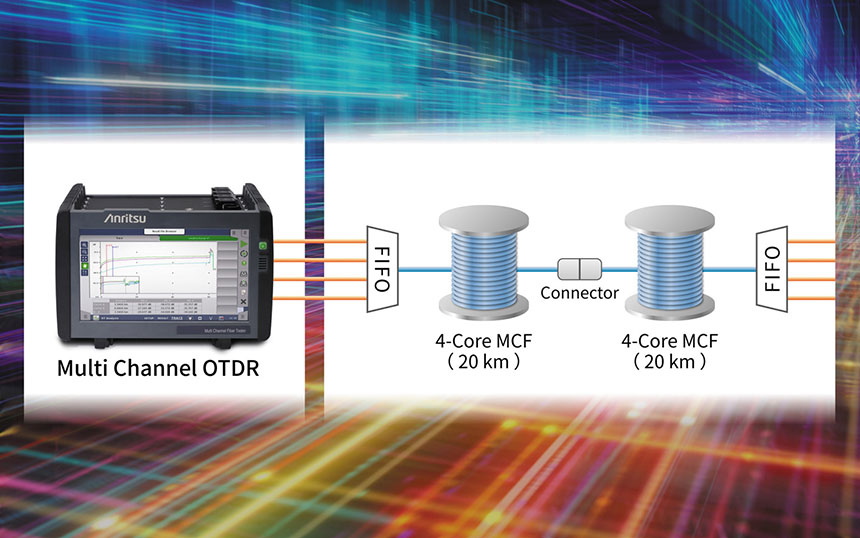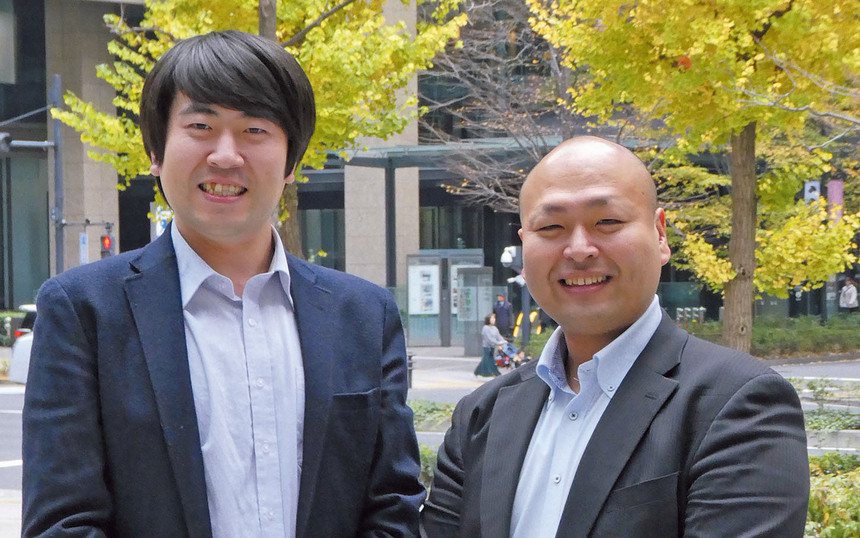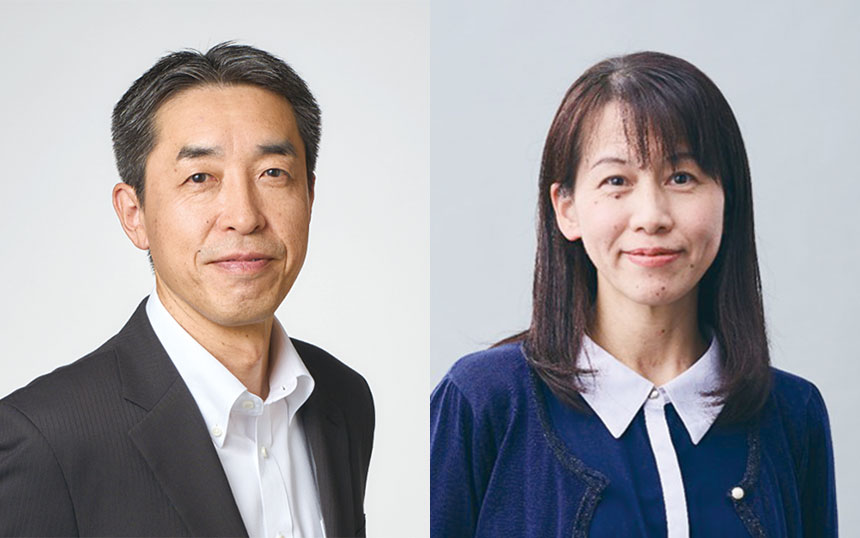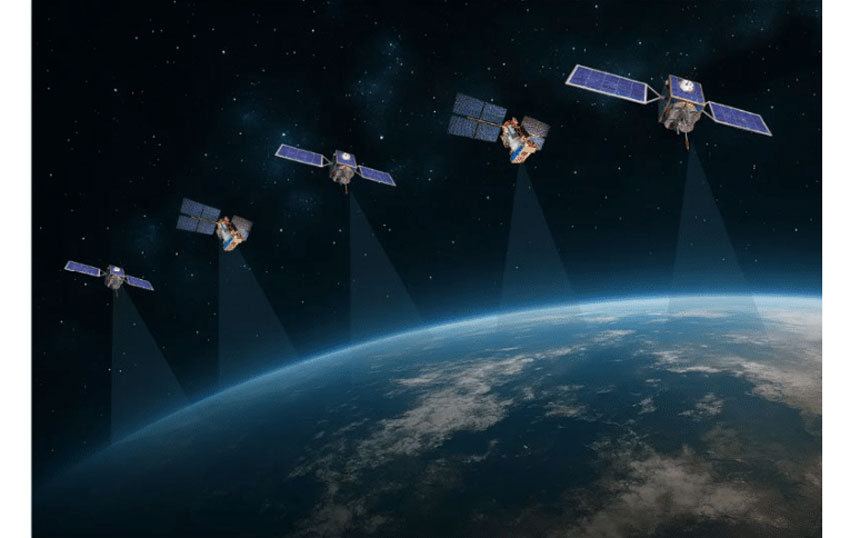ミリ波と呼ばれる高周波数帯は、広い帯域幅を使った超高速通信が可能な点が魅力だ。ただし、電波の直進性が高く飛びにくいため、使いこなすのは難しい。ミリ波通信モジュールを開発するフジクラ 広帯域無線システム開発部 部長の小林聖氏はその特性について次のように話す。
「フェーズドアレイアンテナ※を使ったビームフォーミングが必須。ミリ波は損失が大きいので、無線装置の基板に低損失材料を使ったり、設計にも独特のノウハウが必要だ」
※フェーズドアレイアンテナ 複数のアンテナ素子を配列し、その位相を制御することで電波の送受方向を制御する
そのため、低周波数帯で実績のある無線機メーカーもミリ波は手を出しにくいという。フジクラは光ファイバーで蓄積した高周波領域のアンテナ設計技術を活かし、さらにミリ波向けIC開発のパイオニアであるIBMからライセンス供与を受けて通信モジュールを開発。これから展開が本格化する28GHz帯モジュールを商品化する計画だ。5G無線デバイス開発部 フェロー 部長の官寧氏は、「現在使われている28GHz帯無線装置はプロトタイプ的なもの。本格普及はこれからであり、次世代のミリ波無線機の開発に向けて我々のモジュールを提供していきたい」と話す。無線通信の性能と安定度に深く関わる信号の歪みを抑え、かつビームが広がらない特性を持つ28GHz帯モジュールを開発中で、まもなくワーキングサンプルの提供を始める。
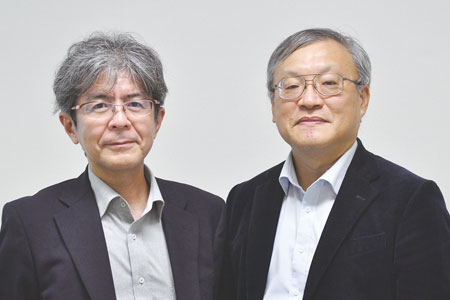
フジクラ 電子応用技術R&Dセンター 5G無線デバイス開発部 フェロー 部長の官寧氏(右)と、
広帯域無線システム開発部 部長の小林聖氏