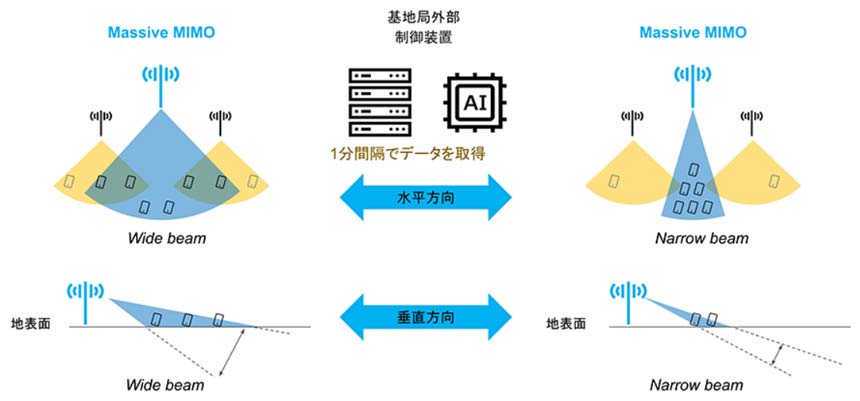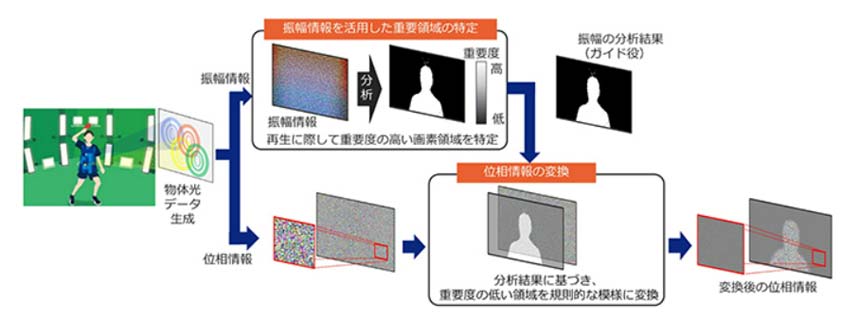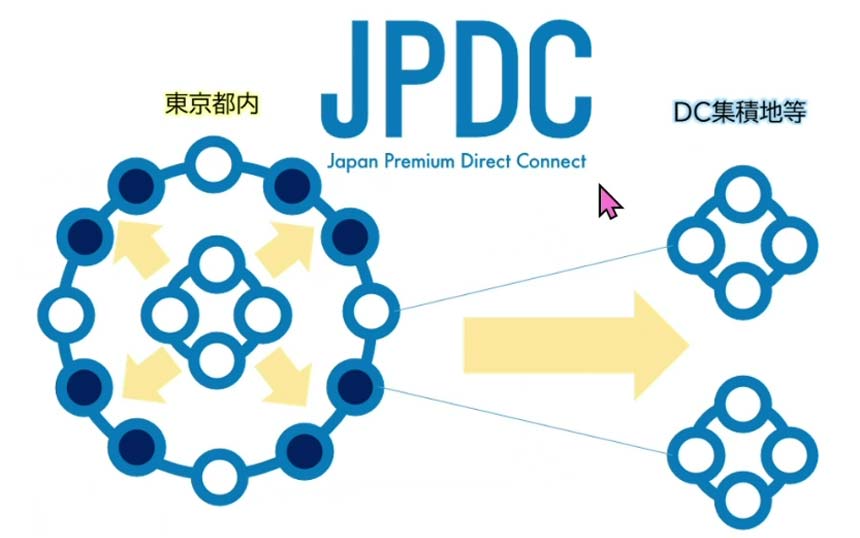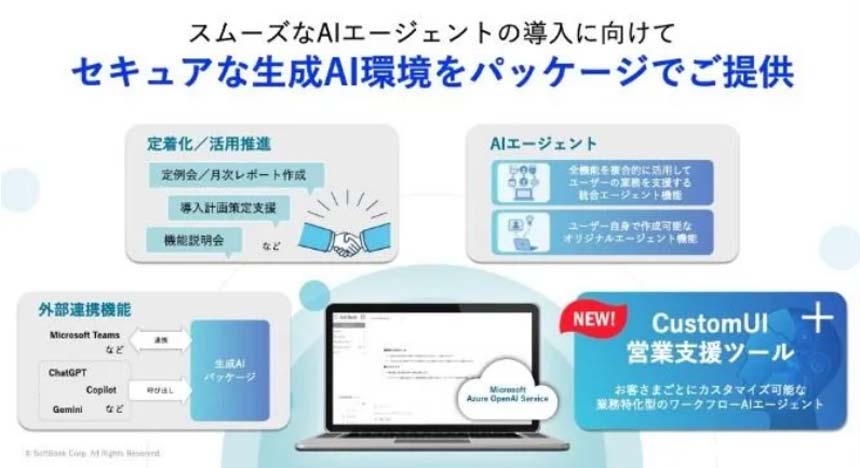「ミリ波は、新しい文化の創造と発展に貢献するツールだ」
そんな観点から5Gミリ波の可能性を見直し、普及推進活動を続けるチームがある。5G/6G推進団体のXGモバイル推進フォーラム(XGMF)で活動する21のプロジェクトの1つ「推し活×5G(ミリ波・ローカル5G)」だ(プロジェクトページはこちら)。
プロジェクト名の通り、フォーカスするのは「推し活」シーンにおける5Gミリ波の活用である。推し活人口は約1400万人、その市場規模は3兆円を超えるとする調査(推し活総研)もある。この推し活文化の発展に貢献することが、ミリ波の活かしどころになるとリーダーを務める吉井大二郎氏は強調する。

「推し活×5G(ミリ波・ローカル5G)」プロジェクトのリーダーを務める吉井大二郎氏(村田製作所)
ミリ波の価値生む3要素
例えば、アイドルのライブイベント会場やサッカースタジアムで“推し”のパフォーマンスを撮影し、SNSに投稿する。スマホがあれば簡単なはずのそんな推し活も、場内Wi-Fiや4G/5G回線が混み合ってできなかった経験を持つ人は珍しくないだろう。どころか、“どうせ通信できない”と端から諦める人も少なくない。
ミリ波が活かせるのは、まさにこうした場面だ。「非日常(推し活など)」「人口密集エリア」「アップリンク活用」の3要素が揃うシーンで高いユーザーエクスペリエンス(UX)を実現することが、消費者に対してミリ波の価値を広く認識させ、ひいては、ミリ波を活用した収益モデルの構築につながると考えてプロジェクトを発足。複数のフィールドサーベイを実施して、ミリ波の実力を測定してきた。
調査した非日常シーンの1つめは、サッカースタジアムだ。J1の試合で通信事業者4社のミリ波性能を測定した。
パナソニックスタジアム吹田では約3.4万人が入った中で(満席率87%)、①フリーWi-Fi、②4G FDD、③5G Sub6(4G+5G)、④5Gミリ波(Sub6+ミリ波)のスループットをそれぞれ計測。④5Gミリ波が圧倒的な数値を叩き出した。試合中の通信速度は下り1Gbps/上り150Mbps、通信が最も混雑するハーフタイム中でも上り100Mbpsを維持した。RTT(ラウンドトリップタイム)も10~180ミリ秒という優秀さで、SNSへのビデオ投稿も十分に可能だ。

パナソニックスタジアム吹田(左)とサンガスタジアム by KYOCERA(右)で実施した通信環境調査の様子。事前に全通信事業者のヒートマップを取得したうえで、ミリ波に接続できる場所を優先に定点観測場所を決定。通信環境の時間変化を観測した
対して、②③はハーフタイムに上り通信が0.5Mbps未満に低下し、RTTが最大9000msまで伸びた通信事業者もあった。満足にインターネット接続もできない状態だ。
ここで重要な点として、本調査に関わった宮下一馬氏は、「アンテナピクトは最大を示しているのに、実質的にはインターネット接続に使えない点に注意すべき」と指摘する。電波強度は十分でも「実際には圏外にいるのと同じ」という状況は、人口密集地では珍しくない。私たちが拠り所としてきたピクト表示は最早、「UXを担保する指標としての役割を果たせなくなっている」と同氏は言う。