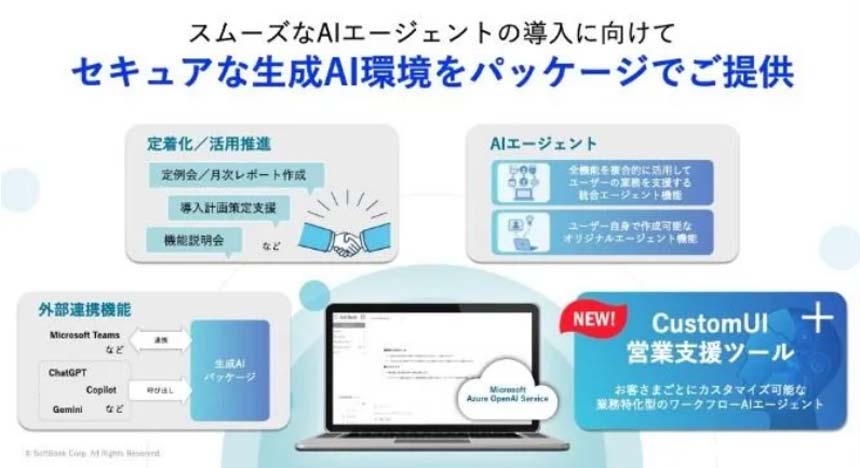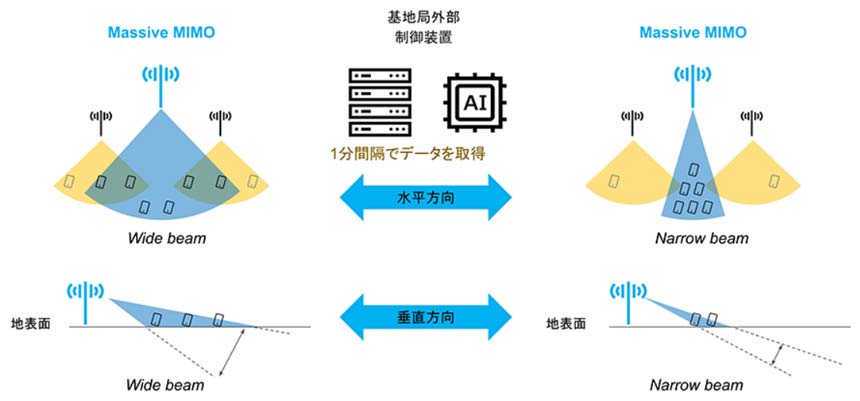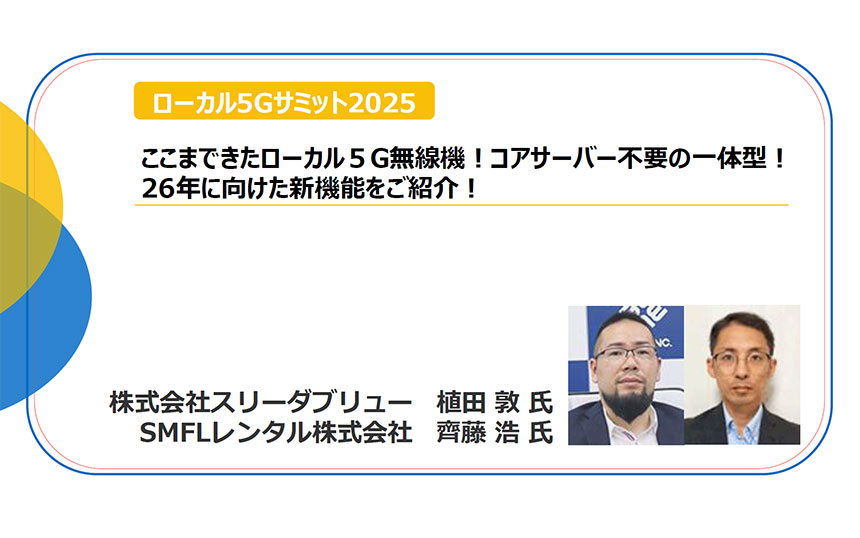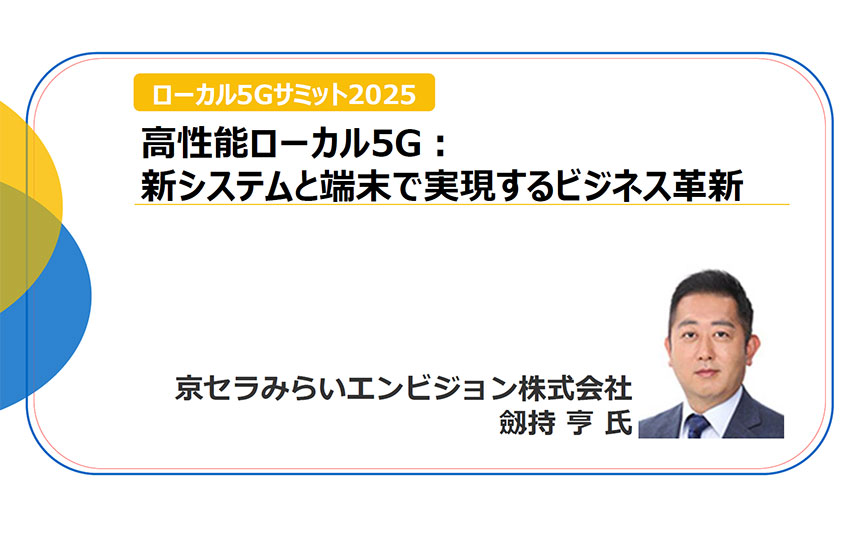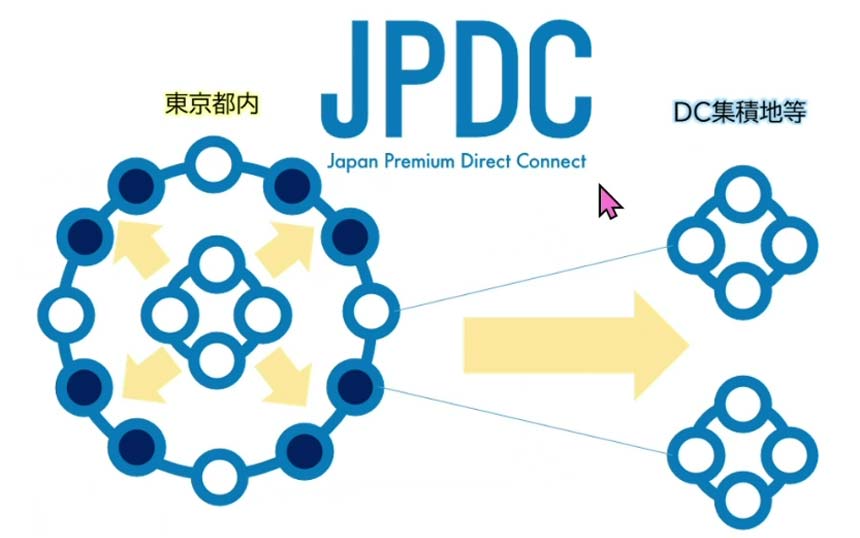衛星通信のビジネス活用が広がっている。その主戦場は、「海上利用」と「災害対応」である。
海上利用では、船舶-陸上間で運航状況などをやり取りするために衛星通信が使われているほか、船内にStarlinkを活用した「フェリーWi-Fi」を構築し、船員が家族とのビデオ通話や動画視聴を行えるようにするなど、ウェルビーイング向上を目的とした取り組みも進んでいる。
昨年1月に発生した能登半島地震では、Starlinkが船舶基地局のバックホール回線として用いられ、被災地におけるネットワークの暫定復旧に貢献した。また、災害対策本部との情報共有やWeb会議を支えるインフラとしても、衛星通信が力を発揮した。
ただ現時点では、「僻地や災害時といった限定的な環境下での活用がほとんどで、それ以外の領域での本格導入はこれからになる」。こう話すのは、XGモバイル推進フォーラム(XGMF)の「宇宙×地上ユースケース検討プロジェクト」でプロジェクトリーダーを務める藤本幸一郎氏だ。そこで同プロジェクトでは、衛星関連事業者に加え、エネルギーや金融などの異業種からもメンバーを募り、衛星通信のさらなるユースケース拡大に向けて議論を行っていくという(図表1)。
図表1 宇宙×地上ユースケース検討プロジェクトの目的・概要
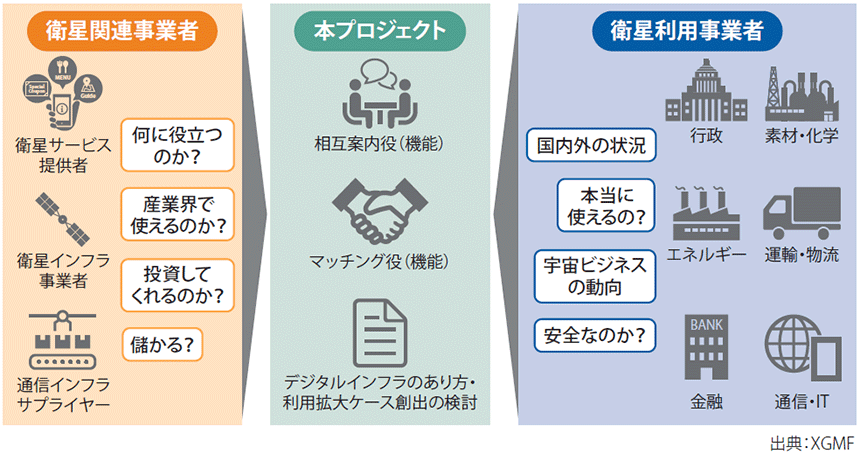
これからの衛星通信は、どう活用されていくのか。これまで同様、ラストリゾート(最後の手段)としての役割が一層期待されるとともに、産業・社会DXを支える社会インフラとしての存在感を高めていくはずだ(図表2)。
図表2 衛星通信の有望なユースケース
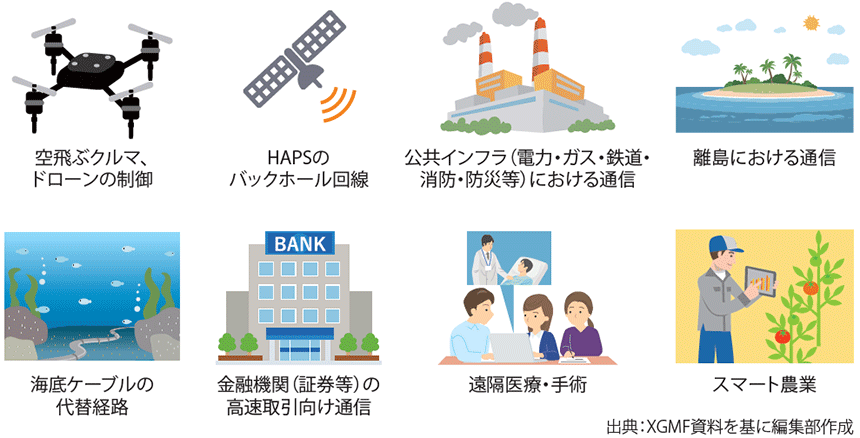
公共インフラ事業者は「平時」に活用
同プロジェクトが有望なユースケースの1つとして挙げるのが、海底ケーブルの代替経路だ。
近年、ヨーロッパ北部や台湾周辺の海域などで海底ケーブルの切断事故が相次いでいる。こうしたリスクに備え、各国は海底ケーブルの冗長化に取り組んでいるが、十分に対応できていない国も少なくない。万が一ケーブルを切られれば、その国は海外との音声・データ通信が途絶してしまう可能性も否定できない。
このような背景から、太平洋諸島をはじめとする島国や、海底ケーブルの整備が難しい地域では、通信の冗長性を確保する手段の1つとして、衛星通信に注目しているという。「衛星通信は物理的に切断されることがないし、海底ケーブルのように国を跨らないので、独立性も高い」(藤本氏)

XGモバイル推進フォーラム(XGMF) 宇宙×地上ユースケース検討プロジェクト プロジェクトリーダー 藤本幸一郎氏
(NEC ナショナルセキュリティ事業部門 衛星コンステレーション統括部 上席事業主幹)
電力をはじめとする公共インフラ事業者も、衛星通信に熱視線を注いでいる。現在は、緊急時のバックアップ用途としての活用が主だが、「平時にも衛星通信を使いたい」というニーズが広がりつつある。
例えば、各地に点在する再エネ発電所の発電・消費量を収集・共有し、需給バランスを適切に制御するためには通信が不可欠だが、発電所はモバイル網の電波が届きにくいエリアにあるケースが多く、光ファイバーの整備にも多大なコストや工数がかかる。「アンテナ1本で通信環境を整備できる」利便性から、衛星通信の導入を検討する事業者が増えているそうだ。