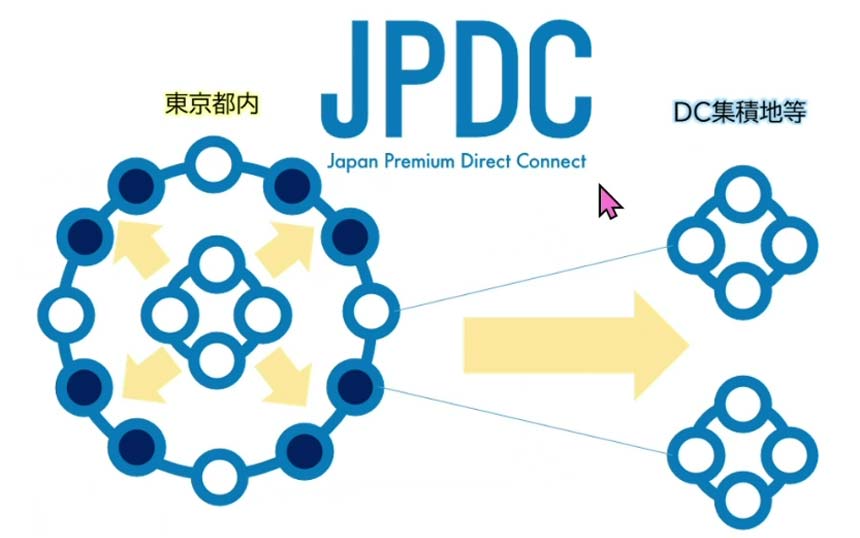「10km・1W以上」という目標はユースケースを想定して設定したものだ。10kmは、アクセス網の一般的なカバー距離。加えて、「最近の省電力なトランシーバーなら10Gbps程度の伝送ができる」1Wにこだわったと、NTTアクセスサービスシステム研究所の中島和秀氏は話す。
図表1は、これまでの光ファイバー給電の実験例の成果を示したものだ。マルチモード(図中の■)を使えば大電力が供給可能だが、伝送距離はせいぜい数百m。対して、長距離用のシングルモード(同●)では1W以上に届かなかった。この壁を初めて打破したのが、マルチコアというわけだ。4コアファイバーを使用して各コアを通信用と給電用に、あるいは双方に割り当てられるシステムを開発し、14km伝送後に約1Wの電力が得られた。
図表1 光ファイバを用いた自己給電光伝送の実験例における、供給電力と伝送距離の関係
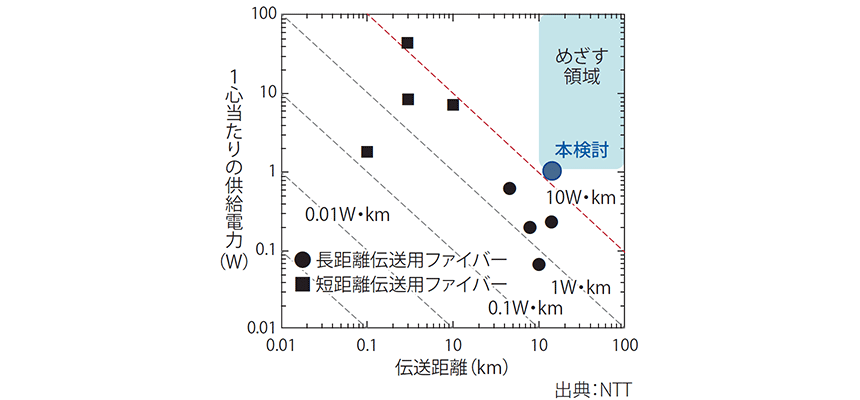
上り/下りで2コアずつのシステムを構成し、自己給電による10Gbpsの双方向通信にも成功している。
災害時の通信確保から
活用領域は、大きく3つを想定しているという(図表2)。災害時に電源を喪失した通信機への電力供給、山間部や僻地のように電源が確保できない場所で使われるIoT/通信機器への給電、そして電磁誘導の懸念から電気が使えないような特殊環境だ。
図表2 光給電の適用領域
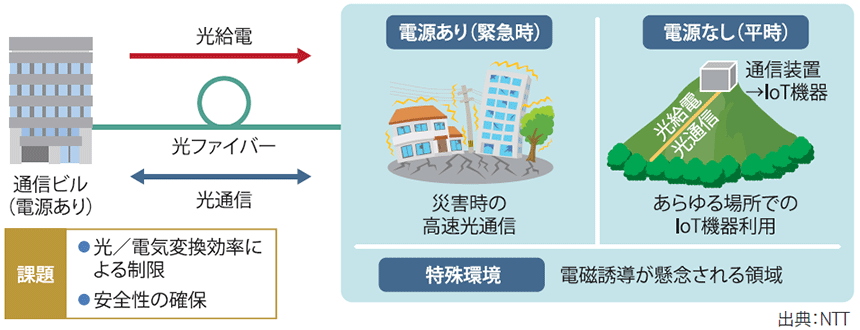
ただし、光ファイバー給電の実用化には大きく2つの課題があるという。
1つが、光から電気への変換効率だ。「現状では30%程度。この変換効率を勘案してでもメリットが得られる領域に用途が制限される」(中島氏)。2次電池の併用も考慮しながらアプリケーションを開発していく考えだ。
もう1つの課題は、安全性の確保である。非常に強い光エネルギーを転送するため、万一、ケーブルが切断された場合に漏れた光が目に入ると失明の危険性がある。一般的な通信用ファイバーでは、切断を検知すると自動的に光源側で出力を停止することで安全性を確保している。この仕組みを光給電にも適用できるが、その分、コストが高くなるのが悩みどころだ。
こうした課題を考慮すると、やはり、災害等の非常時に通信機能を確保するという用途が、最初の適用先として有望と言えそうだ。
非電化エリアや電化困難エリアを含めて、あらゆる場所に光通信を提供できる光ファイバー給電の実用化に向けて、さらなる改善を進めていく。