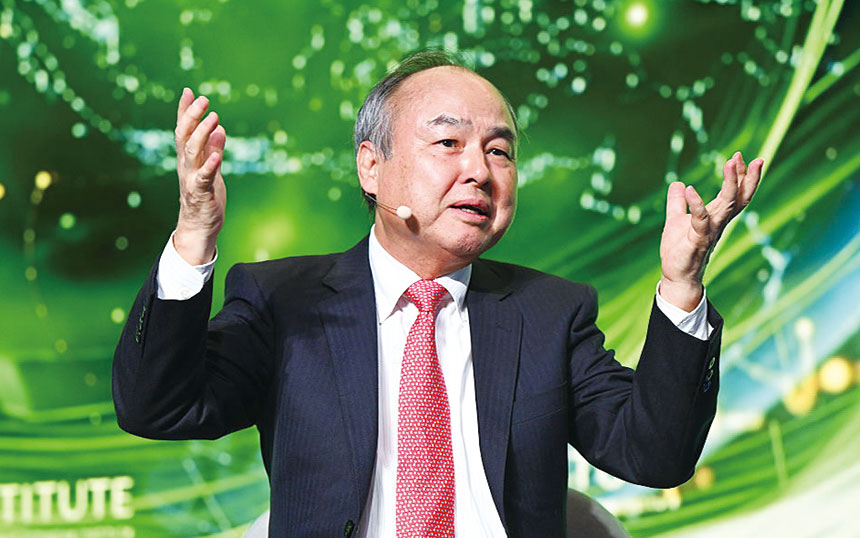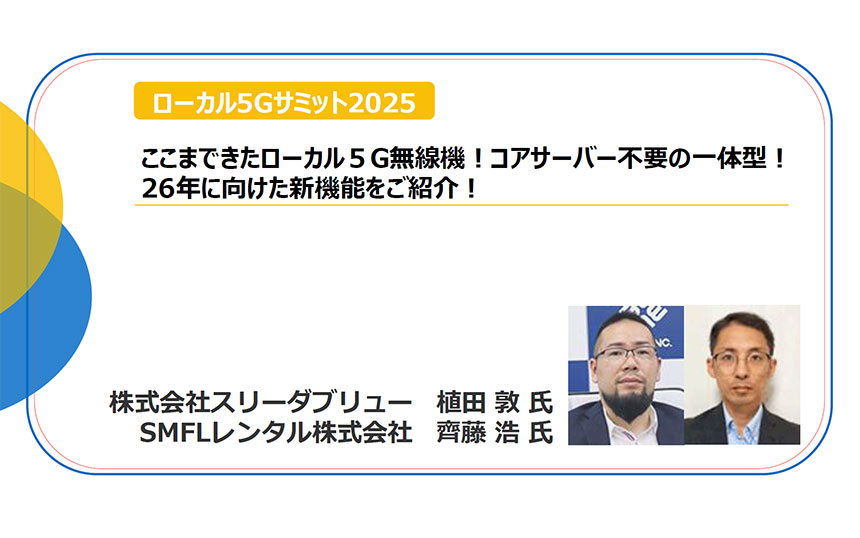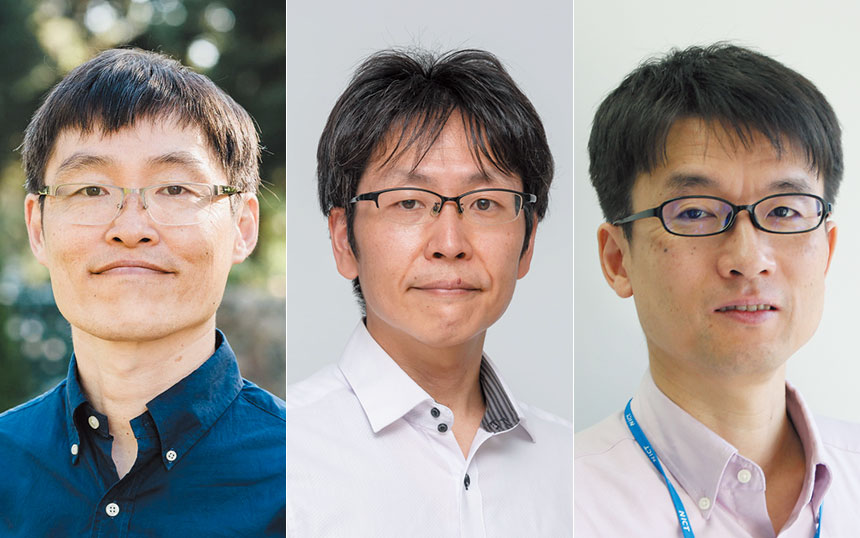DC連携・統合に複数の狙い
分散DCの連携は、“巨大なAIファクトリー”だけが目的ではない。利用効率の向上にも貢献する。図表2は、その一例を示したものだ。
図表2 拠点をまたいだタスクの再配置
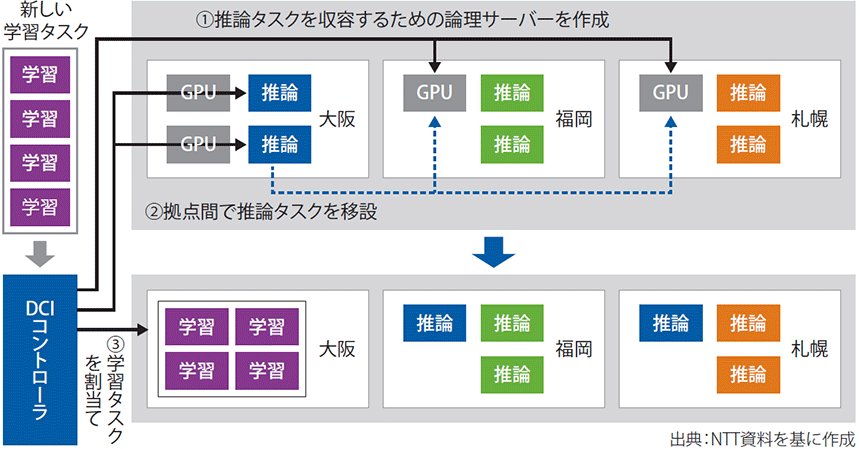
NTTはIOWNの要素技術であるData-Centric Infrastructure(DCI)において、複数DCをワークロードに応じて使い分け、データ処理や電力消費を効率化することを目指している。図のように、大量のGPUリソースを使うAI学習タスクを実行するために、DCIコントローラーが複数DCのリソース使用状況を把握したうえで、大阪DCのタスクを空きリソースのある福岡・札幌DCへ移行すれば、待ち時間なくすべてのタスクを進められる。全体の稼働率も高めることができる。
また、ある拠点で電力供給が逼迫した際にも、他の拠点にタスクを移せば処理を継続できる。
処理内容によって拠点を使い分けることもできよう。DCを分散させると、需要の大きい東京・大阪から離れるほど通信遅延の増大が課題となるが、山本氏は、「AIの大規模学習のような遅延が問題とならない処理に特化すれば、北海道や九州のような再生可能エネルギーを使える場所にも価値が出てくる」と述べる。
脱炭素化に加えて、地価やエネルギー費の安さも活かせる。三菱総合研究所(MRI) 電力・エネルギー本部電力システムイノベーショングループチーフ事業マネージャーの石田裕之氏は、「太陽光発電が多い九州の昼間は、卸電力価格が0.01円/kWhまで下がることがある。この非常に安い電力はDC事業者に地方分散を促すためのインセンティブになる」と話す。需要がなければ、せっかく発電した再エネを捨ててしまう(出力抑制)ことになるため、地方分散したDCで活用できれば「社会的なメリットも生まれる」。
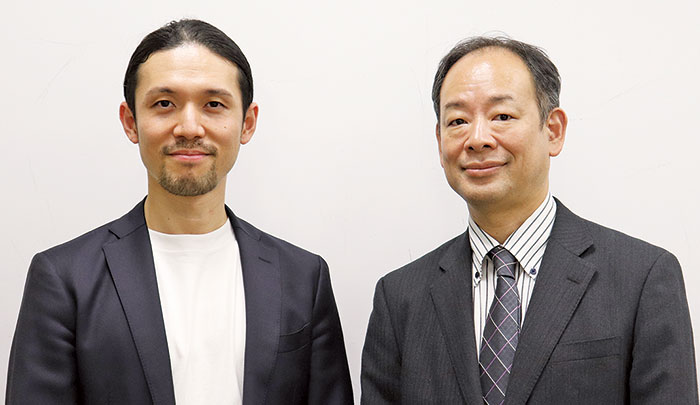
三菱総合研究所 政策・経済センター フェロー(研究提言担当)西角直樹氏(右)
電力・エネルギー本部 電力システムイノベーショングループ チーフ事業マネージャー 石田裕之氏(左)
通信・電力業界の仲介者求む
日本政府は東京・大阪に次ぐDC集積拠点の第3極として、再エネが豊富な北海道や九州を想定。その後、全国へさらなる地方分散を進める戦略を打ち出している。
新たな集積拠点を形成する第1段階においては、「ハイパースケーラーも含めて誘致できるよう、彼らにとって魅力ある拠点を複数形成することが最優先」と語るのは、MRI 政策・経済センター フェロー(研究提言担当)の西角直樹氏だ。再エネ活用・脱炭素はその一要素となり得る。
MRIの分析によれば、DC集積地を東京・大阪・北海道・東北・九州の5エリアに分散させることで、東阪に集中する場合と比較して再エネ出力抑制量が減少し、化石燃料消費量とCO2対策コストが年間約650億円削減されるという。課題となるのは、やはり通信遅延だ。西角氏も「リアルタイム性があまり要求されないAI学習のようなバッチ処理を地方に移すことが合理的な入口になる」と話す。
ただし、ここで留まっていてはDC分散化の効果は限定的だ。「将来的には、細かい時間単位で計算負荷を柔軟に移動させるワークロードシフト(WLS)が鍵になる」と同氏。これを実現するための新たな技術開発、そしてモデル作りの必要性を強調する(図表3)。
図表3 ワークロードシフト(WLS)実現に向けた環境整備
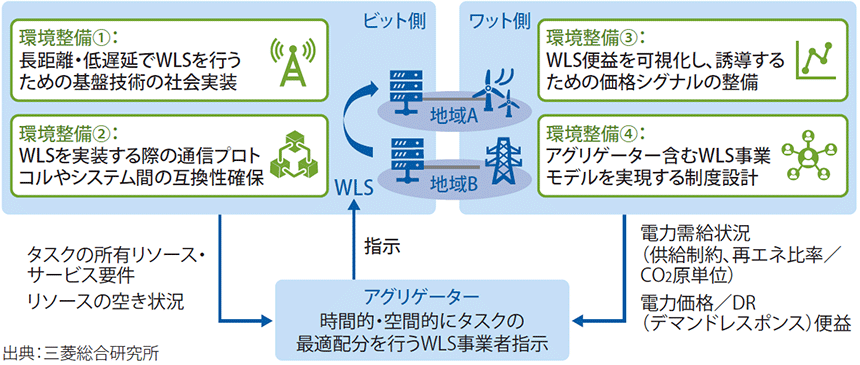
ビット側(通信業界)で必要な取り組みとしては、長距離・低遅延でWLSを行うための通信技術や、通信プロトコル/システムの互換性確保等が挙げられる。ワット側(電力業界)でも、WLSを実装するための制度設計、価格シグナルの整備が求められるほか、通信業界と電力業界の利害関係を調整しつつWLSの運用を担うアグリゲーターを含めた事業モデルの設計が必要とMRIは提言する。石田氏は「再エネを絡めた需給調整をうまく行う技術が重要だ」と指摘。世界に先駆けてこのモデルが確立できれば、「日本の競争力につながる可能性もある」。