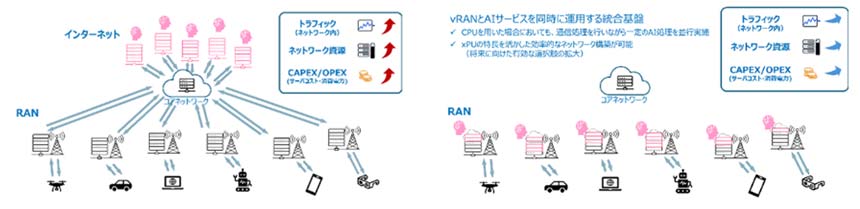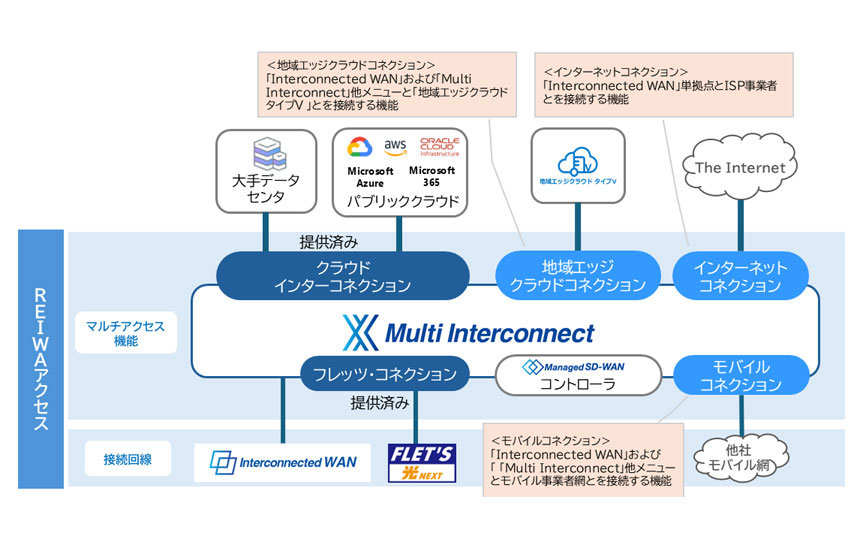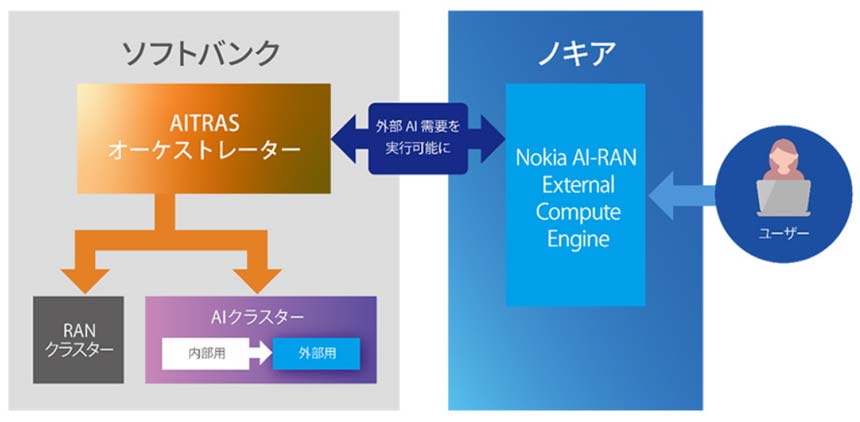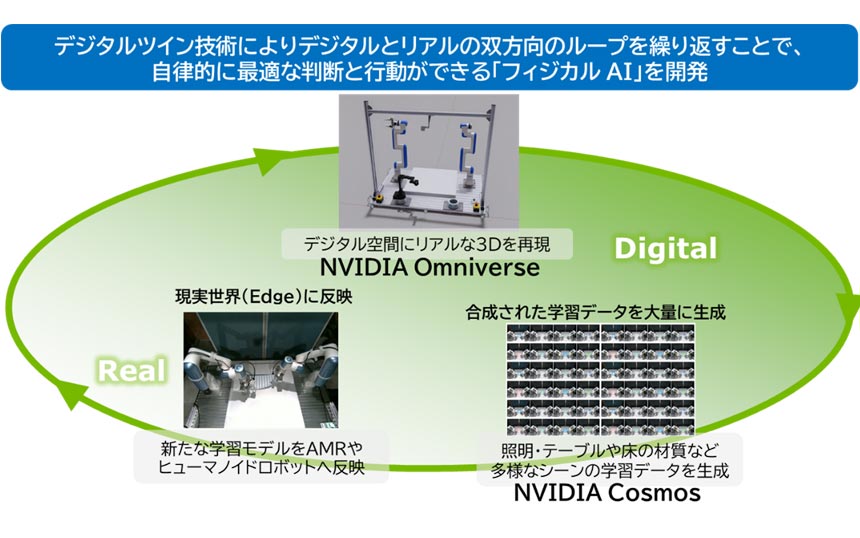2014年、楽天モバイルやIIJmio、mineoといったコンシューマー向けMVNOの台頭により、「格安スマホ」というキャッチーな呼称とともに、MVNO市場は急成長を遂げた。
しかし、当社の調査結果では、2019年に13.2%だったMVNOのシェアは緩やかな減少傾向をたどり、2025年には9.1%となった(図表1)。この背景には、2020年以降の市場環境の劇的な変化が影響している。
図表1 6年間のシェア推移
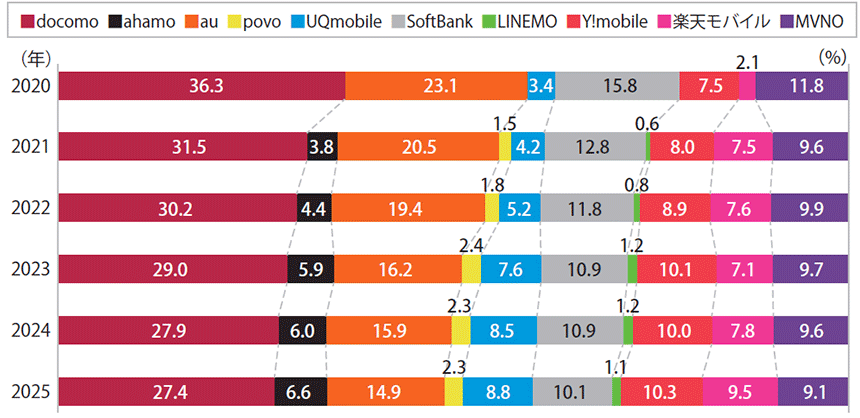
まず、2020年4月に楽天モバイルがMNOとして正式に参入し、MVNOとしての新規契約受付を終了。さらに同年10月には、UQモバイルがKDDIに統合され、MNOのサブブランドへと移行した。MVNO市場を牽引していた2大プレイヤーが、MNO側に移行した格好だ。
加えて、同年には菅義偉首相(当時)が「携帯料金の引き下げ」を政権の重点施策に掲げ、NTTドコモの「ahamo」など、MNOによるオンライン専用プランが登場。これにより、“格安”市場において、MVNOとMNOの競争が一気に激化した(図表2)。
図表2 3キャリア本ブランドvs格安ブランド
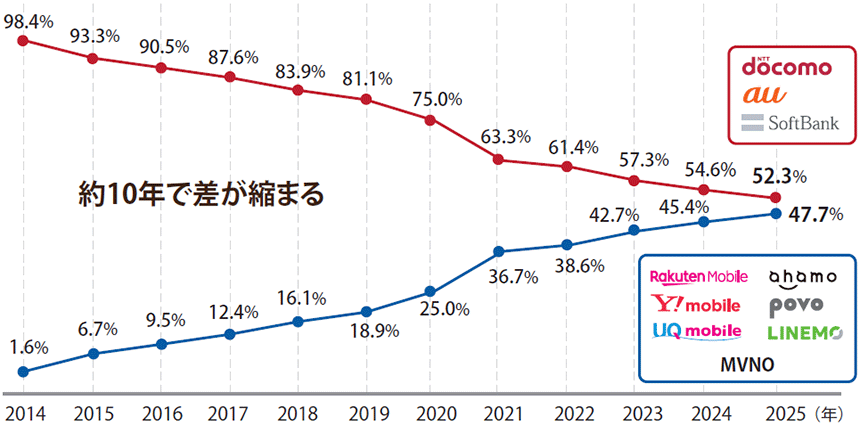
その結果、MNOのサブブランドやオンライン専用ブランドなどのシェアは拡大した一方、MVNO各社のシェアは頭打ちとなった。こうした状況を受け、現在のMVNOはIoTサービスや法人向けソリューション、eSIMといった分野に活路を見出しつつある。
異業種参入が進む3つのワケ
MVNO市場の黎明期においては、ISPや家電量販店など、通信に関連性を持つ業界からの参入が主だった。しかし近年では、JALやメルカリ、カブ&ピースなど、通信とは無縁だった業界からの参入が加速している。
その背景には、3つの要因が挙げられる。1つめは、格安通信サービスが広く普及し、ブランド戦略や販路の一環として“通信サービス”が一定の市民権を獲得したこと。2つめは、物価高騰を背景に、消費者の節約志向が高まり、通信費削減ニーズが顕在化していること。3つめは、MVNE(仮想移動体サービス提供者)による技術・運営支援体制の進化により、異業種でも参入が容易になったことだ。
これらの土壌変化により、MVNOは単なる通信回線提供ではなく、クロスユース(他サービスとの併用)や自社経済圏の拡張を実現する戦略的ツールとして活用されるようになっている。
例えば、メルカリモバイルでは、ユーザー同士で余ったデータ通信量(ギガ)を売買できる機能を搭載。通信費の節約と同時に、自社エコシステム内でのユーザー接点を強化している。JALモバイルは、マイレージプログラムとの連動を通じて、既存会員のロイヤルティを高める仕組みを導入。通信は今や、CRM(顧客関係管理)の接点として再定義されつつある。