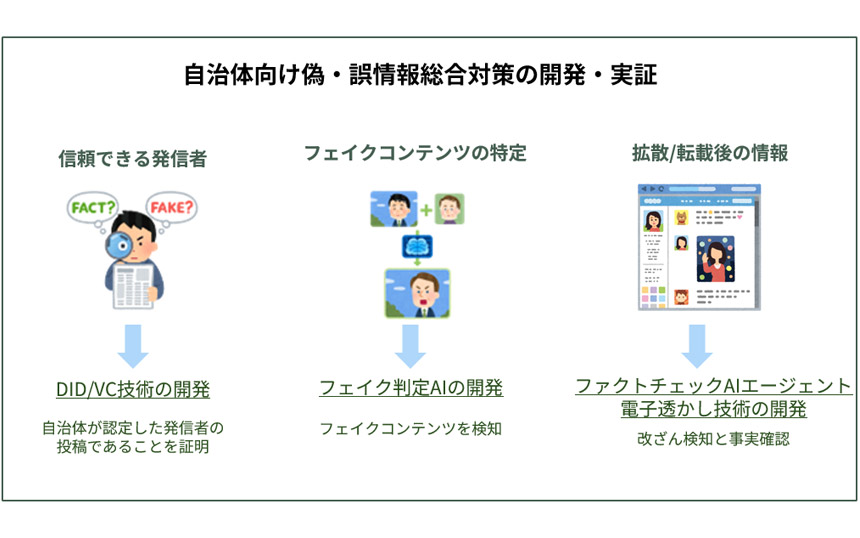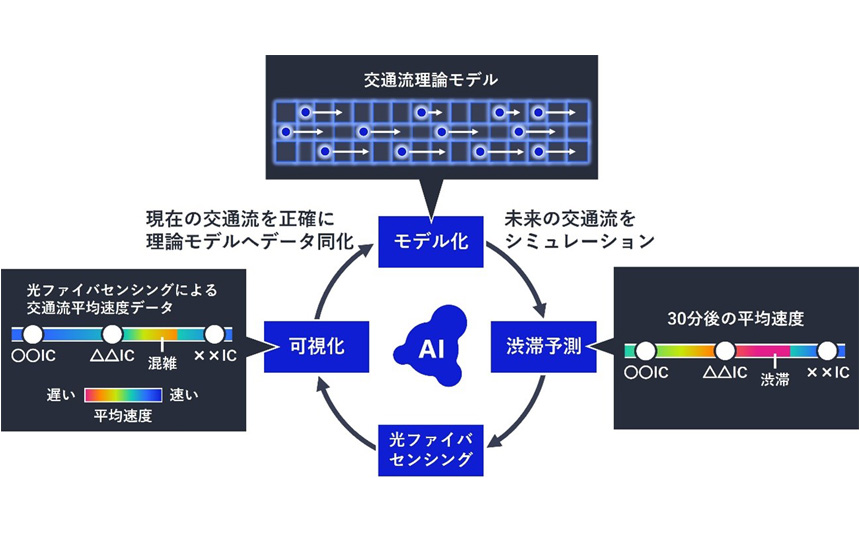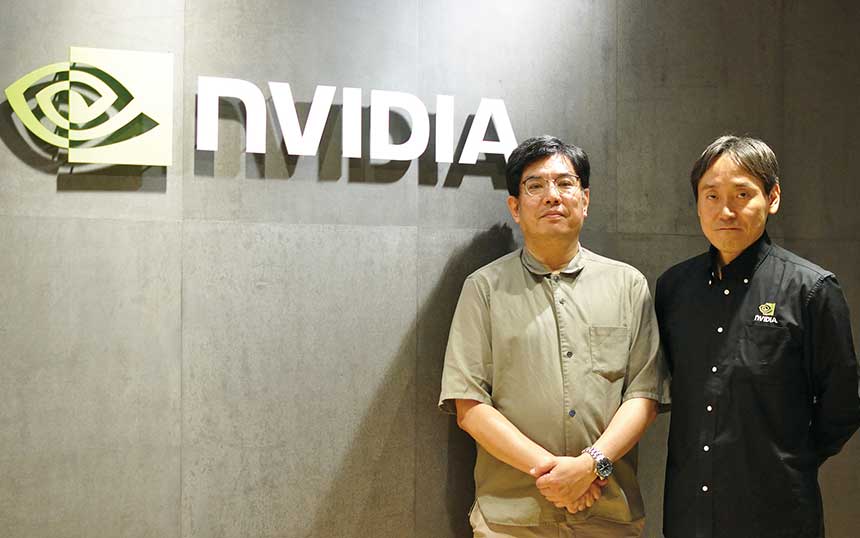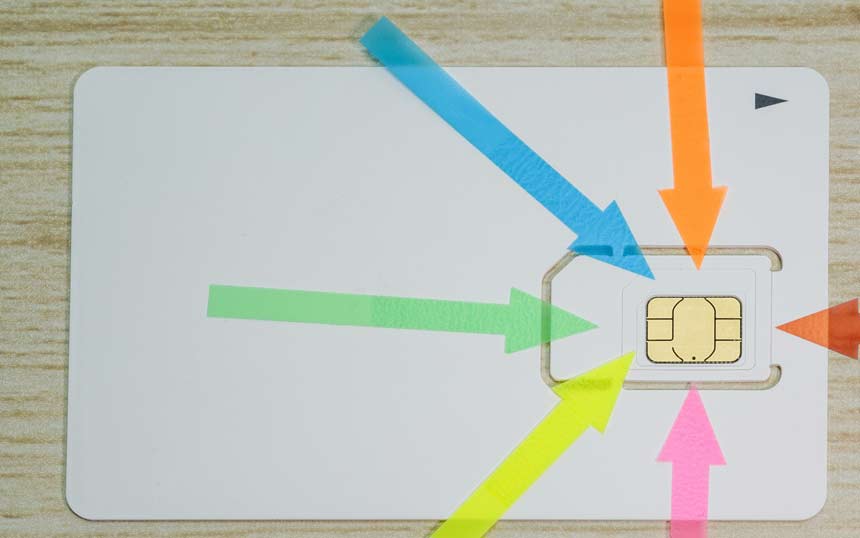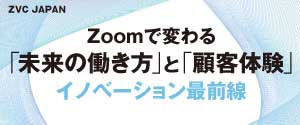分散アンテナに衛星アンテナも
もう1つ、6G時代のRANの要素として欠かせないのが、分散MIMOだ。
大容量伝送が可能なミリ波を本格的に活用するには、遮蔽物に弱いという難点を克服する必要がある。
高周波数帯を活用するための策は唯1つ。基地局と端末間で見通しを確保することだ。分散MIMOは、図表3のように分散アンテナを使って見通しをカバーする。アンテナ数を増やして、複数端末へマルチユーザー伝送を行うことで大容量伝送を行うこともできる。
図表3 高周波数帯分散アンテナシステムの特徴
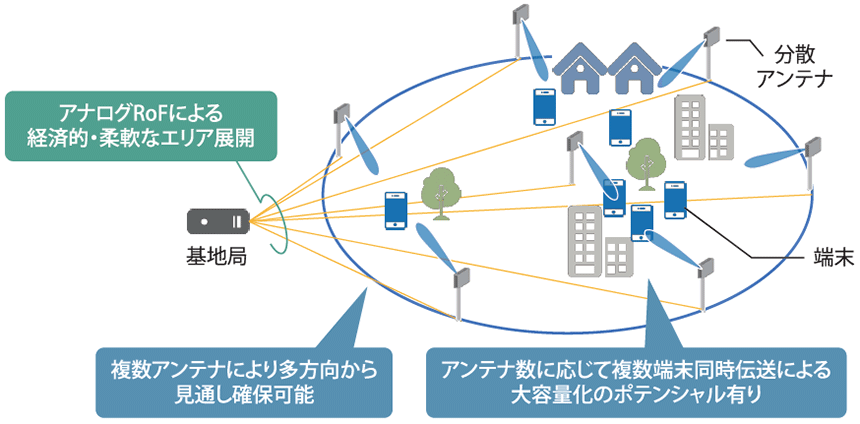
実現への課題は、数多く設置する分散アンテナの展開コストを抑えることが1つ。分散MIMOの研究を進めるNTTやNECらは、電波信号をデジタル変換せずアナログのまま光ファイバーで伝送するアナログRoF(Radioover Fiber)により、経済的な展開を可能にしようとしている。
もう1つの課題は、高速移動する端末との接続をいかに維持するかだ。分散MIMOを実現するには、端末の移動に応じて適切なアンテナとビームを選んで使い分ける必要があるが、分散MIMOの適用エリアを広げると、計算量が膨大になる。
NTTとNECは、分散アンテナ間で協調して送受信タイミング等を補正する新技術を開発し、この課題に対処しようとしている。計算量を増やさずにアンテナを切り替えることで、時速100kmで走行する車両でも、100Mbpsのスループットを維持する実験に成功した。
実用化されれば、分散MIMOの適用領域が広がり、自動運転バスや鉄道などの移動サービスにもミリ波が使える可能性が出てくる。
6G時代には、こうした地上系RANの進化と合わせて、NTNとの連携という新要素も加わる。
現在は、Starlinkなどの衛星通信サービスで独自方式によるスマートフォンとの直接通信が始まっているが、5G-Advancedでは、5G端末と通信衛星やHAPS等との接続を仕様化する「5G NTN」の標準化と拡張が進んでいる。目指すのは、地上網とNTNのシームレスな連携であり、ゆくゆくは“空を飛ぶ基地局”も6G RANの一部となろう。2030年代には、地上基地局と衛星を意識せずに使い分けるのが当たり前になっているかもしれない。