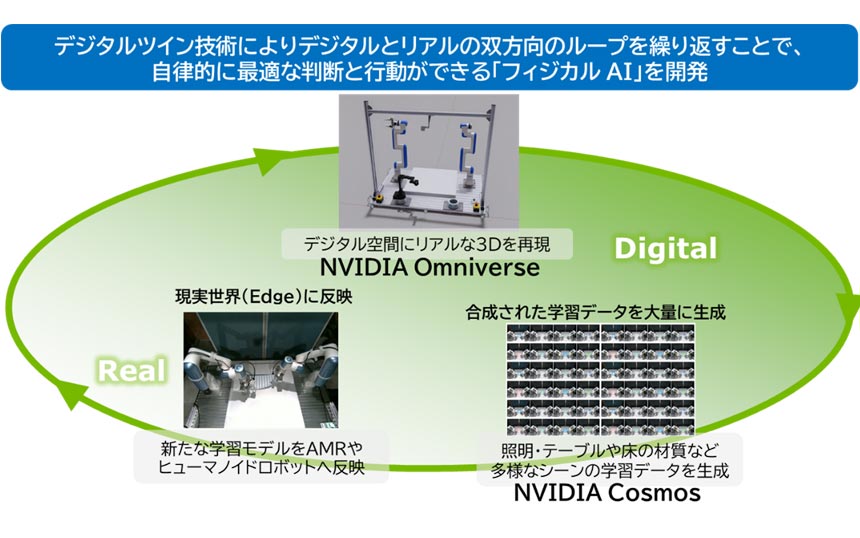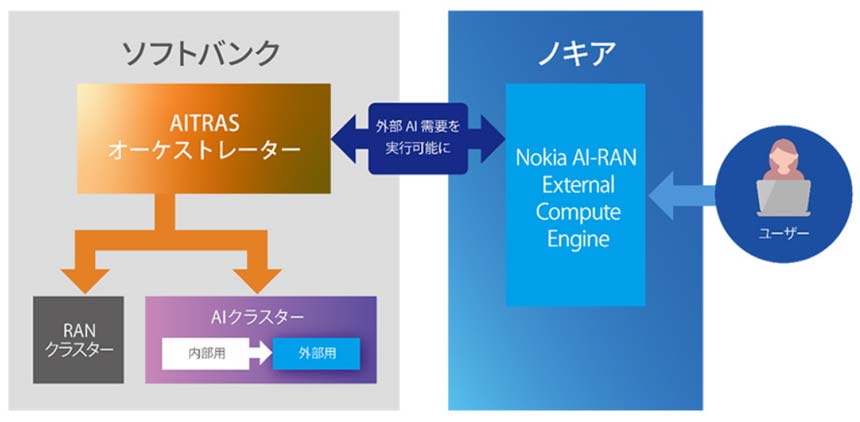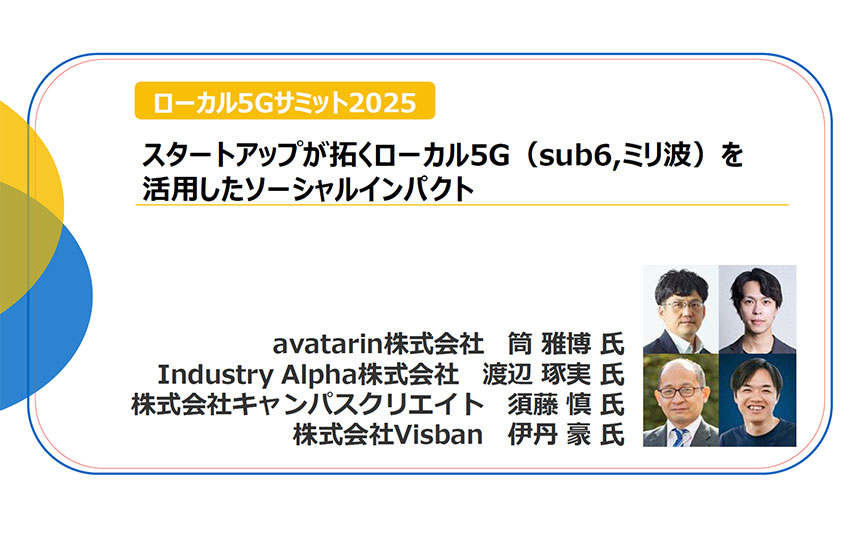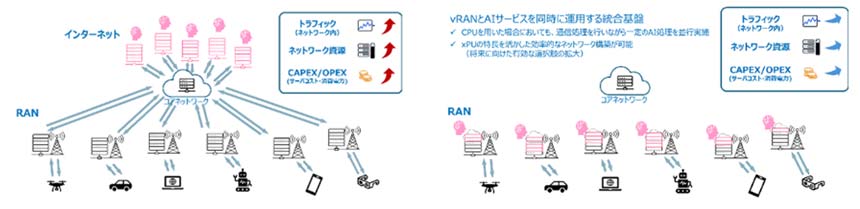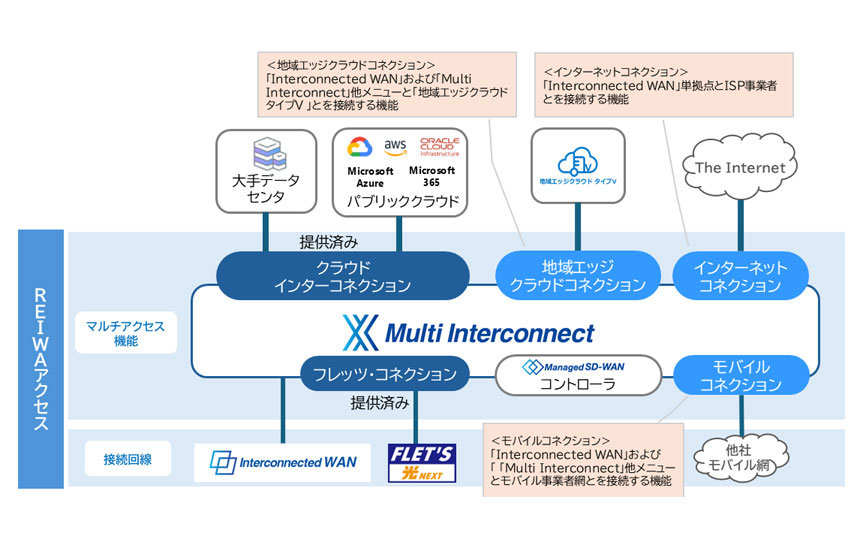6Gの無線性能は、5Gのそれを一段と高めたものになる。世界各国の通信事業者はそれぞれのビジョンの中で、最大通信速度100Gbps、エンドツーエンド遅延が1ミリ秒以下、1平方km当たり1000万デバイスの同時多数接続といった高い目標を掲げている。具体的な数値目標は今後、3GPPの標準化を経て見えてくるだろう。
そして、5Gと比較しやすいこうした性能アップの他にも、6G RAN(無線アクセスネットワーク)には新たな進化の方向性がある。経済性のさらなる追求やカバレッジ拡張、AIによる高度化だ。5Gの開始時には存在しなかったNTN(非地上系ネットワーク)やAIを新要素として取り込むことで、RANの構成やアーキテクチャは大きく変貌していく。
5Gと6Gで周波数をシェア
6G RANはどのような形になるのか。
現在、最も議論が過熱しているのが、5Gから6Gへの移行形態だ。移行コストをいかに下げるかが焦点となる。
キーポイントは、周波数のマイグレーションである。6Gでは新たな周波数の追加が検討されているものの、もちろんそれだけでは足りない。Part2で述べたように、6Gコアに6G RANと5G RANを収容する「6G SA」でのスタートを実現するには、既存の5G周波数を6Gとシェアする仕組みが欠かせない。既存の5G設備への追加投資をなるべく抑えて、これを実現する必要がある。
その解決策として考えられているのが、Multi-RAT spectrum sharing(MRSS)だ。図表1は、クアルコムが提案している方法を示したものである。
図表1 6Gへのマイグレーション:6G SAを優先
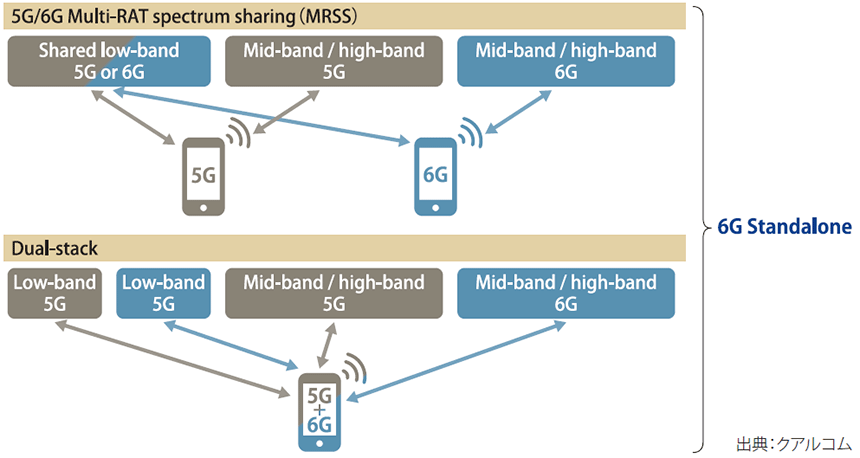
ローバンド基地局が5G信号と6G信号を出すことで、つながりやすい1GHz以下の周波数をアンカーとして使って6Gの信頼性を高められるのが第1の利点だ。かつ、既存の5G帯域を使って6Gを効率的に展開したり、6Gの新周波数と5G帯域をアグリゲーションして大容量化するといったアプローチが可能になる。
このMRSSは、エリクソンやノキアも5Gから6Gへのスムーズな移行を実現するキー技術と位置づけている。エリクソンのパトリック・ルゲランド氏は「6Gが5Gと連携するためにはMRSSが不可欠な要素」とその重要性を強調している。
ただし、クアルコムジャパン シニアディレクターの北添正人氏によれば、このMRSSは、5Gと6GのRANが相互連携する複雑な仕組みとなるため、「すべての基地局、エリアで使えるとは考えにくい」という。
そのため、同社はもう1つのソリューションを提案している。
北添氏がワイヤレスジャパン×WTP 2025で紹介したのが、図表1の下にあるDual Stackだ。簡単に言えば、5Gと6Gのどちらにも接続可能な機能を端末が持つことで、5G-6G RAN間の調整を不要にする。既存ネットワークへの影響は最小限に抑えつつ、5Gと6Gを組み合わせた大容量通信も可能になるという。