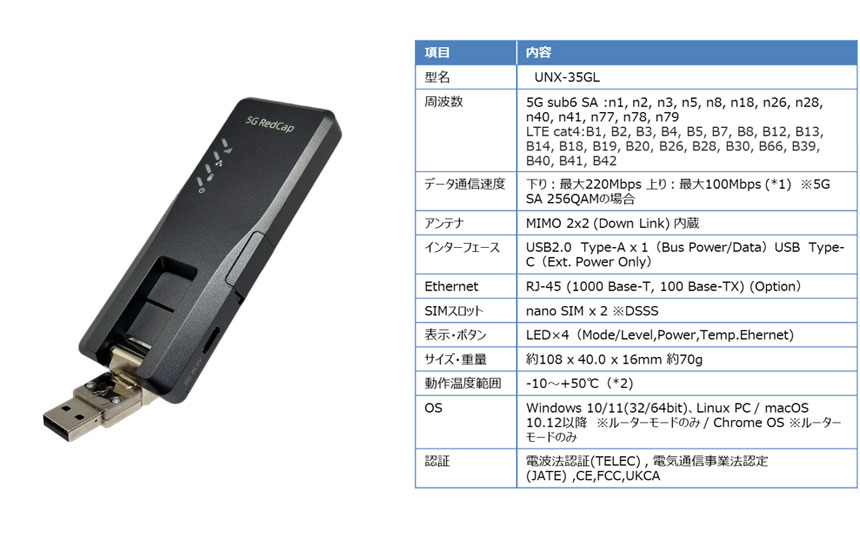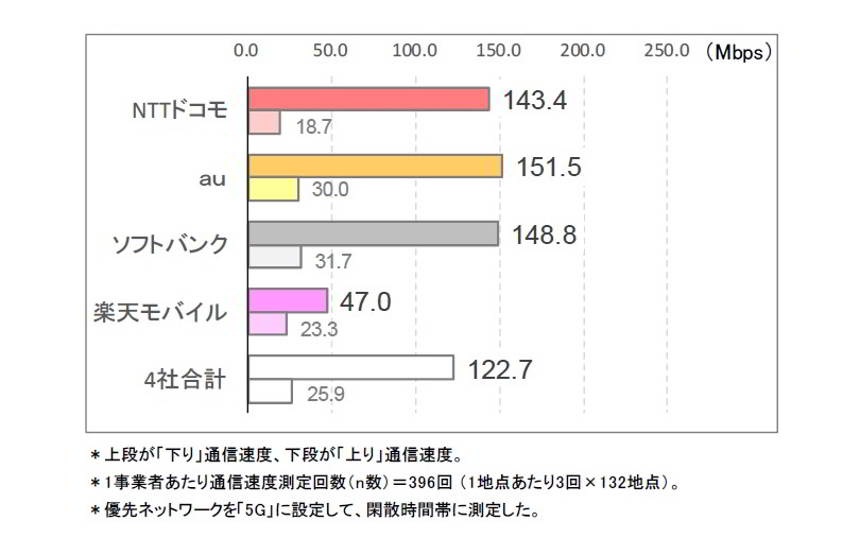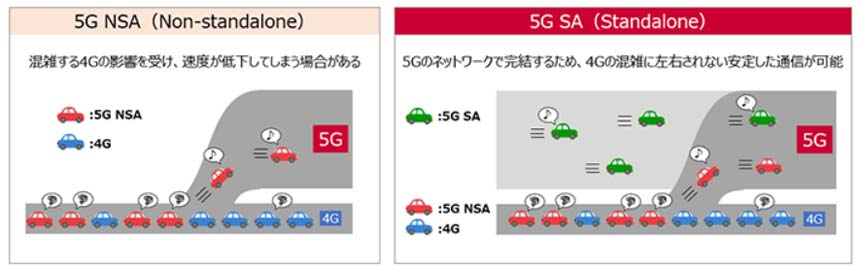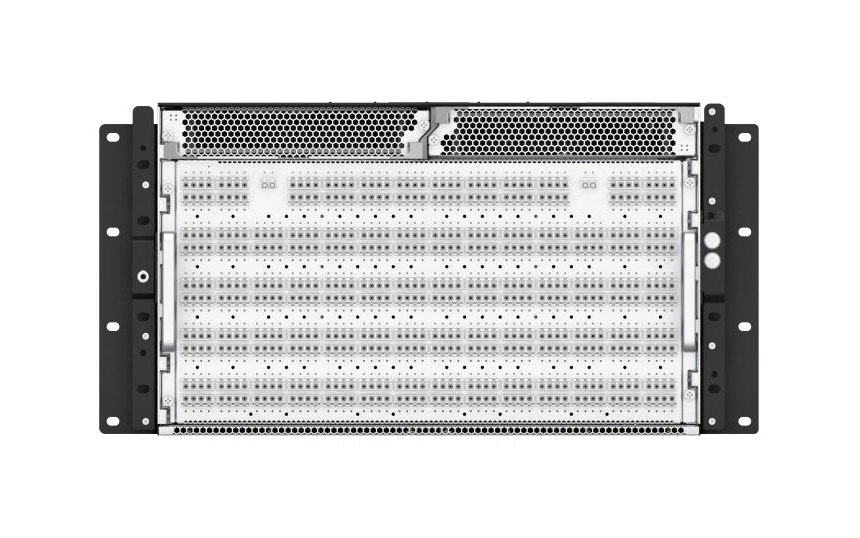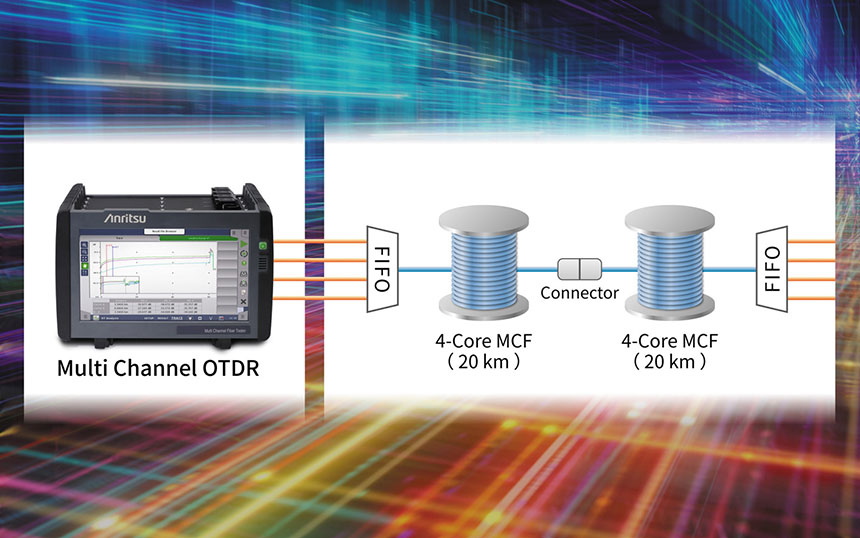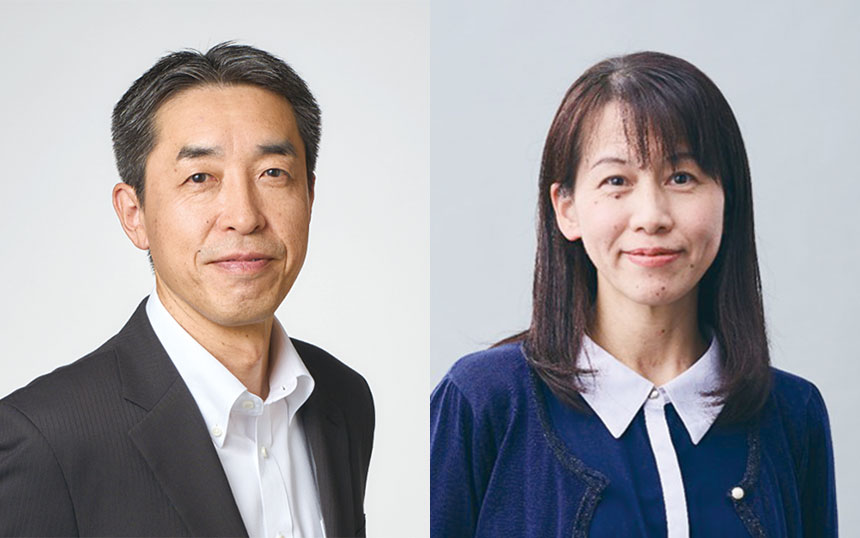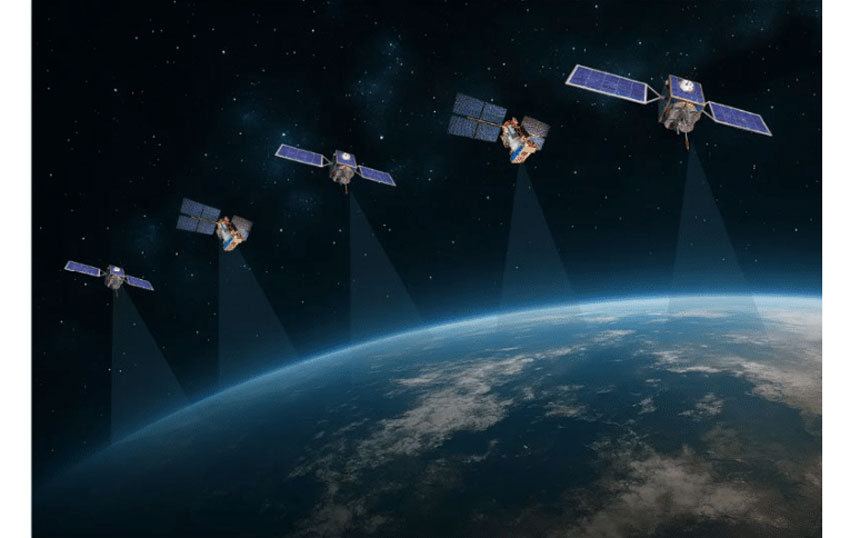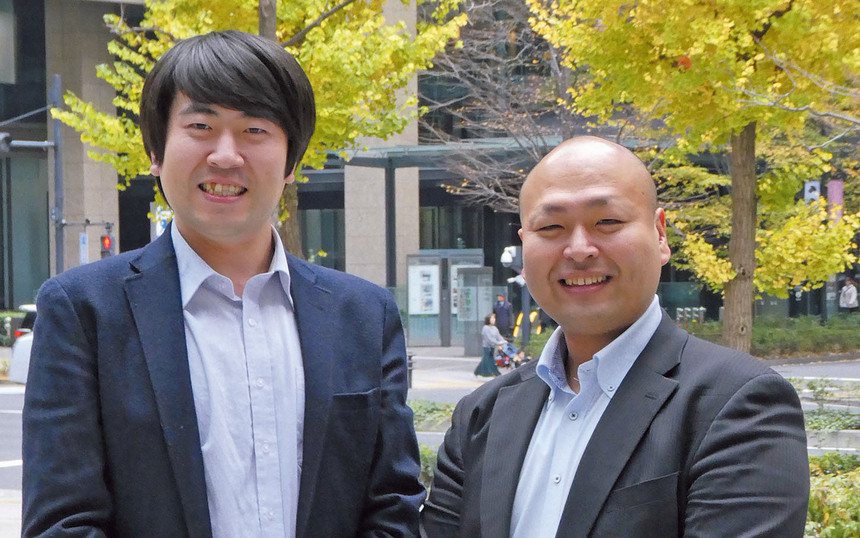――CanonicalはUbuntuの開発および商用サポートを提供していますが、通信業界での実績を教えて下さい。
フェイブル CanonicalとUbuntuには通信業界における長い歴史があります。ティア1の通信事業者の多くがUbuntuを採用しており、我々の商用サポートを利用して通信インフラを構築しています。
公開できるだけでも、ドイツテレコム、AT&T、ベライゾン、NTTドコモ、テルストラ、ボーダフォン、テレフォニカがUbuntuを使っています。
NFV基盤に広がるUbuntu――どのように利用しているのですか。
フェイブル 代表的なのが、モバイルコアのNFVI(Network Functions Virtualization Infrastructure:仮想ネットワークインフラ)です。LTEネットワークのNFV化に当たって、その構成要素であるVIM(Virtual Infrastructure Manager:オーケストレーターであるNFV MANOの内部でNFVIを制御するコンポーネント)に採用されています。通信事業者がUbuntuとOpenStack、Canonicalの商用サポートを活用してNFVプラットフォームを構築する場合もあれば、我々のパートナーのソリューションを用いてN FVを構築しているケースも少なくありません。
例えば、エリクソンのVIMソリューション「Cloud Execution Environment(CEE)」もUbuntuをベースとしています。日本でも、NTTドコモがNFVにこれを採用していますね。
――コアネットワーク以外の用途もありますか。
フェイブル ネットワークエッジのVirtual Radio Access Network(vRAN)でも使われています。
――最近では、基地局のベースバンドユニット(BBU)を仮想化しようとする動きもありますが、そこでもUbuntuを使う考えは。
フェイブル そこはまだ議論している最中です。将来的にBBUをオープン化し、ホワイトボックスハードウェア上でワークロードが動くようになれば、そこでUbuntuを使う可能性はあるでしょう。