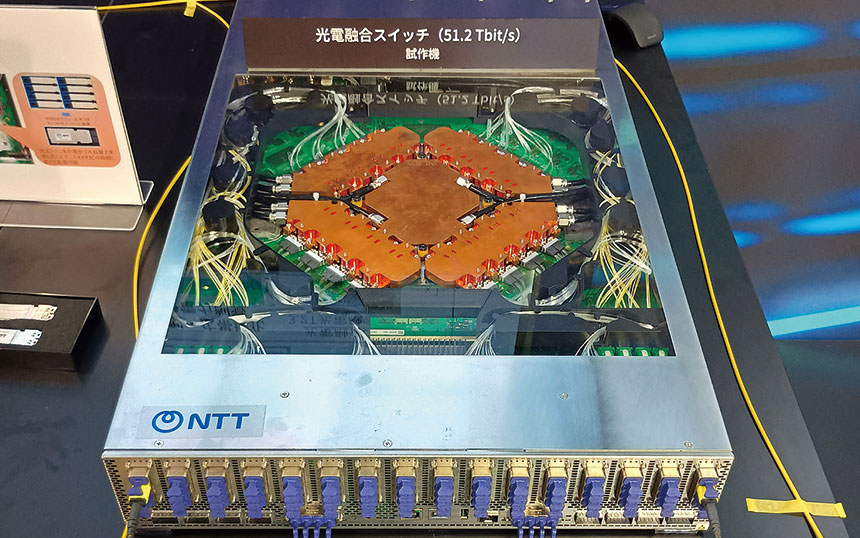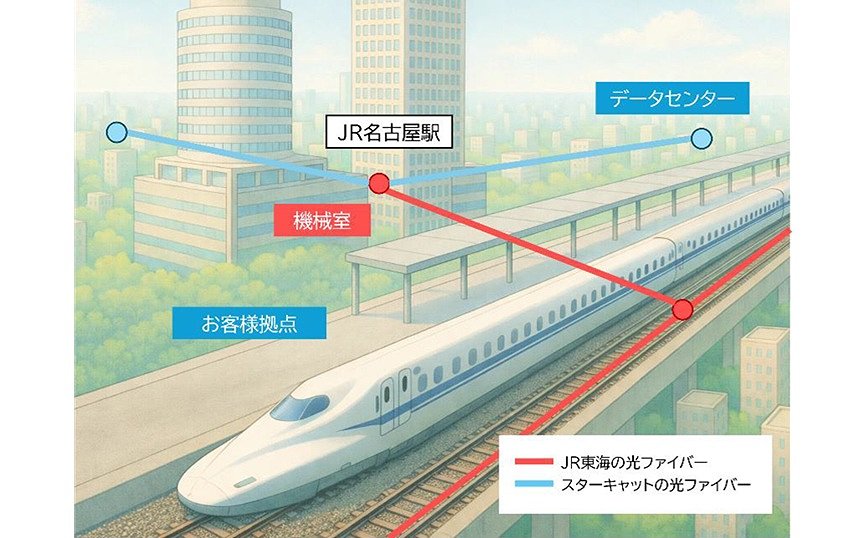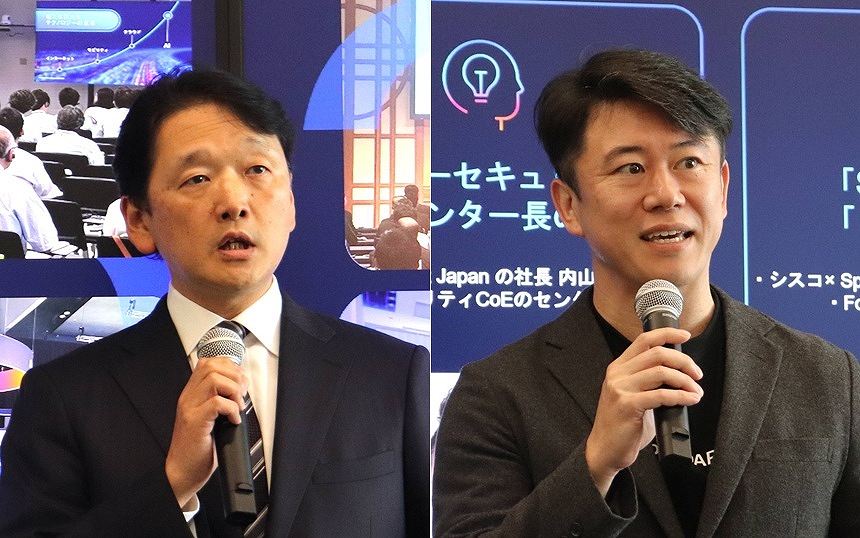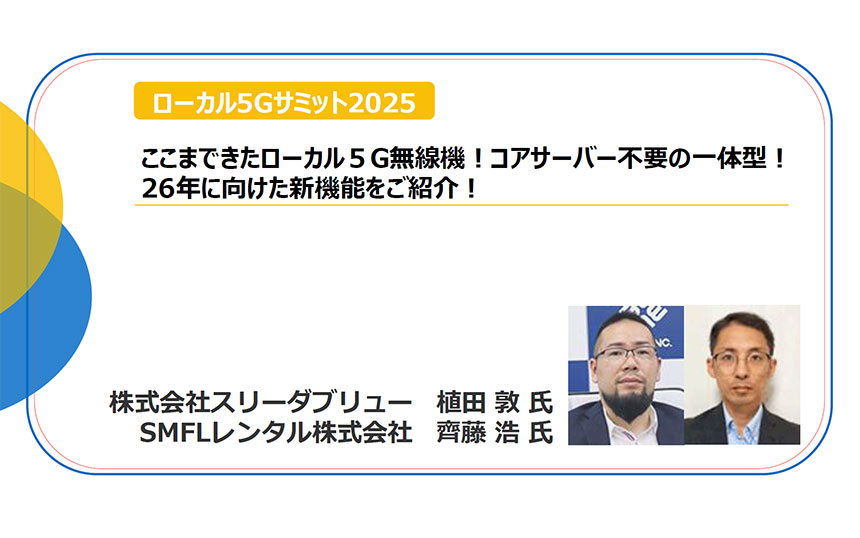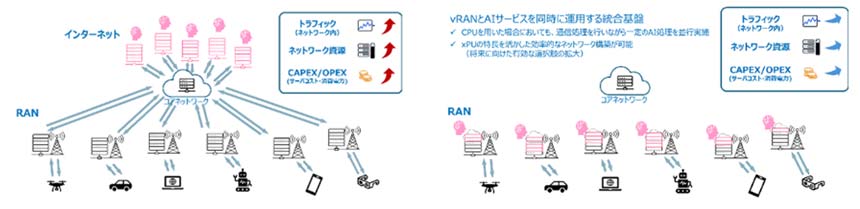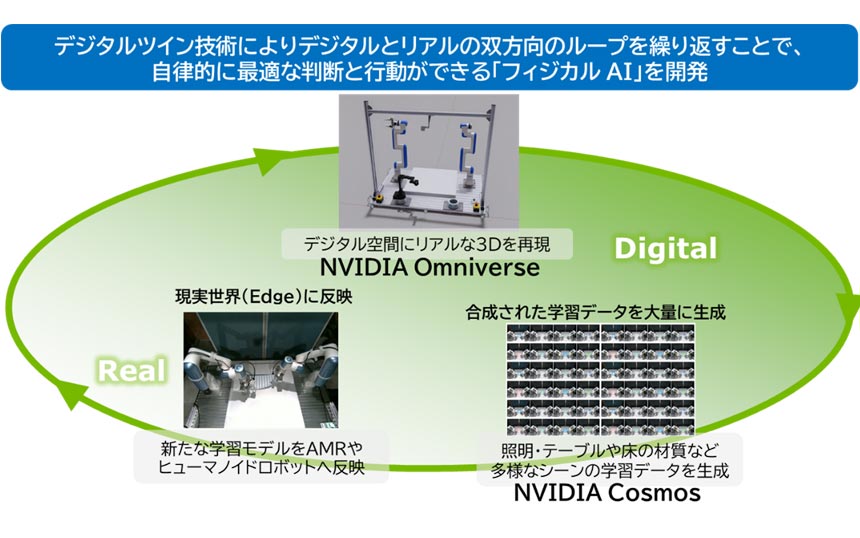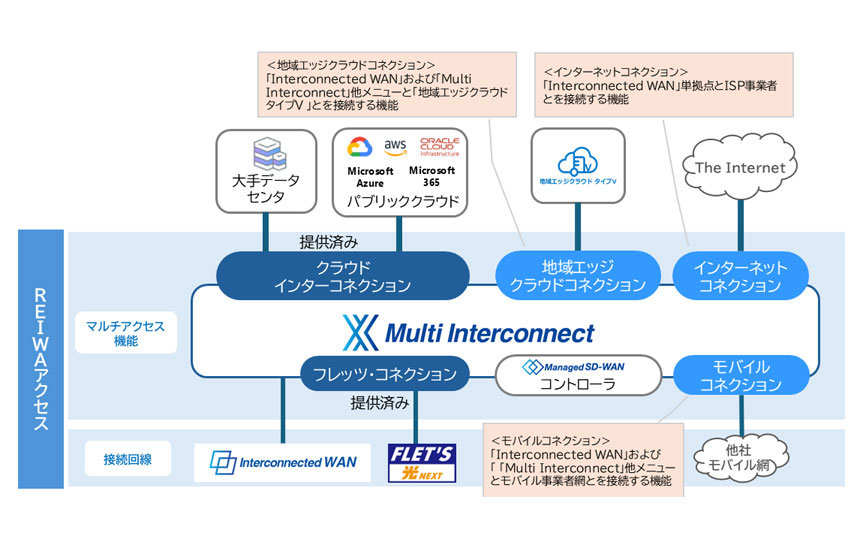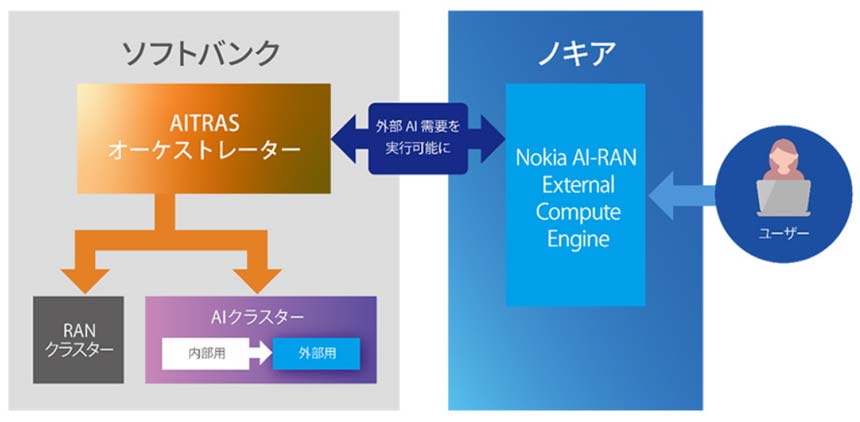世界中の通信事業者から今、熱い注目を浴びているのが、シスコシステムズが提唱する「RON(Routed Optical Networking)アーキテクチャ」だ。
もっと大容量・低遅延の通信サービスを、もっと低コストに――。通信事業者はこうしたユーザーの期待に応えるため、通信インフラを要素ごとに常に研ぎ澄ませてきた。だが、既存のアーキテクチャを踏襲しながら、IP、光伝送といったレイヤーごとに改善を図るだけでは限界がある。本格的なAI時代の到来、6G時代への対応などを見据えれば、個別最適を脱したアーキテクチャレベルでの全体最適が必要だ。
そこでRONアーキテクチャである。「これまで交わってこなかったIPと光伝送が密に連携することで、新しいサービスを創出できる可能性を秘めています」と、シスコシステムズの児玉賢彦氏は述べる。

シスコ APJCサービスプロバイダーアーキテクチャ事業 サービスプロバイダールーティング本部
ソリューションズエンジニア 児玉賢彦氏
光伝送装置の機能分割とルーターへの再統合
通信ネットワークを構成する機器はレイヤーごとに分かれ、それぞれ特定の機能に特化して提供されるというのが長年の常識だった。ルーターはIPパケットのルーティングに、光伝送装置はルーターから受け取ったトラフィックの大容量・長距離伝送に専念することで、ユーザー要件を満たす安定した通信をこれまで実現していた。
だが、スマートフォンやIoT、そしてAIの時代を迎え、次々と新たなアプリケーションが誕生しては、新たなトラフィック需要を爆発的に生み出すのが現代だ。
シャーシ型の光伝送機器を前提とした従来のアーキテクチャでは、ルーターと光伝送機器の両方で物理と論理の作業が必要になり、柔軟かつ迅速にネットワークキャパシティをスケールさせたり、新技術を追加することは困難である。また、シャーシ型の場合、将来の需要増を見越して、余裕を持ったスロット数で導入するケースが多いだろう。未使用の期間は、そのスロット分のスペースと電力を無駄にすることになる。キャパシティプランニング、コスト、サステナビリティなど様々な面で、シャーシ型の限界が見え始めている。
そうしたなか、光伝送装置の世界で進展してきたのが、「ディスアグリゲーション(機能分離)」という潮流だ。従来1つの機器で一体提供されてきた光伝送機能を、それぞれの機能に分離して提供する。これにより、特定の機能だけをアップグレードし、最新の技術進化を取り入れたり、パフォーマンスを向上させることが容易になった。
さらに、このディスアグリゲーションと同時並行で起きているのが、IPと光伝送の垣根を乗り越えての「レイヤー統合」である。つまり、ルーターでIPルーティングと光伝送を統合的に行う。
これを可能にするのが、IP over DWDMの流れをくむRONアーキテクチャであり、RON実現のカギの1つが「コヒーレント光トランシーバー(Coherent Optics)」の登場である。
児玉氏が解説する。
「以前の光伝送装置は一体型で、シャーシに挿すカードによってトランスポンダーやROADM、光アンプなど、すべての機能を搭載していました。そこにディスアグリゲーションが起き、小型化したトランスポンダー機能を光トランシーバーの中へ搭載可能になりました。このコヒーレント光トランシーバーをルーターに挿せば、ルーターで光伝送を実現できます。通信事業者にとって新たな選択肢が生まれており、日本でも採用が増えています」
シャーシ型の光伝送装置に替えて、ボックス型ルーターに挿したコヒーレント光トランシーバーで光波長を直接送出することにより、省スペース化が図れるうえ、消費電力もポートあたり150W程度から24W程度へ大幅削減できる。ネットワーク全体で考えると数百、数千ポートになるため、その削減効果はかなり大きいといえる。また、IPと光伝送で構成される広域転送ネットワーク全体がシンプルになるため、ネットワークの自動化の導入もしやすくなる。その結果として、競争力のある料金で、高品質な通信サービスを提供する基盤が整うのだ。
このように、サステナビリティを意識しつつ、広域転送ネットワークのシンプル化と通信サービスの高度化を同時に実現できるRONアーキテクチャは、すでに国内でも多くの通信事業者が採用しており、「2018年頃は、RONのコンセプト自体は理解されても、『本当にそうした世界が実現されるのか』と懐疑的な見方もありました。しかし、導入が進み始めた今、通信事業者側から『次の一手はないだろうか』とリクエストされるほどになっています」(児玉氏)