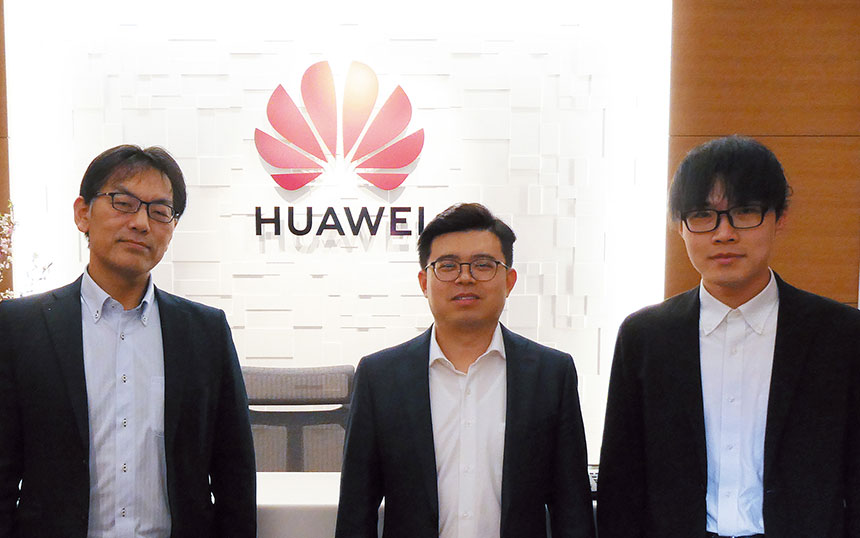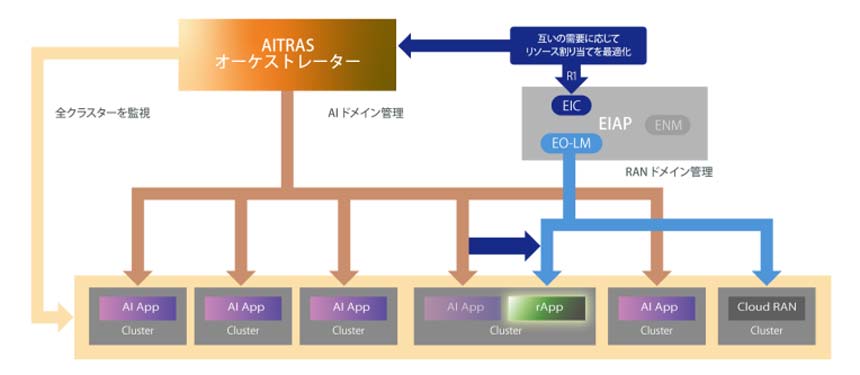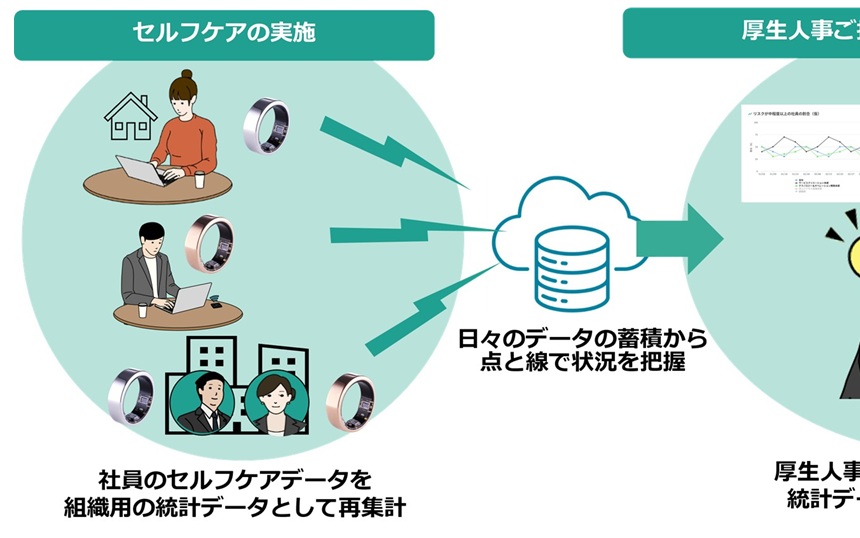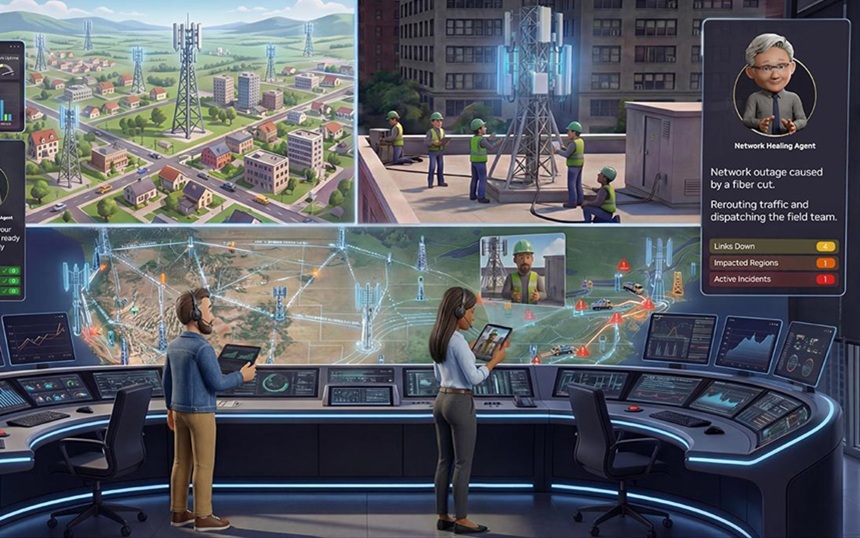2010年12月に日本初となるLTEの商用サービスをスタートさせるNTTドコモは、世界でも最もLTEに意欲的な通信事業者といえる。
その根拠の1つは、LTEが「ドコモ発」の技術であることだ。ドコモは2004年に「スーパー3G」構想を発表、その開発を進めてきたが、このスーパー3Gをベースに3GPPで標準化されたのがLTEである。
スーパー3Gは、現行3Gから4G(ITUで検討中の「IMT-Advanced」)への移行を円滑に進めるための中間的なシステム(3.9G)としてドコモが提唱した通信規格である。IMT-Advancedは、100MHz近い広い搬送波幅の利用を可能にするOFDMAを基盤とし、MIMOなどの技術も駆使することで、1Gbpsクラスのモバイルデータ通信を実現するものだ。スーパー3Gは、こうしたIMT-Advancedの技術要素を用いたうえで、現行の3G帯域にも導入可能なシステムとして考案され、さらにIMT-Advancedと共通運用することが想定されていた。ドコモの次世代インフラ戦略は、このコンセプトを踏まえたものである。
W-CDMA/HSPAを導入している欧州の通信事業者の多くは、HSPA+やDC-HSDPAなど3.5Gの発展システムを経て、LTEへの更新を進める意向である。これに対して、ドコモはそうしたステップを踏まず、直接LTEに置き換えるアグレッシブな展開を計画しているのだ。
ただし、早期の実用化を優先した結果、ドコモ単独でのシステム立ち上げとなり、後日、世界標準とのズレを埋めるための設備改修を余儀なくされたW-CDMAの教訓をLTEでは踏まえている。ドコモは標準化や相互接続性の確保などの活動に力を注いでいるほか、商用化の時期についても欧米の先行グループと歩調を合わせた。
2GHz帯をメインバンドとして選択した2つの理由
ドコモの次世代インフラ戦略の特徴は、2GHz帯をLTEの主力バンドとして想定している点である。2GHz帯は3Gの世界共通バンドで、ドコモはこの帯域を中心にW-CDMA/HSPAのサービスエリアを整備している。
海外では、2GHz帯にHSPAの高度化システムを導入する動きが主流となっており、現時点で2GHz帯でのLTE本格展開を表明しているのは、世界でもドコモだけだ。
ドコモがLTEの主力バンドに2GHz帯を選択した理由には、大きく次の2つが考えられる。
1つはネットワーク容量を確保できること。ドコモは2001年に2GHz帯でW-CDMAによる3Gサービス「FOMA」をスタートしたが、PDCの主力帯域である800MHz帯に比べ2GHz帯は伝搬特性が劣ることから、不感地対策のために都市部を中心に多数の基地局を設置することを迫られた。ドコモの2GHz帯の基地局数4万5000以上は、通話エリアへの評価が高いKDDIの旧800MHz帯基地局数の実に3倍強に相当する。
ドコモはこの高密度の基地局配置をHSPAのデータ通信容量の拡大につなげる戦略を採っており、さらに基地局には一般的な3セクター構成の倍近い容量が得られる6セクター構成を採用している。ドコモはこうして実現した大容量インフラを生かし、KDDIやソフトバンクに先駆けて、映像系サービスやPC向けのデータ通信サービスの本格展開に踏み切っている。この基地局群をLTE化することで、圧倒的な競争力を持つインフラが実現できるのだ。
もう1つは帯域幅である。ドコモが3Gを展開している帯域のうち、新800MHz帯と1.7GHz帯は割当幅が各15MHz幅だが、2GHz帯には唯一20MHzの連続した帯域幅がある。そのため、将来フルスペックの下り173Mbps(端末規格上は150Mbps、以下括弧内の伝送速度は同様)のデータ通信を実現できる可能性があるのだ。LTEのエバンジェリストであるドコモにとってこれは重要なファクターとなる。
W-CDMA/HSPAを現在運用中の2GHz帯にLTEを導入できるのは、LTEの周波数利用効率がHSPAの3~4倍と高いためだ。LTEによる高速化に伴い大幅にトラフィックが増えなければ、ユーザーをLTEに移行させることで同一帯域に数倍のユーザーを収容できる。LTEはW-CDMA/HSPAと同じ5MHz幅にも対応するので、こうした運用が容易に行えるのである。この手法はドコモがスーパー3Gの構想を発表した当初から考えられていたものだ。
その意味では、2009年6月に割り当てられた1.5GHz帯は、ドコモにとって「想定外」の帯域であり、その役割はLTEトラフィックの受け皿として、2GHz帯を補完するものにとどまる。とはいえ、もちろん新帯域の利用によるキャパシティの拡大はドコモのサービスの可能性を広げることになる。