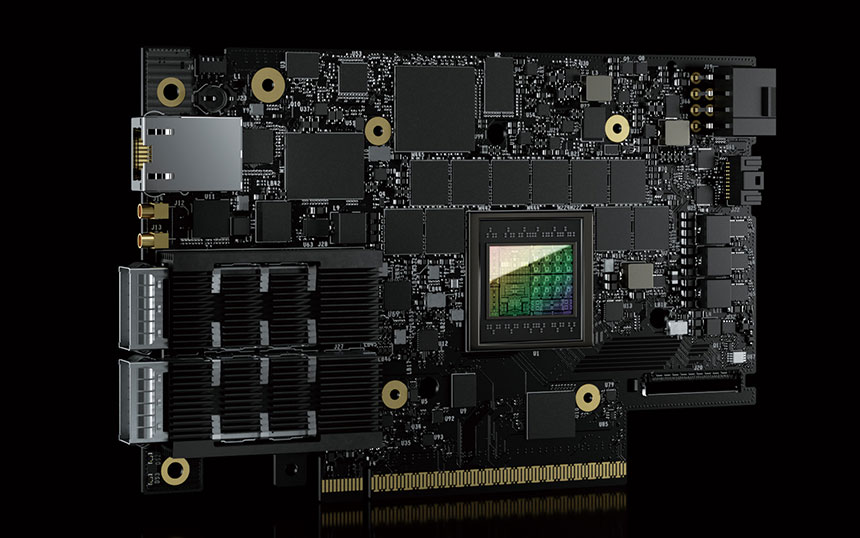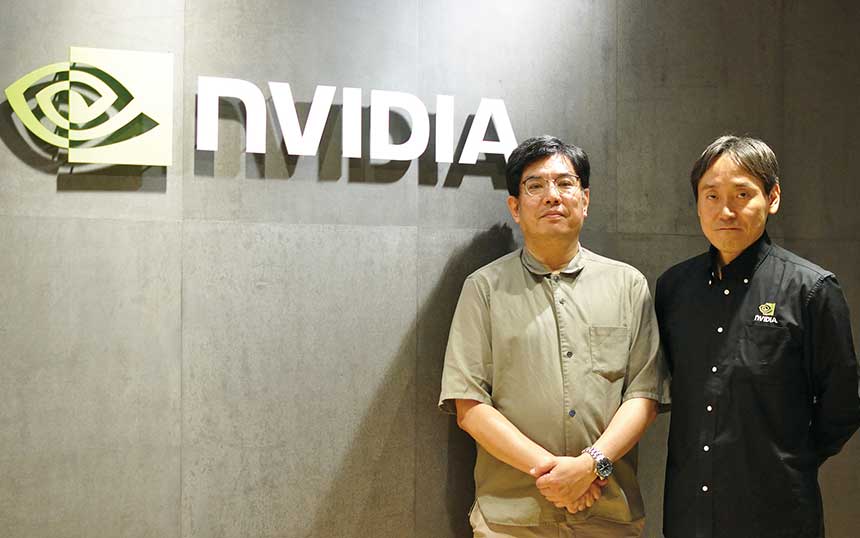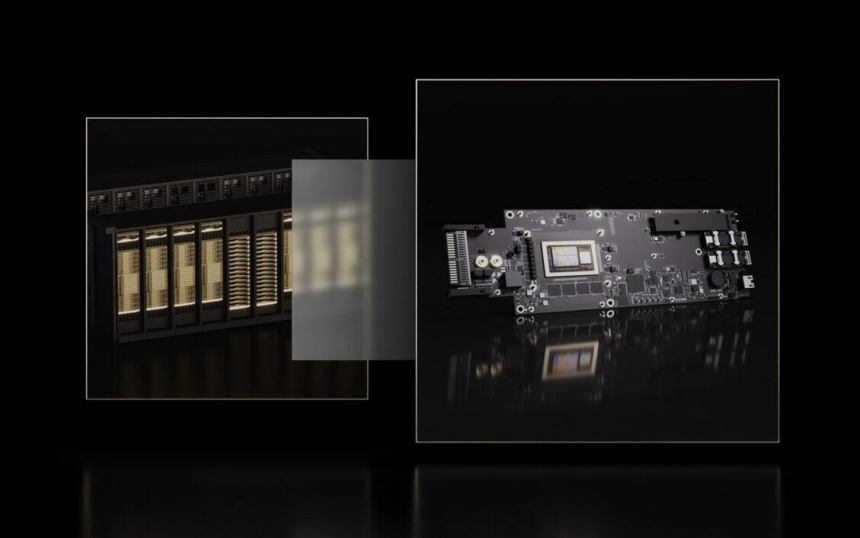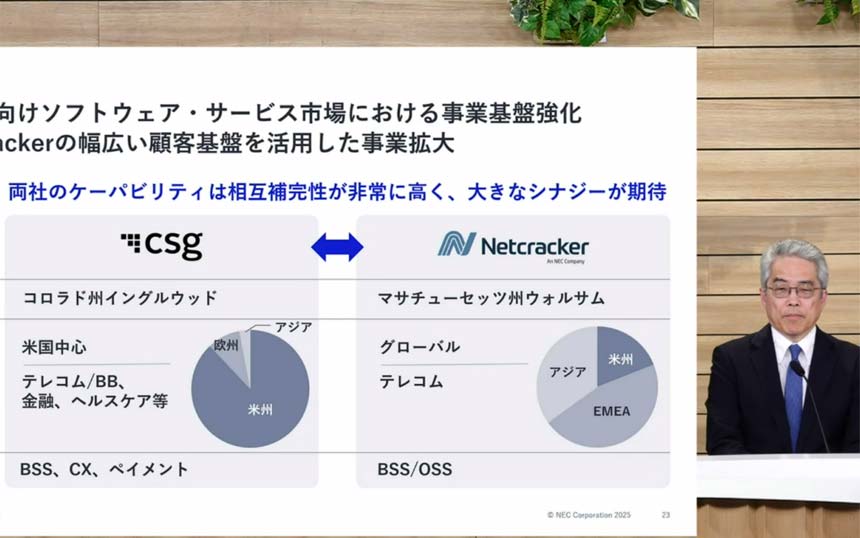2024年1月のWi-Fi 7正式発表から早くも1年半。6GHz帯とMLO等の新機能の魅力は大きいものの、未だにアクセスポイント(AP)の価格が高いことなどから、導入をためらうユーザーも多い。現時点で市場に出ているWi-Fi 7対応APはハイエンド向けかミドルレンジが大半で、導入にはかなりのコストがかかる。普及価格帯の製品が出揃うにはさらに1~2年はかかろう。
現状では、Wi-Fi 5のユーザーが既設APのEoLを迎えて設備更新するケースが大半だ。Wi-Biz 技術・調査委員会 委員の塚本潤氏によれば、「価格が安いWi-Fi 6を選ぶケースがまだまだ多い」。企業で使われている端末もWi-Fi 6が大半であり、「6GHz対応端末への入れ替えとともに、徐々にWi-Fi 7の割合が増えてくるだろう」。
トライバンド移行は意外と早い?
Wi-Fi 5から6への移行期には、APの出荷台数が逆転するには3~4年かかったと見られる。今回のWi-Fi 6から7への移行は、間にWi-Fi 6Eを挟んだこともあって、より長期化する可能性がある。
図表1は、Wi-Fi Allianceの出荷台数予測だ。Wi-Fi 7対応APはドラフト版対応製品が2023年時点から発売されていたが、2028年時点でもWi-Fi 6/6Eと7の台数は拮抗すると見られている。
図表1 2017年~2028年のWi-Fiデバイス世代別出荷台数
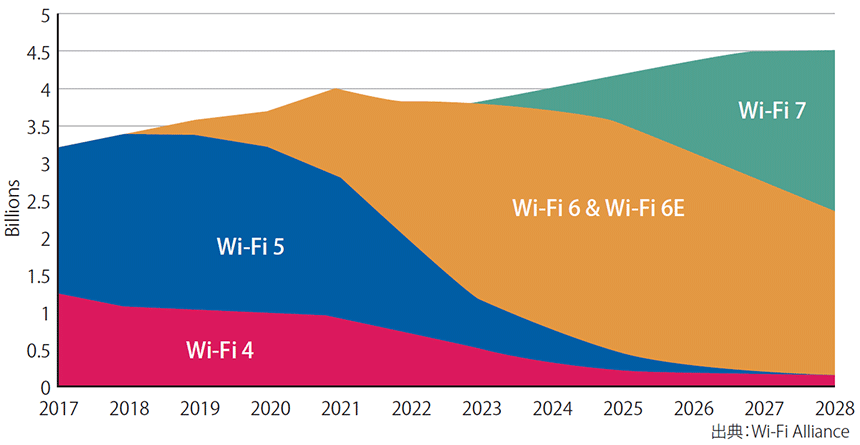
また、Wi-Fi 7対応APのエントリーモデルが出揃っても、価格が即座にWi-Fi 6並みに低廉化するかは疑問が残る。周波数帯が増えたことでチップセットの価格が高くなるからだ。Wi-Biz 技術・調査委員会 副委員長の本橋篤氏は、「トライバンドになるためコストはどうしても高くなる。Wi-Fi 7対応チップセットの価格がこなれてくるまでにはまだ時間がかかる」と見る。
一方、普及が早まる可能性も出てきている。スマートフォンのWi-Fi 7対応が急速に進んでいるからだ。ティーピーリンクジャパン 法人代理店営業部部長の木下裕介氏は、「Wi-Fi 4から5、Wi-Fi 5から6の移行時より、Wi-Fi 6から7への移行がものすごく早い。6GHzに対応しただけで“中途半端”な感じがする6Eよりも、機能が充実したWi-Fi 7への移行が進むだろう」と期待する。
Wi-Fi 6E対応PCやスマホは早くも2022年から登場した。日本における新技術普及の指標とも言えるiPhoneは、2023年9月発売のiPhone 15 Proで対応。グーグルは2022年10月のPixel 7から、サムスンは2023年4月のGalaxy S23からとさらに早い。
Wi-Fi 7対応は2024年9月のiPhone 16、Pixel 9、Galaxy S25、シャープのAQUOS R9、ソニーのXperia 1 VIとさらにスピードが増した。Wi-Fi 7対応チップセットの出荷も順調で、ミドルレンジへの搭載も早まりそうだ。
コンシューマー市場での世代交代は当然、ビジネス向けにも影響する。ホテルや大学のように、出入りするモバイルユーザーにWi-Fiを提供する業種では、“せっかく端末が対応しているのに使えない”という不満を解消するためにも、Wi-Fi 7導入が早まる可能性がある。Wi-Fi設備は導入後5~7年ほど使うことを考えると、少なくとも6GHz帯はサポートしておきたい。
Wi-Fi 6Eと7のどちらを選択するかについては、MLO等に代表されるWi-Fi 7の新機能がどこまで必要かに依る。価格差はWi-Fi 6と7の比較ほど大きくはなく、シスコのように「Wi-Fi 6Eと7は、ほぼ価格差のない状態で販売している」(高橋氏)ベンダーもある。