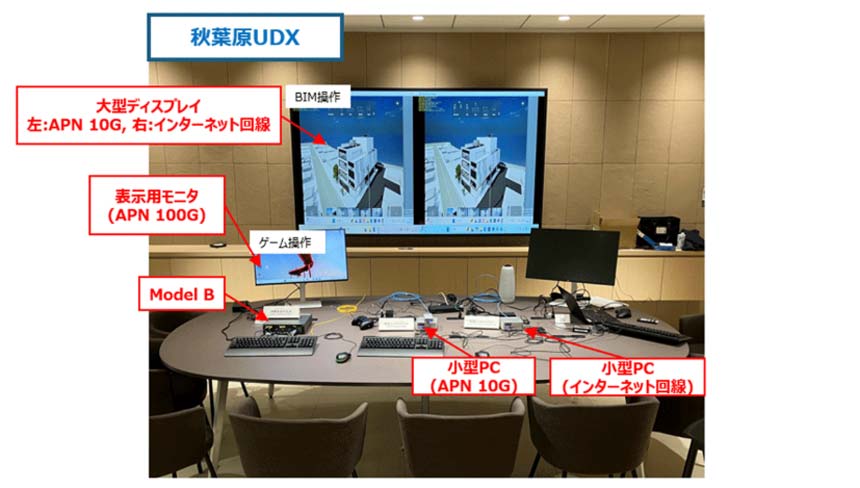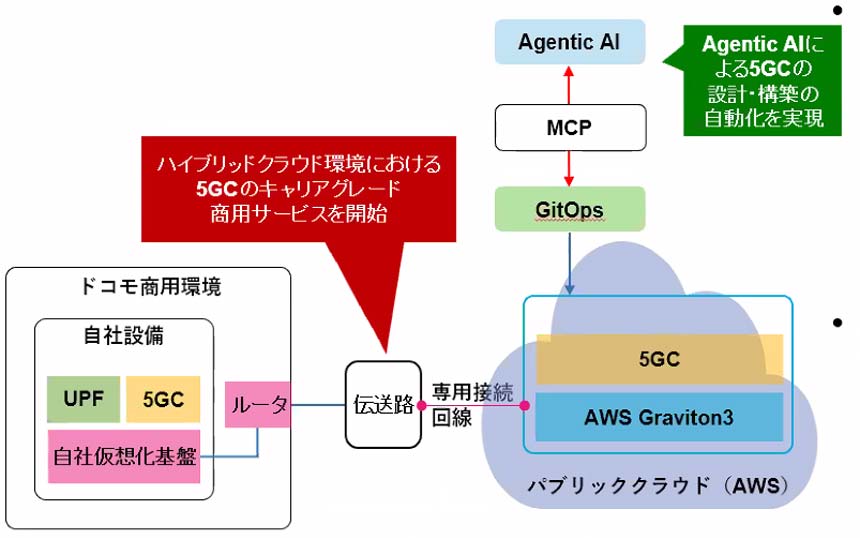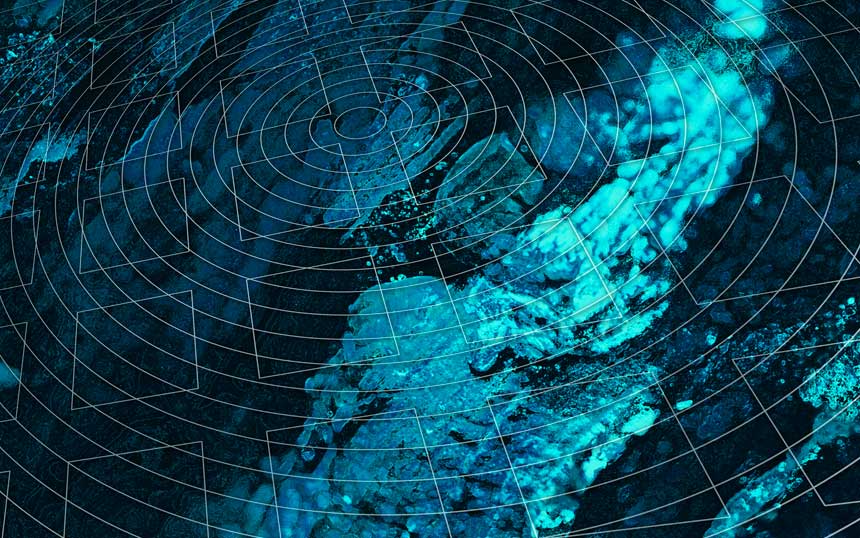2030年代の実用化を目指して世界中で開発競争が激化している量子コンピューター。その競争でキーとなる数字が「100万量子ビット」だ。
量子コンピューターは、新素材や新薬の開発、物流や交通の最適化、暗号解読などの分野で革新を起こす可能性がある。ただし、実用的な問題が解け、汎用的に使える「誤り耐性量子コンピューター」の実現には、最低でも100万量子ビットが必要とされると言われているからだ。
量子ビットは量子コンピューターの情報単位である。古典的なビットが「0」または「1」のいずれか一方の状態しか取れないのに対し、量子ビットは「0」と「1」を同時に重ね合わせられる。観測を行うと必ず「0」か「1」のどちらかに収束するが、計算過程では重ね合わせを活用できる。
さらに重要なのが、量子もつれだ。複数の量子ビットが強い相関を持った状態を指し、まるで1つのまとまりのように振る舞う。一方の量子ビットを測定すれば、その結果は他方の量子ビットの結果に直ちに反映される。
量子計算では、この量子もつれを利用することで量子ビット同士を単なる組み合わせ以上に結びつけ、状態空間(取りうる状態の組み合わせ)全体を効率的に操作する。重ね合わせと量子もつれを組み合わせることで、量子コンピューターは指数関数的に大きな状態空間を扱うことができ、特定のアルゴリズムにおいて古典コンピューターを凌駕する計算能力を発揮すると期待されている。
時分割多重で計算能力アップ
だが、100万量子ビット実現までの道のりは遠い。
現在開発されている量子コンピューターの量子ビット数はようやく3桁に達したところ。東京大学と日本IBMが川崎市に設置している超伝導型量子コンピューターに今年導入するIBMの最新世代プロセッサー「Heron」で156だ。多くの企業が2030年代の100万量子ビット達成を目指しており、量子ビット数を飛躍的に増やすスケーラビリティの実現が勝負の分かれ目となる。
量子ビットを作る実現手法には、超伝導やシリコンなどいくつかの方式があるが(図表1)、このスケーラビリティの観点で注目されている新方式が「光量子コンピューター」だ。他の方式とは異なるアプローチを取ることで、シンプルな構成で高いスケーラビリティを実現することを目指した方式である。
図表1 量子コンピュータの方式(量子状態の実現方式)

光量子コンピューターは、光の波の振幅に量子情報を載せて計算を行う。
超伝導等の他方式は、物理的な空間に量子ビットを並べて数を増やす必要があるが、光方式はこの点が異なる。光の波の性質を活かして、連続的な量を取りながら量子ビットに相当する光のもつれの状態を作る。図表2はそのイメージを示したものだ。東大発スタートアップのOptQC 代表取締役CEO の高瀬寛氏は「量子テレポーテーション(量子状態を遠隔地に転送する技術)を基本原理として、情報を転送しながら同時に処理するアーキテクチャを採用している」と話す。光通信と非常に似た構造であり、「時間的に多重化された情報が一本の伝送路を通り、プロセッサーで処理される」。
図表2 OptQCの光量子コンピューター
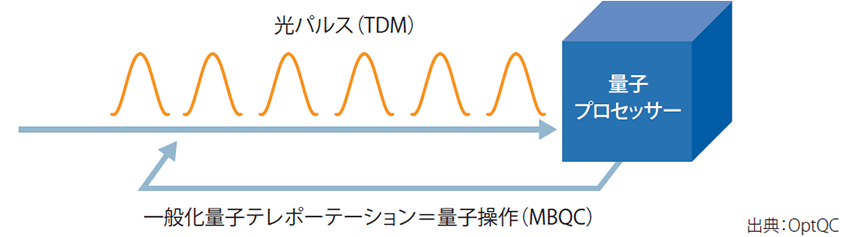
他方式では、ビット数を増やすために素子を増やさなければならないので、サイズもコストも増大する。対して、光方式は時間的に情報を多重できるため、ハードウェアサイズが量子ビット数に比例して大きくならない。簡単に言えば、「光通信における『ブロードバンド化』と同じ原理で情報の密度を高め、計算能力を拡張できる」(高瀬氏)。これが第1の利点だ。

OptQC 代表取締役CEO 高瀬寛氏
この「時間領域多重」は、OptQC取締役CTOのアサバナント・ワリット氏によれば「光通信の多重化とほぼ同じ」だ。さらに、「光通信と親和性を高めるため、1.5μmの通信波長帯を使っている」。

OptQC 取締役CTO アサバナント・ワリット氏
光方式にはもう1つメリットがある。NTT先端集積デバイス研究所 機能材料研究部 上席特別研究員の梅木毅伺氏は「光は非常に熱に強いので、常温で動作する」と話す。極低温や真空の環境を作らなければならない他方式と異なり、データセンターレベルの精密空調環境で動作可能。特殊な冷却装置や真空装置を動かすための電力も不要になる。