700MHz~900MHz帯の電波は携帯電話の世界において「プラチナバンド」と呼ばれている。遠くまで届き、障害物があっても回り込み易いという、無線通信にとっては高い価値がある周波数特性を持つ一方、割当可能な帯域は限られており、携帯電話各社は、プラチナバンドの割当をめぐって数々のバトルを過去繰り広げてきた。
実は誰でも利用することが可能なプラチナバンドもある。LPWAの各方式をはじめ、様々な無線通信方式が使用できる920MHz帯だ。
920MHz帯を利用するIoT無線は、利用者自らが任意の場所にネットワークを構築する「自営系」と、通信事業者が構築したエリア内で利用する「公衆系」に大別できる(図表1)。
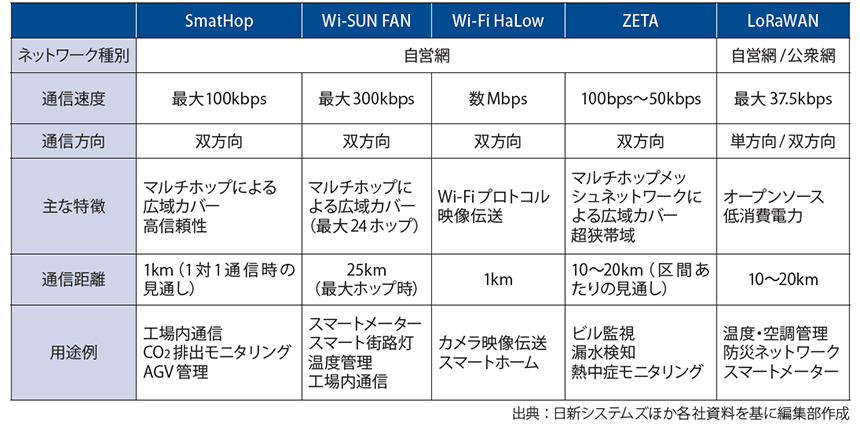
この帯域には915~930MHzが割り当てられており、出力20mW以下の「特定小電力無線局」に該当するシステムが免許・申請不要で利用できる。大量のデータを送るのには不向きとされているうえ、干渉や電波の専有を回避するため、電波の放射を1時間あたり10%(360秒)に抑える「Duty制限」が法令上課せられている。
自営系IoT無線はLoRaWANやZETAといった、低消費電力で低速ながら広いカバーエリアを特徴とする無線ネットワークであるLPWAの存在感が大きい。これらは温度計やスマートメーター、位置情報といったごく限られた量のデータを送るのに用いられてきた。公衆系のLPWAや、LPWA以外の920MHz帯IoT無線でも同様だ。
しかし最近、この“常識”が変わりつつある。2022年9月に国内で商用化が開始されたWi-Fi HaLowは、920MHz帯を利用しながら数Mbpsのスループットを出せ、1kmの距離で映像伝送が可能。すでに監視カメラ運用や、カメラを利用したアナログメーター読み取りなどに活用されている。
最大24ホップのマルチホップでメッシュネットワークを形成し、長い到達距離と不感地帯の容易なカバーを実現するLPWAであるWi-SUN FANは、現行のWi-SUN FAN1.0がアップデートされた「1.1」が早ければ年内にもリリースされる見込み。1.1はOFDMに対応し、スループットは最大2.4Mbpsを達成する。映像圧縮技術の進歩と相まって、高画質映像の伝送も現実的なものとなる。
自営系と公衆系のどちらの方がトータルコストが安くなるかはケースバイケースだが、自営系の利点は必要な場所にきめ細やかにネットワークを構築できることだ。そして、電波が届きやすい920MHz帯はそれに非常に適した帯域であり、人口カバー率を重視する公衆網では手薄になる屋内やへき地などでも自在にネットワークを張り巡らせ、目的に応じた利用が可能だ。
このような特徴を持つIoT無線を、企業や地域社会の課題解決のために使わない手はない。そして、発展するAI技術と組み合わさって、その可能性はさらに広がる。