今や社会生活を支える基盤となった光ファイバーネットワーク。その伝送技術は、飽くなき帯域ニーズに応えるべく高速・大容量化を追求する一方、より経済的に安全・安心な通信サービスを実現すべく日々進化している。
光伝送の適用領域は社会の隅々まで及んでおり、通信事業者の基幹ネットワークや海底ケーブル等の長距離伝送から都市レベルのメトロネットワーク/データセンター間接続(DCI)、アクセスネットワークと幅広い。
光伝送の仕組みと機能光伝送システムは伝送容量や距離、機器構成によって様々な形態があるが、大きく次の2つに分けられる。
光伝送機能に特化した専用装置(光伝送装置)を用いる場合と、電気信号と光信号を変換する機能を持つ光トランシーバーをスイッチ/ルーターに挿して光信号を直接伝送する方法だ。前者は長距離伝送に、後者はデータセンター内や企業LAN等の短距離用途で主に使われるが、100GbEを超える大容量伝送に対応した光トランシーバーの普及と伝送性能の向上により、後者の形態をDCIやメトロ/アクセスネットワークでも活用するケースが増えてきている。
光伝送システムの機能・構成は次の通りだ(図表1の上側)。
図表1 光伝送装置の機能分離
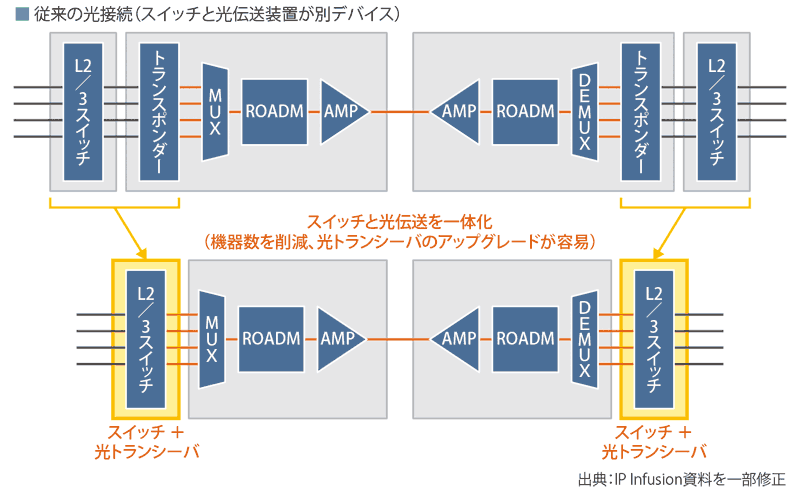
(1)トランスポンダー
電気信号と光信号を相互に変換する。スイッチ/ルーターから受けた電気信号を光信号に変換して伝送し、受信側で電気信号に戻す。
(2)波長分割多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)
複数の波長の光信号を同時に送出し(図表1のMUX)、1本の光ファイバーで伝送する機能。多重して送られた波長は受信側で分割される(DEMUX)。CWDMとDWDMの2方式があり、DWDMのほうが光ファイバー1本当たりの収容数が多い。
(3)光アンプ(光増幅器:AMP)
光ファイバーを通るうちに減衰した光信号を増幅する。概ね60~80km程度で増幅が必要になる。
(4)ROADM(reconfigurable optical add/drop multiplexer)
複数拠点の光伝送装置をつなぐ場合に中核となる機能で、WDM波長から光のまま任意の信号を取り出したり、信号を加えたりする(add/drop)ことで、光パス(経路)を制御・管理する。
トランスポンダーを機能分離数kmを超える中・長距離用途では従来、(1)トランスポンダーから(4)ROADMまでを単一ベンダーが提供するのが主流であり、現在もその形態が多いが、このうちトランス
を光伝送装置から分離するディスアグリゲーション(機能分離)が近年進んできた。光電変換機能を光に集約した「プラガブルモジュール」をルーター/スイッチに挿入して直接光信号を送出する。
スイッチとプラガブルモジュールの組み合わせで光伝送を行う場合は、光伝送装置に比べて出力が弱いため伝送距離は短くなるが、高価な専用装置が不要になるコストメリットが大きく、ポイントツーポイントの拠点間接続等で使われている。
IPネットワークと光伝送の管理・運用を統合できる利点もある。スイッチ/ルーター側のOS/ソフトウェアの対応が必要になるが、機器点数を減らせるうえ、光/IPネットワークを単一ソフトウェアで統合運用することでOPEXの削減も期待できる。
また、図表1の下側のように、DWDMやアンプ、ROADMと組み合わせて長距離伝送する場合にも利点がある。伝送容量の拡張が容易になることだ。
上記の各機能のうちトランスポンダーが最も技術革新が早く、この部分を伝送装置から分離することで、迅速かつ容易に伝送容量を増やせる。各機能をつなぐインターフェースがオープン化することでマルチベンダー構成も可能になり、ユーザーは選択肢の増加、価格競争によるコストダウンといった恩恵を享受できる。
OSを搭載しないホワイトボックス型のスイッチ/伝送装置を活用して、このディスアグリゲーションを推進しているIP Infusion会長で親会社ACCESSのCTOを務める植松理昌氏は、トランスポンダーの分離は「5~6年前からできており、DCIや通信事業者にも入り始めている」と話す。メトロ・アクセスネットワークでも同社のネットワークOS「OcNOS」が広く利用されており、「2020年はコロナの影響でインフラ見直しの機運がいったん下がったが、2021年は将来を見据えてオープン化を始める動きが増えた」。