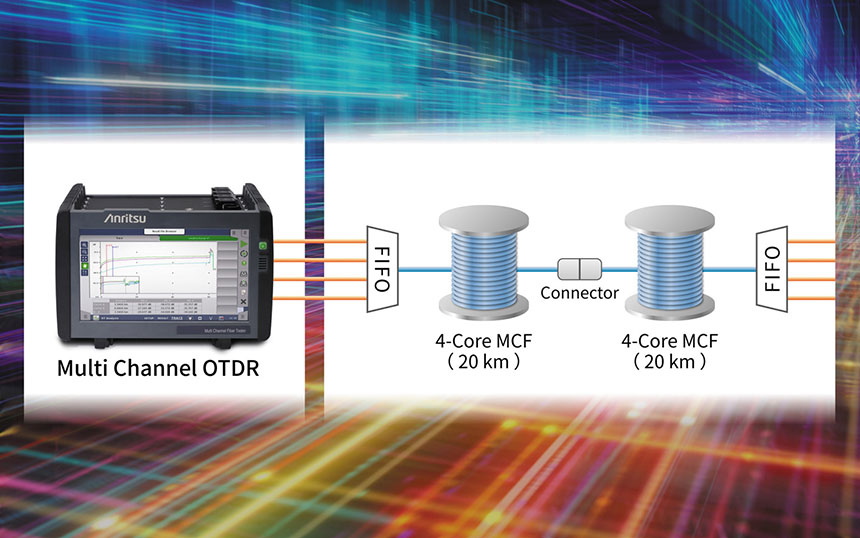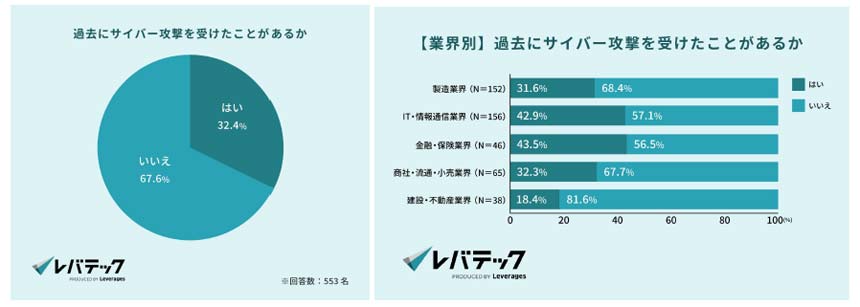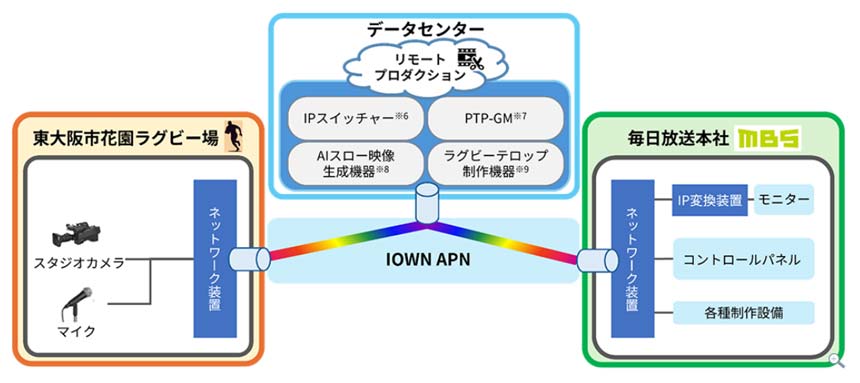イー・モバイルが2010年10月から提供予定のDC-HSDPAは、同社がこの7月から展開している21Mbps対応HSPA+の搬送波を2本束ねることで、下り最大42Mbpsの通信速度を実現するシステムである。
イー・モバイルは、すでに人口カバー率にして約60%のエリアで21Mbpsのデータ通信サービスを提供している。また、21Mbps対応HSPA+基地局の一部では、2009年6月に新たに割当を受けた1.7GHz帯10MHz幅のうちの5MHz幅の運用を今年1月からスタートさせた。トラフィックの集中する大都市圏の運用帯域をこれまでの1波5MHz幅から2波10MHz幅に広げることで、ネットワーク容量の大幅な拡大を実現しようとしているのだ。
DC-HSDPAサービスは、これらの2波運用基地局群をソフトウェア更新によりDC-HSDPAにアップグレードさせることで実現する。開始時期は前述の通り10月。まずは大都市圏から提供を始め、順次サービスエリアを拡げていく計画である。
総務省が2009年6月に公表した携帯4事業者の基地局整備計画によれば、イー・モバイルは2014年度末までに6388の基地局をDC-HSDPA化し、全国の主要都市で42Mbpsサービスを展開するとしている。2014年度末時点の人口カバー率は75.2%だ。
イー・モバイルは2010年6月末までに約9000局の基地局を整備、人口カバー率91.5%のサービスエリアを構築している。このロケーションを活用することで、人口カバー率75.2%という目標は早ければ2011年、遅くとも2012年には達成できると見られる。これに加えて、DC-HSDPA化しない1波運用基地局も21Mbps対応HSPA+にアップグレードさせれば、イー・モバイルのネットワークの競争力は格段に向上するものと考えられる。
不透明なLTEへの移行計画
総務省公表の基地局整備計画には、イー・モバイルがDC-HSDPAの次のステップとしてLTEの導入を計画していることが記されているが、これにはまだ不透明な要素が多い。
現在イー・モバイルが割当を受けている15MHz幅の帯域では、DC-HSDPAからLTEへ円滑に移行するシナリオが描き難いのである。
先に見た通り、同社が1.7GHz帯に割当を受けている15MHz幅のうち10MHz幅は21Mbps対応HSPA+/DC-HSDPAで使われるので、LTEは残りの5MHz幅に導入されることになる。
だがこの場合、(1)5MHz幅でLTEを運用した場合の最大通信速度は43Mbps(端末ベースで37.5Mbps)でDC-HSDPAと変わらないため、すでDC-HSDPAを利用しているユーザーにとってLTEに移行するインセンティブが働き難い、(2)さらにLTEの帯域を10MHz幅に拡張しようした時点でDC-HSDPAは廃止しなければならないなどの運用上の問題が生じる。円滑にLTEを導入するには周波数の追加取得が不可欠なのだ。
このLTE導入プランは、帯域拡大の必要性をアピールするための「暫定案」とでもいうべきものなのである。
現在、総務省の「グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース」に設置された「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」で、周波数割当施策の見直しが検討されており、この結論次第で、イー・モバイルの次世代インフラ戦略は大きく変わることになるだろう。